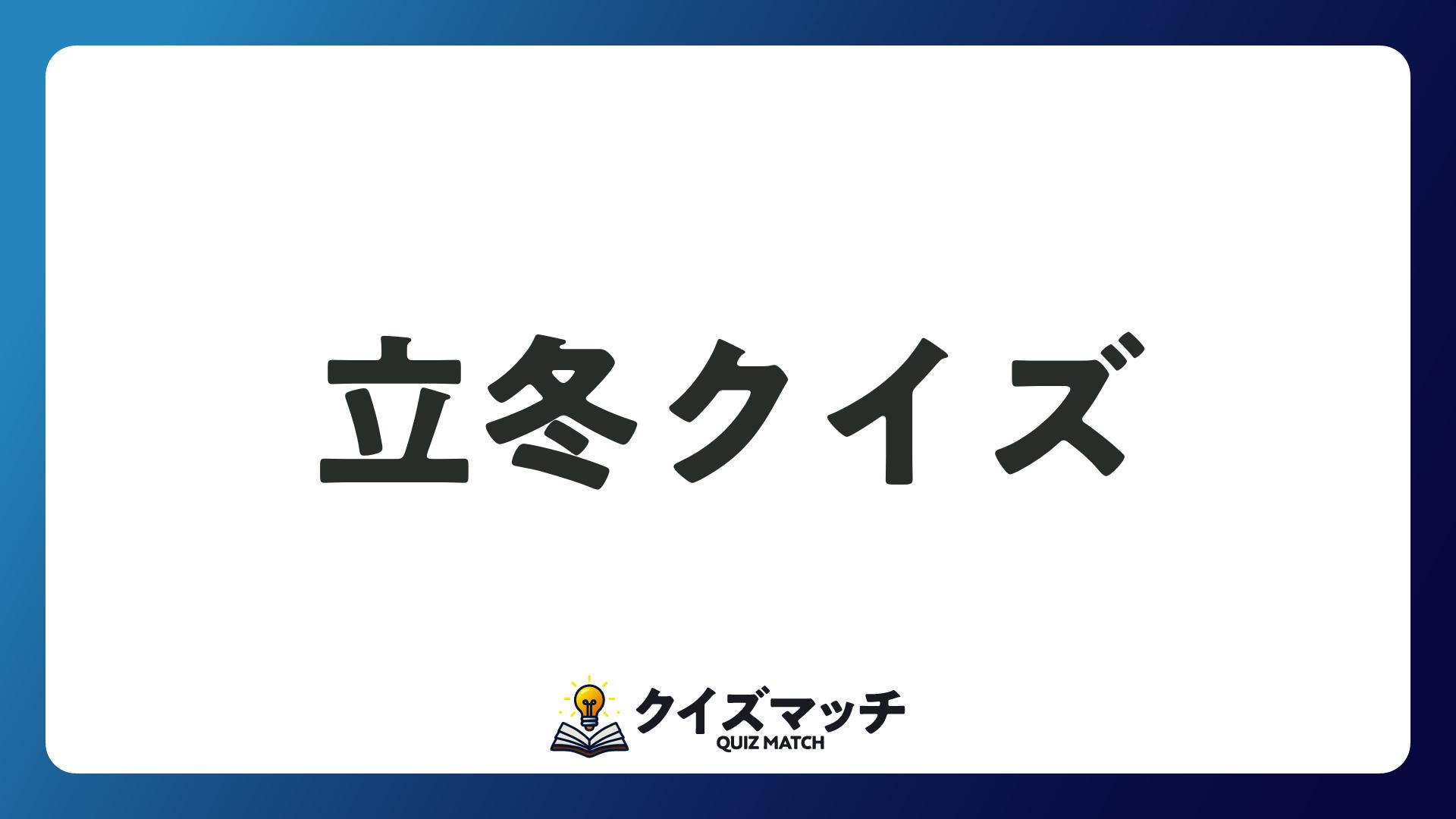立冬は二十四節気の19番目にあたります。二十四節気は太陽の動きをもとに1年を24分割した中国の伝統的な暦法で、日本でも広く使われています。立冬は「冬の始まり」を意味しており、暦のうえではこの日から冬の季節に入ることになります。この記事では、立冬に関する様々な知識を問うクイズを10問ご紹介します。節気の意味や日付、食事や行事など、立冬にまつわる様々な側面について、興味深い問題にチャレンジしていただけます。
Q1 : 立冬の意味を表す言葉として正しいものはどれ?
立冬は文字通り「冬が立つ」、すなわち冬の季節が始まることを表しています。まだ本格的な寒さは訪れていませんが、季節の移り変わりを暦のうえで感じることができます。「冬が一番寒い日」は冬至以降、「冬が終わる日」は立春、「春の始まりの日」も立春を指すので、正解は「冬の気配が現れ始める日」です。
Q2 : 「立冬」を含む季語・俳句で冬の到来を表すのはどれ?
「冬隣」は冬をすぐ身近に感じる立冬の頃の季語・俳句用語で、秋の終わりから冬の始まりに用いられます。春霞は春の風物詩、夏至は夏の現象、秋晴れは秋の安定した晴天を指し、いずれも冬の到来を表す用語ではありません。冬隣は季節の狭間を詠む際の代表的な表現です。
Q3 : 立冬は「冬始まり」を意味しますが、立冬の日以降に行うのが良いとされる日本の伝統行事は?
立冬になると本格的な寒さを感じやすくなるため、日本の家庭では古くから「こたつ開き」(こたつを出すこと)が行われてきました。こたつは冬の代表的な暖房器具で、立冬を機会に防寒体制に入る風習です。七五三、節分、ひな祭りは立冬に限らず別の季節の伝統行事です。
Q4 : 立冬の日に多くの日本の家庭で食べられる伝統的な料理は?
立冬の頃から寒くなり始めるため、温かいおでんが好まれるようになります。おでんは具材をだしで煮込んだ日本の伝統的な冬料理で、体を温めるのにぴったりです。チキン南蛮や冷やし中華は季節的に冷たい料理、ざるそばは夏向けであり、立冬によく食べられる料理とは言えません。
Q5 : 立冬は中国から伝来したものですが、日本の気候に適合していると言われる理由は?
立冬を含む二十四節気は中国発祥ですが、日本も温帯モンスーン気候に属し、春夏秋冬と四季が比較的はっきりしているため、これらの節気が日本の季節感や農作業の目安として伝統的に適してきました。これに対して、亜熱帯気候・乾燥気候・砂漠気候の地域では二十四節気の季節感は必ずしも当てはまりません。
Q6 : 立冬の「立」はどのような意味でしょう?
二十四節気の「立春」「立夏」「立秋」「立冬」に使われる「立」という字は「始まる」「到来する」という意味です。立冬は「冬が始まる」という意味になります。季節の変わり目を示す言葉として、これと同じような用法で使われているのが立春(春の始まり)、立夏(夏の始まり)、立秋(秋の始まり)です。
Q7 : 立冬の頃に旬を迎える野菜はどれ?
立冬の頃に旬を迎える野菜のひとつが大根です。大根は秋から冬にかけて甘みが増し、鍋料理などにもよく使われます。反対に、ナスやトマトは夏野菜、タケノコは春の山菜であり、立冬の時期とは旬が異なります。気温が下がり始める立冬のころは、大根や白菜などの冬野菜の出回る時期になります。
Q8 : 立冬の次の二十四節気はどれ?
立冬(19番目)の次、二十四節気の第20番目にあたるのは小雪(しょうせつ)です。小雪はおおむね11月22日ごろにあたり、本格的な降雪はまだ少ないですが、雪がちらつき始めるころを表しています。大雪(12月上旬)、冬至(12月下旬)、小寒(1月上旬)はいずれも立冬後に続く冬の節気ですが、立冬の直後は「小雪」です。
Q9 : 立冬の日付は太陽暦でおおむね何月ごろにあたるでしょう?
立冬は太陽暦(新暦)で毎年11月7日ごろにあたります。旧暦ではその年によって日付がずれることもありましたが、現在は太陽の黄経が225度になる日を立冬と定めており、多くの場合11月7日か8日となっています。よって「11月上旬」が正解となります。
Q10 : 立冬は二十四節気の第いくつ目ですか?
立冬は二十四節気の19番目にあたります。二十四節気は太陽の動きをもとに1年を24分割した中国の伝統的な暦法で、日本でも広く使われています。立冬は「冬の始まり」を意味しており、暦のうえではこの日から冬の季節に入ることになります。第19節気であり、この次は小雪(20番)、その前が霜降(18番)となっています。
まとめ
いかがでしたか? 今回は立冬クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は立冬クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。