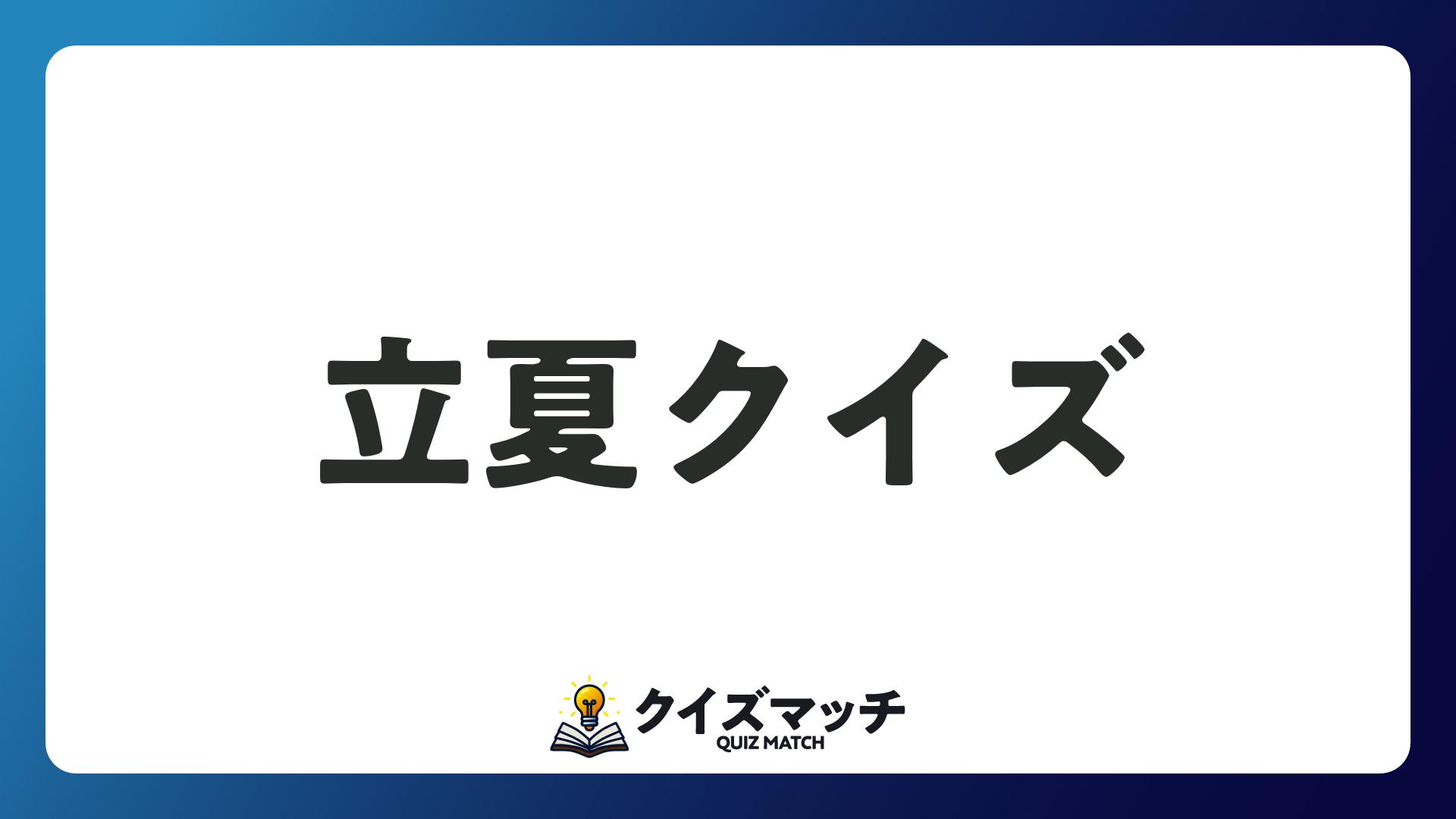二十四節気の一つ「立夏」を、楽しみながら学べるクイズ特集をお届けします。立夏は5月上旬を中心に訪れ、春から夏への移り変わりを告げる大切な季節節目です。暦の上では夏の始まりを示しますが、実際の気候とはズレがあるのも特徴です。そんな立夏の意味や風習、自然の様子など、様々な角度から10問のクイズにチャレンジしてみましょう。二十四節気の知識を深めるとともに、季節の移ろいを感じ取ることができるはずです。
Q1 : 立夏には昔からどのようなことを始めるのが良いとされてきたでしょうか?
立夏は、生命力や成長のエネルギーが高まる時期と考えられ、新しいことや始めたいことに着手するのに良いとされてきました。旅や断食、冬支度とは違い、スタートの時期としての意味合いがあります。
Q2 : 立夏を含む「夏」の期間は、二十四節気の中ではおよそどの期間でしょう?
二十四節気では、立夏から始まり、立秋までが夏の期間とされています。その後、立秋で暦の上では秋となりますが、実際の気候とずれることも多いです。立夏から立秋までが「夏」です。
Q3 : 立夏の頃に日本でよく見られる自然の風物詩は何でしょう?
立夏の頃は、日本の各地で田植えが始まる大事な時期です。稲刈りは秋、雪祭りは冬、ブドウ狩りは晩夏以降から秋にかけて行われます。立夏は農事暦上も転換点となる重要な季節です。
Q4 : 立夏に食べると良いとされる和菓子は次のうちどれ?
立夏は端午の節句と時期が重なるため、端午の節句に食べられる柏餅が選ばれます。柏の葉で包んだ柏餅は「家系が絶えない」縁起のよい食べ物として親しまれています。桜餅、笹だんご、羽二重餅とは異なります。
Q5 : 立夏と同じく季節の始まりを示す二十四節気はどれ?
立夏と同じく四季それぞれの「始まり」を示す節気には「立春」「立夏」「立秋」「立冬」があります。中でも「立春」は春の始まりを示し、「立夏」と並んで、季節の変わり目の大事な節目です。芒種、処暑、小雪は各季節の途中で訪れます。
Q6 : 立夏の頃、日本の気候や自然の変化にあらわれやすい現象はどれでしょう?
立夏の時期は、春が終わり本格的な新緑の季節となります。木々や草花は青葉をしげらせ、自然が生命力に溢れる時期を迎えます。桜は春、紅葉は秋、雪は冬に目立つ現象です。
Q7 : 立夏の由来となった「〇〇が立つ」という言葉の〇〇に入るのは?
立夏は、「夏の気配が立つ」つまり夏の始まりを告げる時期です。このため「夏が立つ」という意味です。「立春」「立秋」も同様に、それぞれの季節の始まりで使われています。
Q8 : 「立夏」を迎えると、日本の五節句のうち、どの節句が近いでしょうか?
立夏は5月5日ごろで、同じく5月5日に行われるのが端午の節句です。端午の節句は男の子の健やかな成長を願う日で、鯉のぼりや柏餅が有名です。その他の節句は主に春や夏・秋に行われるため違います。
Q9 : 「立夏」は、一年を24に分けた二十四節気の何番目にあたる節気でしょうか?
立夏は二十四節気のうち7番目にあたる節気です。春分や清明、穀雨が終わり、立夏を迎えることで暦の上では春から夏へと移り変わります。二十四節気の構成上、7番目が正解です。
Q10 : 二十四節気の一つである「立夏」は、通常、現代の暦(グレゴリオ暦)ではおおよそ何月に訪れるでしょうか?
立夏は二十四節気の一つで、春が終わり、夏の気配が立ち始める時期を指します。現代のグレゴリオ暦では、ほぼ毎年5月5日ごろから始まります。気象的な夏の到来とはややずれますが、旧暦や農事暦では重要な節目です。4月や6月、7月ではなく「5月」が正解です。
まとめ
いかがでしたか? 今回は立夏クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は立夏クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。