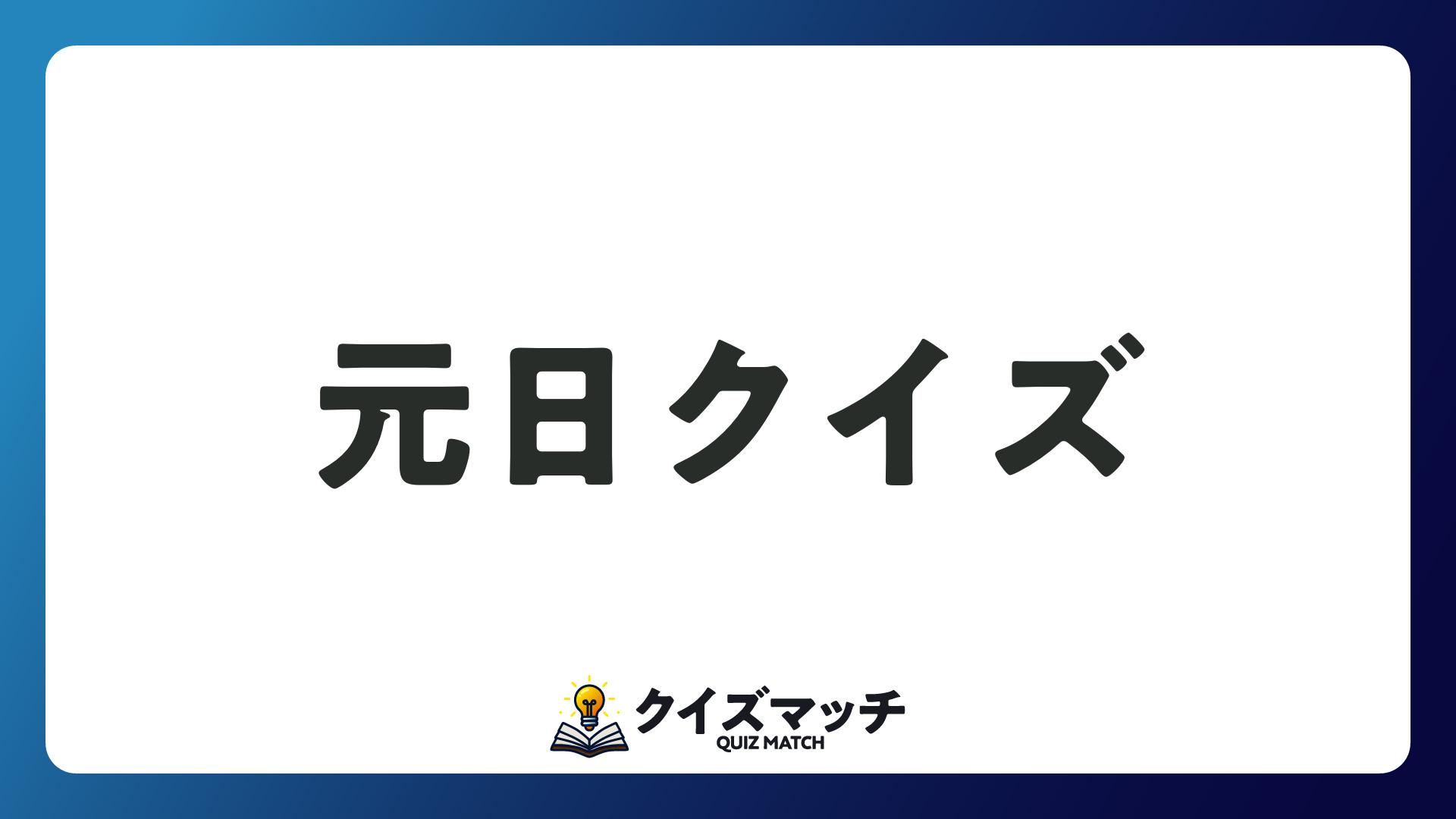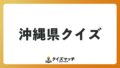新年を祝い、日本の伝統と文化を彩る元日クイズ。1月1日の”元”の意味や、お正月ならではの風習、神事などを10問でご紹介します。元旦の食事、祭祀、遊び、そして年中行事の歴史を学び、2023年の幕開けを心から祝福する一助となれば幸いです。年の変わり目に思わずおどろくような発見があるかもしれません。新年早々、楽しい知的好奇心を刺激するクイズにどうぞご期待ください。
Q1 : 日本の宮中で元日に行われる伝統行事は何でしょう?
「歌会始」は宮中で元日に行われる伝統行事のひとつです。天皇や皇族、選ばれた人たちが和歌を詠む行事で、1月初旬に開催されるのが慣例です。日本の文化や伝統を象徴する行事の一つです。流鏑馬・田植え式・けまりは元日の宮中儀式ではありません。
Q2 : 元日によく見かける「羽根つき」という遊びの羽根には、ある鳥の羽が使われてきました。それはどの鳥?
伝統的な羽根つきの羽根には「つばめ」の羽が使われてきました。つばめは害虫を食べてくれる益鳥であることから縁起が良いとされ、お正月の遊びに最適と考えられてきました。現在は人工の羽も使われています。
Q3 : 日本で元日が祝日(国民の祝日)となったのは何年からでしょう?
日本の元日が「国民の祝日」として正式に制定されたのは1948年(昭和23年)です。この年に祝日法が公布・施行され、制度として現在の「元日」が定められ、一般的な祝日となりました。それ以前は伝統的行事として祝われていました。
Q4 : 元日に神社やお寺で鳴らされる鐘のことを何というでしょう?
元日にかけて大晦日の夜に鳴らされる鐘は「除夜の鐘」です。一般的には大晦日に108回撞かれ、人間の煩悩を払い清めて新年を迎えるための仏教儀式です。元日にも余韻として聞かれることがありますが、「年越しの鐘」や「元旦の鐘」という呼び名は使われません。
Q5 : 元日によく使われる季語はどれでしょう?
「初春(はつはる)」は、元日や新年によく使われる季語です。暦の上で春の始まりを示す言葉であり、俳句や詩歌で元日や新年の情緒を表現する際によく登場します。「晦日」「秋分」「小寒」は元日の季語ではありません。
Q6 : お年玉の風習の起源とされるものは何でしょう?
お年玉の起源は、もともと年神様に供えた餅(年玉)を家族や子供に分け与えた風習に由来しています。時代の流れで、餅が小銭や紙幣に置き換わり、現在の「お年玉」としてお金を贈る習慣が定着しました。
Q7 : 中国で新年に行われる行事『春節』は元日と同じ日に行われますか?
中国の春節は旧暦(農暦)の1月1日にあたる日であり、毎年異なる日程になります。日本の元日(1月1日)とは通常一致しません。春節はアジアの多くの国でも重要な新年行事となっていますが、グレゴリオ暦の1月1日とは異なるため、同じ日ではありません。
Q8 : 元日に行われる伝統行事の一つ「初詣」でお参りする主な目的は?
初詣は、新年を迎えた最初に神社や寺に参拝し、去年一年の感謝を伝えるとともに、新しい年の無事や家族の安全、健康などを祈願する日本独特の文化です。特定のお願いよりも、年の始まりの挨拶や感謝が重視されています。
Q9 : お正月に食べる「おせち料理」は元日になぜ食べられるようになったでしょうか?
おせち料理は、年神様(としがみさま)をお迎えし、もてなすために作られる料理です。年神様は新年に各家庭を訪れる神様で、おせち料理はその神様に捧げる料理として古くから伝えられています。また、保存がきくものが多く、元日は料理をしなくて済むようになっています。
Q10 : 元日の「元」は何を意味している言葉でしょうか?
「元」は物事の「始まり」を意味します。元日は年の最初の日であるため、「元年」「元気」などの「元」と同様に新しい出発点やトップを示します。新年という一つの区切りやスタートを象徴する、昔から使われてきた日本語の核的な表現となっています。
まとめ
いかがでしたか? 今回は元日クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は元日クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。