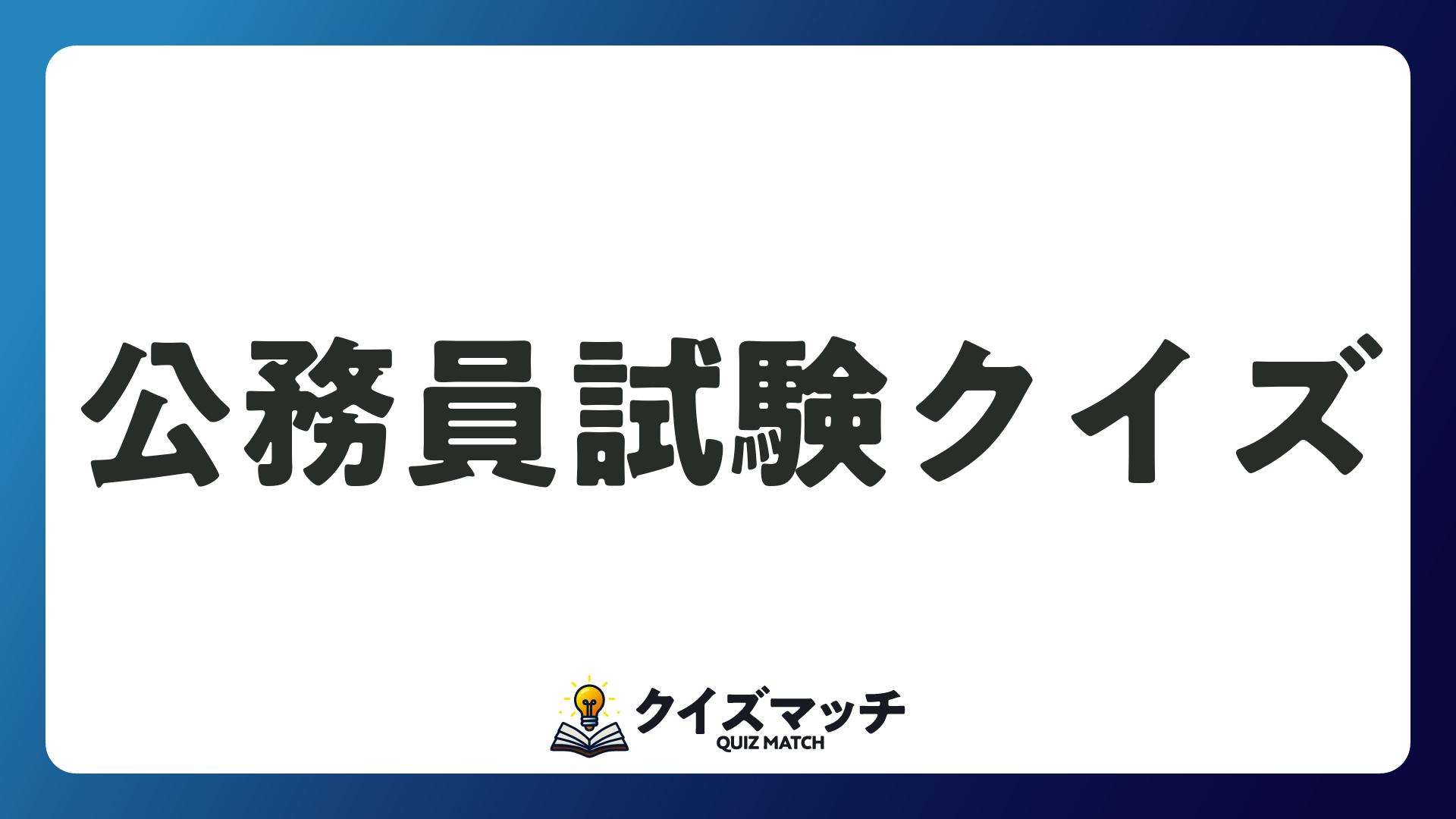日本の公務員試験に合格するためには、国の仕組みや法令に関する基礎知識が不可欠です。本記事では、そのような基礎知識を問う10問のクイズを紹介します。日本国憲法、地方自治、公務員法など、公務員試験に関連する重要なトピックスを網羅しています。公務員を目指す方はもちろん、行政に興味のある方にも役立つ内容となっています。この機会に、自分の知識を確認し、学習の参考にしてください。
Q1 : 国家公務員が守るべき守秘義務の規定があるのはどの法律か?
国家公務員法第100条には、国家公務員の守秘義務が規定されています。これにより職務上知りえた秘密を漏らしてはならないとされており、違反した場合には解雇や懲戒処分だけでなく、刑事罰の対象にもなります。地方公務員には地方公務員法で同様の規定がありますが、国家公務員の場合は国家公務員法が根拠法令となります。
Q2 : 地方債の発行において都道府県が国の許可を必要とする場合とは何か?
地方自治体が地方債を発行する場合、通常は一定の条件下で総務大臣または都道府県知事の許可が必要です。特に起債制限比率が高い自治体や、資金使途が国の定める基準を超える場合に許可が必要です。一方、自主的に発行できる場合もありますが、条件を超える際は必ず許可が必要です。
Q3 : 地方自治体の長の任期は通常何年か?
地方自治体の長(都道府県知事、市町村長など)の任期は地方自治法により原則4年と定められています。ただし、辞任や死亡、リコールなどで任期満了前に職を離れる場合を除き、通常は4年ごとに選挙によって選び直されます。
Q4 : 行政事件訴訟において原則として必要とされる訴訟の種類はどれか?
行政事件訴訟とは、行政庁の違法または不当な処分・裁決に対して私人が訴訟を起こす制度で、「行政訴訟」が正しい名称です。民事訴訟や刑事訴訟、労働審判は別の法的制度であり、行政処分に挑む際は行政事件訴訟法の元で「行政訴訟」を提起します。
Q5 : 公務員が違法な上司命令を拒否した場合、懲戒処分を受けるか?
公務員には法令遵守義務があり、違法な命令は拒否する義務があります。国家公務員法・地方公務員法ともに、違法な命令には従う必要がないと明確に規定されています。したがって、違法命令を拒否したこと自体により懲戒処分を受けることはありません。ただし、命令が正当か否かの判断は慎重さが求められます。
Q6 : 人事院の役割として適切なものはどれか?
人事院は国家公務員法に基づき、国家公務員の給与や人事管理、任用、勤務条件などの監督・勧告を行う行政機関です。国会議員の給与決定や地方公務員、警察職員の直接任命・監督は人事院の権限ではありません。特に給与勧告は毎年国会や政府に対し行われています。
Q7 : 裁判所の中で唯一の憲法裁判所的性格をもつのはどれか?
日本の最高裁判所は、違憲立法審査権を持っており、憲法裁判所的な性格も兼ねています。これは日本国憲法第81条で規定されており、法律・命令・規則・処分が憲法に適合するかどうかを最終的に判断する権限を持つ唯一の裁判所です。他の裁判所も違憲審査ができますが、最終的な判断は最高裁が行います。
Q8 : 民法で『成年』とされる年齢は何歳か?(2022年施行後)
2022年4月1日から民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これにより、18歳に達した者は親の同意を得ることなく契約行為などができるようになり、成人として法律行為を行うことが可能になりました。ただし、飲酒や喫煙、公営ギャンブルなど一部の制限は20歳のままとなっています。
Q9 : 日本で地方自治の本旨を規定しているのは憲法第何条か?
日本国憲法第92条には地方自治の本旨について規定されています。第92条では、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は法律でこれを定める」と明記され、住民自治と団体自治に基づいた地方自治制度の基本原則が示されています。この基本原則を受けて地方自治法などの法律が制定されています。
Q10 : 日本国憲法で内閣総理大臣の任命権があるのはどの機関か?
日本国憲法第6条により、内閣総理大臣の任命権は天皇に属しています。ただし、天皇は国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命します。つまり、最初に国会が総理大臣を指名し、その後天皇が形式的・儀式的に任命を行います。政治的な実質的権限は国会にあり、天皇の任命は形式的なものに限定されています。
まとめ
いかがでしたか? 今回は公務員試験クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は公務員試験クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。