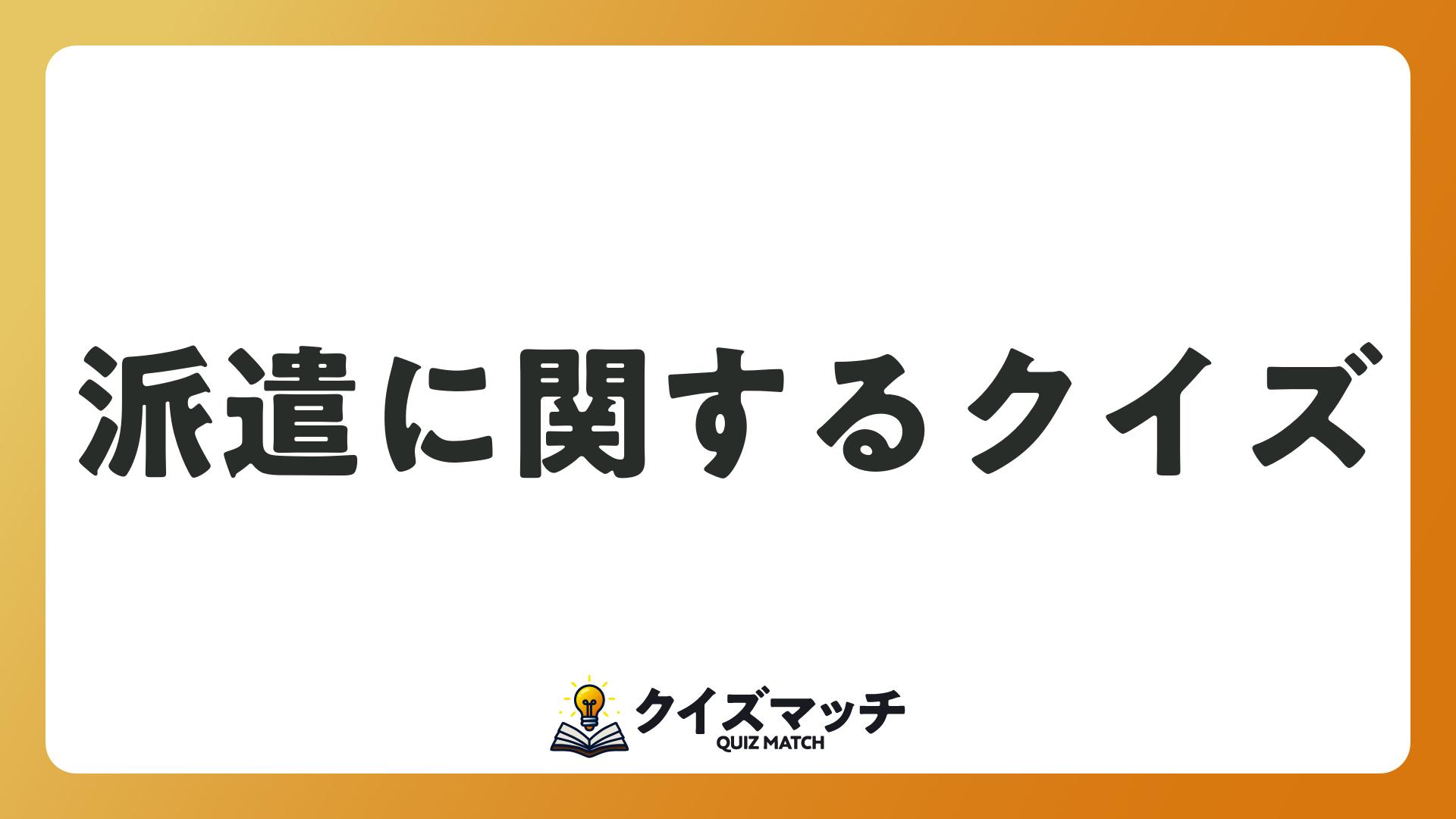派遣に関する知識を深めるための10問のクイズが用意されています。派遣労働者の保護と適正な運用を目的とした2015年の労働者派遣法改正により、無期雇用への切り替え促進や日雇い派遣の制限、派遣労働者の待遇改善など、様々な変更がありました。このクイズを通して、派遣ルールの基本的な内容や最新動向を確認することができます。派遣をめぐる法制度の理解を深めるのに役立つ内容となっています。
Q1 : 派遣労働者が派遣先でセクハラやパワハラを受けた場合、苦情の相談先はどこが適切でしょうか?
派遣労働者が派遣先でハラスメントを受けた場合、まずは雇用契約を結んでいる派遣元事業主に相談することが原則です。派遣元には相談窓口の設置や必要な対応を取る義務があります。その後、適切な対応がなされない場合は労働局や監督署に相談できますが、最初の窓口は派遣元になります。
Q2 : 派遣元責任者の選任が義務付けられる労働者派遣法上の派遣労働者数の基準は?
事業所ごとに労働者派遣を1人でも行う場合、派遣元責任者の選任が法律で義務付けられています。派遣元責任者は主に法令遵守・適正な労働者派遣事業運営を監督し、派遣労働者の保護・管理や派遣先との連絡調整などを担います。人数に関わらず、必須の役割です。
Q3 : 労働者派遣法で定められる“均等待遇”の趣旨はどれでしょうか?
労働者派遣法では、派遣労働者と派遣先の通常労働者との間で、不合理な待遇差をなくす「均等・均衡待遇」が定められています。まったく同じ待遇にする必要はありませんが、説明できない不合理な格差(基本給・賞与・福利厚生など)は認められません。導入により派遣社員の待遇向上が図られています。
Q4 : 派遣労働者を雇用する際、派遣元が必ず書面で明示しなければならない事項はどれですか?
派遣元は、労働条件通知書などにより「業務内容」や「派遣先の名称」「就業場所」「派遣期間」などを明示する必要がありますが、その中でも業務内容は必須記載事項で、仕事の内容が不明確なまま派遣されることを防ぐ目的があります。そのため「業務内容」を必ず書面で明示しなければなりません。
Q5 : 労働者派遣事業の許可を得る際に必要な基準として“資産要件”があります。この要件として正しいものはどれでしょう?
労働者派遣事業の許可を受けるには、純資産2千万円以上、または現金・預金1,500万円以上などの資産要件があります。これは事業運営の安定性を確保し、派遣労働者の雇用や給与支払いの不安定さを防ぐために設けられたものです。資本金や負債超過ではなく、純資産額が基準です。
Q6 : 派遣元事業主が派遣労働者に対して講じなければならない義務として正しいものはどれですか?
派遣元事業主は、労働安全衛生法に基づき、派遣労働者に対して定期健康診断を行う義務があります。派遣労働者も派遣元の従業員であり、その雇用者としての義務を果たさなければなりません。社会保険や有給休暇も条件を満たせば義務となりますが、定期健康診断は必須事項です。
Q7 : 派遣法に定められている日雇い派遣の原則禁止の例外に当てはまる職種はどれですか?
日雇い派遣は原則として禁止されていますが、ソフトウェア開発やクリエイティブ系、事務用機器操作など11の業務について例外が定められています。そのため、ソフトウェア開発の業種は日雇い派遣の例外に該当します。他の選択肢は原則禁止となる業種です。
Q8 : 派遣先が派遣労働者に対して直接指揮命令を行うことはできますか?
派遣労働契約において、派遣労働者の指揮命令者は派遣先となります。派遣元は雇用主ですが、仕事の指示や命令については派遣先の指揮命令に従います。これが職業紹介との違いの一つです。したがって、派遣先が指揮命令を出すことができます。
Q9 : 2015年の派遣法改正で、同一の派遣労働者が同じ組織単位で働ける期間は原則最大何年となったでしょう?
2015年の改正で、同一の派遣労働者が同じ組織単位(課など)で働ける期間の上限は原則3年となりました。これにより、特定の人が長期間派遣のままで働き続けることを防ぐとともに、派遣先は3年ごとに人を入れ替えるか直接雇用へ切り替える努力が求められるようになりました。
Q10 : 派遣労働者が直接雇用に切り替わることを促進する法律はどれですか?
労働者派遣法は、派遣労働者の保護と適正な運用を目的として制定された法律です。2015年の改正により、派遣元・派遣先の責任が強化され、派遣先において無期雇用の機会提供(直接雇用への切替え)を促進する仕組みが設けられました。また、3年ルールなどにより、同一の派遣先での派遣期間が制限されています。
まとめ
いかがでしたか? 今回は派遣に関するクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は派遣に関するクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。