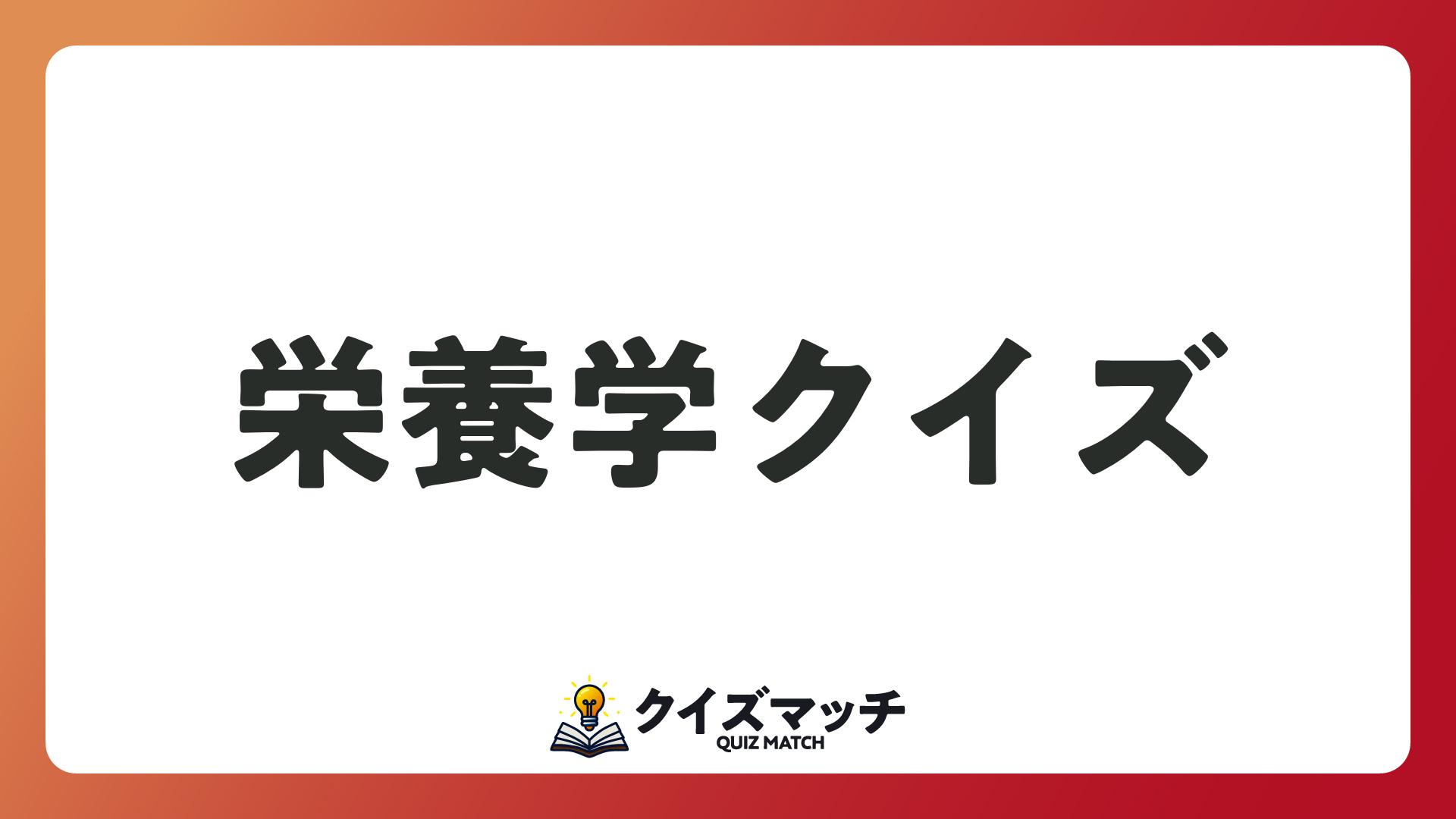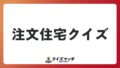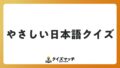エネルギーやたんぱく質、ビタミンなどの栄養素の働きを正しく理解することは、健康的な生活を送る上で大切です。この10問のクイズでは、野菜のビタミンC含有量や必須アミノ酸の数、脂溶性ビタミンの種類、鉄分の多い食品など、栄養学の基礎知識をチェックできます。食生活の改善につながる情報が満載ですので、ぜひ挑戦してみてください。
Q1 : ビタミンB1が不足すると生じやすい症状は?
ビタミンB1は糖質の代謝に不可欠な水溶性ビタミンで、不足すると脚気(かっけ)を起こします。脚気は倦怠感やむくみ、神経障害などを引き起こします。壊血病はビタミンC欠乏、貧血は鉄欠乏、骨粗鬆症はカルシウム・ビタミンD欠乏が原因となります。
Q2 : エネルギー産生栄養素のうち、1gあたりのエネルギー量がもっとも多いのは?
脂質は1gあたり9kcalのエネルギーを産生しますが、炭水化物とたんぱく質はそれぞれ4kcal、ビタミンはほぼ0kcalです。そのため、脂質の過剰摂取はエネルギー過多や肥満につながりやすいので注意が必要です。
Q3 : 体内のカルシウムの多くはどこに存在している?
カルシウムの約99%は骨や歯に存在し、体の構造を支え丈夫に保つ働きをします。残り1%は血液や筋肉などに存在し、神経伝達や筋収縮、血液凝固など生命維持の重要な役割を持ちます。カルシウム不足は骨粗しょう症などの原因となります。
Q4 : 水分補給が重要な理由として誤っているものはどれ?
水は体温調節や老廃物排泄、栄養素の吸収・運搬のほか多くの身体機能に関わりますが、エネルギー源にはなりません。水はカロリーを持たず、炭水化物・脂質・たんぱく質とは異なります。水分不足は脱水や熱中症、健康障害を引き起こすため補給は大切です。
Q5 : 食物繊維の働きとして正しくないものはどれ?
食物繊維は腸内環境を整えたり、コレステロールの排出を助けたり、食後の血糖値上昇を緩やかにする役割がありますが、ヒトでは消化吸収されずエネルギー源にはなりません。他の栄養素とは異なる生理作用を持ち、健康維持に欠かせない成分です。
Q6 : 鉄分が豊富に含まれている食品として正しいものは?
鉄分はほうれん草をはじめとする緑黄色野菜やレバー、赤身肉、貝類などに多く含まれています。牛乳やじゃがいも、コーンフレークにも含まれていますが、含有量はほうれん草や動物性食品に劣ります。鉄は赤血球の成分となり、貧血予防に重要です。
Q7 : 脂溶性ビタミンに該当しないものはどれ?
脂溶性ビタミンはA・D・E・Kの4種類で、油脂に溶けやすく体内に貯蔵されやすい特徴があります。一方で、ビタミンB1は水溶性ビタミンです。水溶性ビタミンは尿中に排泄されやすく、過剰摂取になりにくいですが、脂溶性ビタミンは過剰摂取に注意が必要です。
Q8 : エネルギー源の主要三大栄養素は、炭水化物、脂質とあとひとつは何でしょう?
炭水化物、脂質、タンパク質が三大栄養素(エネルギー産生栄養素)です。ビタミンやミネラルは身体の調子を整えるために必要ですが、主なエネルギー源にはなりません。タンパク質は筋肉や内臓など体の構成成分となるほか、一部はエネルギーにもなります。
Q9 : 「必須アミノ酸」は体内で合成できないアミノ酸ですが、その数はいくつでしょう?
必須アミノ酸は9種類存在し、体内で合成できないため食事から摂取する必要があります。ヒトにとっての必須アミノ酸はバリン、ロイシン、イソロイシン、リジン、メチオニン、フェニルアラニン、スレオニン(トレオニン)、トリプトファン、ヒスチジンです。子どもや成長期には追加で必要なものもあります。
Q10 : ビタミンCが特に多く含まれている野菜はどれ?
ビタミンCは野菜全般に含まれていますが、ブロッコリーには特に多く、加熱後も比較的残りやすい点が特徴です。トマトやキャベツにも含まれますが、含有量はブロッコリーに劣ります。ビタミンCは抗酸化作用を持ち、風邪予防や美肌効果が期待できます。
まとめ
いかがでしたか? 今回は栄養学クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は栄養学クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。