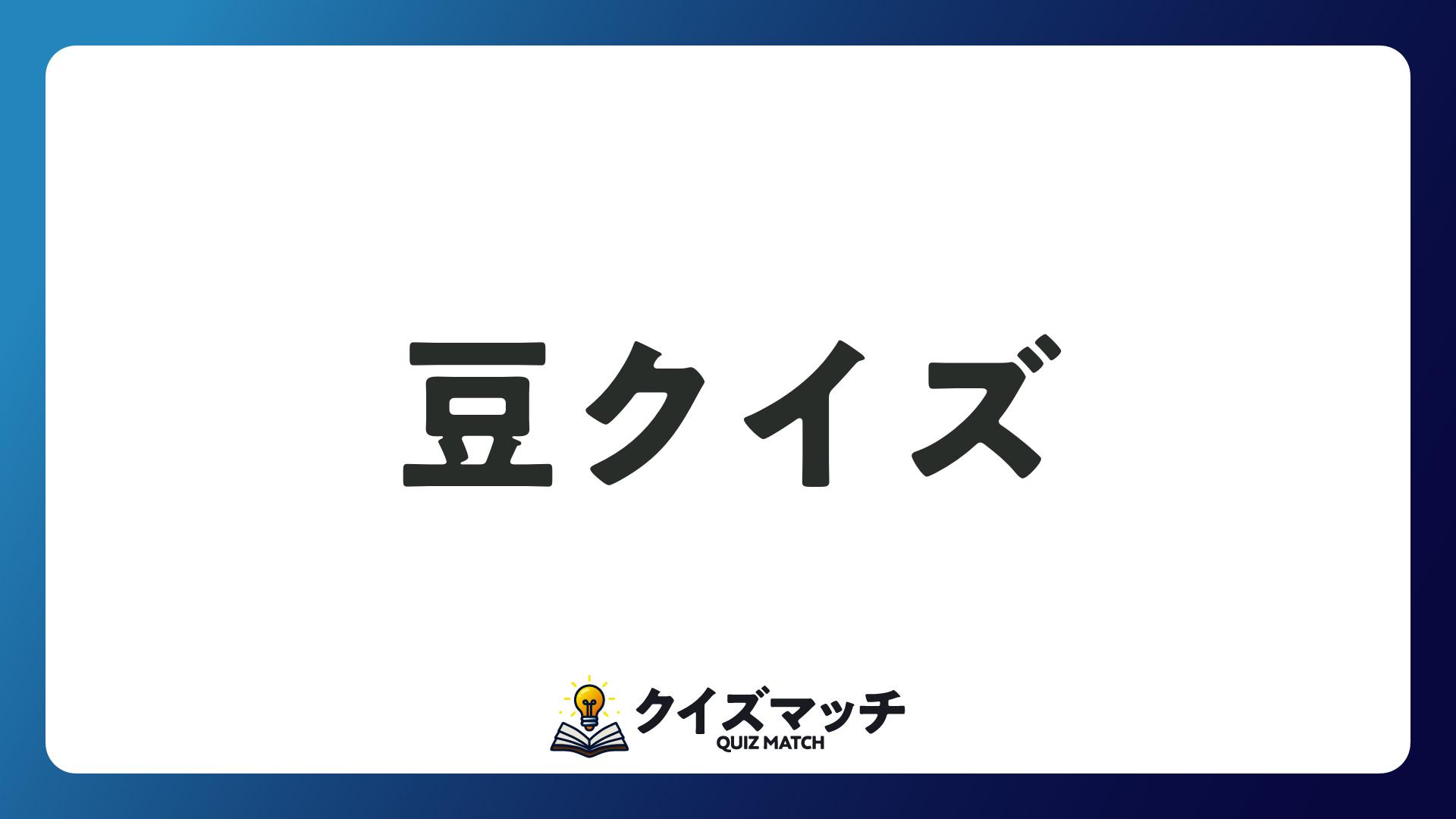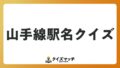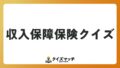節分の季節になると、日本人なら誰もが豆の話題に花を咲かせます。そこで今回は「豆クイズ」と題して、日本の食文化にまつわる豆の雑学を10問ご紹介します。大豆やそら豆、落花生など、日常的に口にしているあの豆について、意外な知識が満載です。豆の歴史、栄養、加工法など、豆に関するさまざまな側面を楽しく学べる内容となっております。豆好きの方はもちろん、豆について詳しくない方にも、きっと新たな発見があるはずです。さあ、豆の世界を存分にお楽しみください。
Q1 : 日本の豆菓子である「きなこ」の主な原材料は何?
きなこは炒った大豆を粉にしたもので、日本の伝統的な豆菓子や和菓子の材料です。たんぱく質やイソフラボンなど、栄養も豊富。小豆やピーナッツ、そら豆はきなこの原材料ではありません。
Q2 : 煎り大豆を用いた「福豆」が登場する日本の年中行事はどれ?
「福豆」とは節分の行事で使われる煎り大豆のことです。家の中や外に豆を撒き、「鬼は外、福は内」と唱えて邪気を払います。七夕やひな祭り、彼岸には福豆は使われません。
Q3 : グリーンピースとして食べられる豆は、どの豆の未熟な実ですか?
グリーンピースはエンドウ豆の未熟な実です。完熟したエンドウ豆は硬くなり、日本では乾燥エンドウとしても利用されます。小豆、そら豆、いんげん豆は別の種類の豆です。
Q4 : インゲン豆の由来となった名前の人物は誰でしょう?
インゲン豆の由来は、中国から日本にインゲン豆の種子を伝えたとされる明の僧・隠元隆琦(いんげんりゅうき)に因んでいます。江戸時代初期に日本に持ち込まれ、広まりました。他の人物は豆の由来に関係ありません。
Q5 : 納豆の発酵に使われる主な菌は?
納豆の発酵には主に「納豆菌」(正式名称:バチルス・サブチリス/Bacillus subtilis)が使われます。この菌によって大豆が発酵し、あの独特の風味と粘り気が生まれます。他の選択肢のビフィズス菌やラクトバチルス菌はヨーグルトなどに使われる菌です。
Q6 : 日本で「豆苗」と呼ばれている野菜はどの植物の若芽ですか?
豆苗(とうみょう)はエンドウ豆の若芽です。シャキシャキした食感と高い栄養価が特徴で、サラダや炒め物によく使われます。そら豆や小豆、黒豆の若芽は通常豆苗とは呼ばれていません。
Q7 : 「枝豆」として食べられる豆は、成熟すると何になりますか?
枝豆は未成熟の大豆を塩ゆでなどで食べるもので、完熟させると一般的な大豆となります。大豆はさまざまな加工食品、例えば味噌や醤油、納豆などにも使われています。小豆やピーナッツ、グリーンピースはそれぞれ異なる植物です。
Q8 : 豆腐の主な原材料は?
豆腐の主な原材料は「大豆」です。大豆を水に浸してすりつぶし、煮て凝固剤を加えることで豆腐が作られます。日本の食文化に欠かせない存在であり、古くからタンパク源として親しまれています。他の選択肢は豆腐の主要原料ではありません。
Q9 : 落花生が節分豆として用いられることが多い地域はどこですか?
落花生が節分豆として使われることが多いのは、主に北海道や東北地方です。寒冷な地域では大豆をまくと拾いきれない分が芽を出してしまう恐れがあるため、殻つきで衛生的な落花生が用いられました。他の地域では主に大豆が使われるのが一般的です。
Q10 : 日本の節分で撒かれる豆として最も一般的なものはどれですか?
節分で撒かれる豆として最も一般的なのは「大豆」です。理由は、悪霊を追い払うためには栄養価が高く、生命力を象徴する大豆が縁起が良いとされていることです。そら豆や黒豆はおせち料理などに多く使われ、枝豆(=若い大豆)は主に酒のつまみなどになるため節分にはあまり用いられません。
まとめ
いかがでしたか? 今回は豆クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は豆クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。