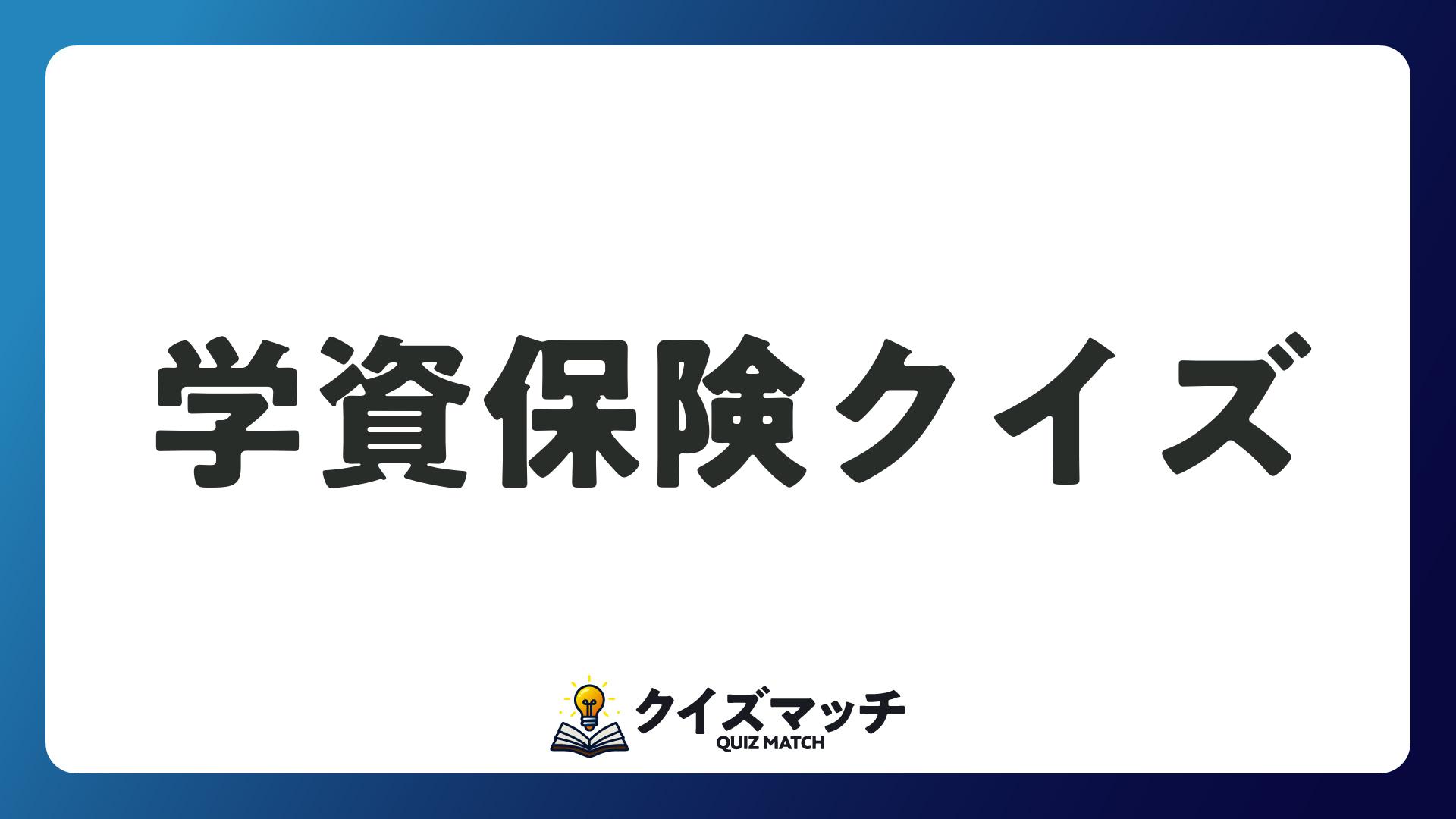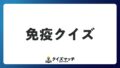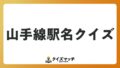学資保険は、子どもの教育費の準備に役立つ重要な保険商品です。これからの学生生活や進学といった大きな出費に備えるため、多くの親が学資保険に加入しています。この記事では、学資保険の特徴や仕組み、注意点などについてクイズ形式で学んでいきます。学資保険に関する基礎知識を確認し、子どもの未来のために最適な学資保険の活用方法を見つけていきましょう。
Q1 : 学資保険の祝い金(祝金)は、どのようなタイミングで受け取るのが一般的か?
学資保険の祝い金(祝金)は、主に小学校・中学校・高校・大学など、一定の年齢や進学時に合わせて受け取れるよう設定されています。多くのプランでは受け取りのタイミングがあらかじめ決まっており、希望時にいつでも受け取れるわけではありません。教育資金にタイムリーに使えるのが特徴です。
Q2 : 学資保険の保険金受取人として一般的に指定されるのは誰か?
学資保険の受取人は多くの場合、契約者(親や祖父母)自身が指定されます。その理由は、受け取った保険金を子どものために用途にあわせて管理するためです。税法上も契約者である親が保険金受取人となる組み合わせが一般的です。ただし契約内容によって受取人を子どもに設定することもできます。
Q3 : 学資保険の途中解約時に注意すべき点は?
学資保険は途中で解約すると、受け取れる解約返戻金が払い込んだ保険料の総額よりも少なくなる「元本割れ」が起こりやすい商品です。早期に解約するほど損失が大きくなりやすいため、計画的に続けていくことが重要です。解約返戻金は契約期間・種類によって異なります。
Q4 : 学資保険と「児童手当」との違いはどれか?
児童手当は国が支給する公的な給付金で、0歳から15歳の子ども(中学校卒業まで)を対象に定期的に支給されます。一方、学資保険は民間の保険会社が販売する商品で、契約や内容も自由に選択できます。このため、「保険は民間、児童手当は公的制度」という点が大きな違いです。
Q5 : 学資保険の保険料を安く抑える一般的な方法はどれか?
学資保険の保険料は加入時の子どもの年齢が若いほど安くなります。理由は、保険期間が長くなる分、リスクの平準化が図れるためです。子どもが生まれてすぐに入るのが最も低コストで済みやすいです。年齢が上がるごとに毎月の保険料や総払い込み額が高くなります。
Q6 : 学資保険の満期は一般的にいつに設定されていることが多いか?
学資保険の満期はお子さんが大学進学や高等学校卒業を迎える18歳に設定されていることが多いです。これにより、進学に必要となる大きな資金が一度に受け取れるようになっており、加入目的に合致しています。また一部の商品は17歳や22歳満期も選択できますが、メインは18歳です。
Q7 : 学資保険の保障内容として、一般的に含まれないものはどれか?
学資保険の主な保障内容は、契約者死亡時の払込免除、子どもの成長に合わせた祝い金(祝金)、満期保険金などです。「親(契約者)の入院給付金」は医療保険の内容であり、学資保険には通常含まれません。学資保険はあくまでも子どもの教育資金準備が目的です。
Q8 : 学資保険の主な目的はどれか?
学資保険は子供の成長とともに発生する進学準備金や入学時の費用、学費などの教育資金準備を主な目的として設計されています。満期時や定期時に祝い金等が支払われることで、計画的な資金準備が可能です。結婚資金や親の老後・医療資金目的の商品とは区別されます。
Q9 : 学資保険の返戻率(へんれいりつ)について、正しい説明はどれか?
返戻率とは、保険満期時や進学祝金として受け取れる総額が、これまで払い込んできた保険料総額の何パーセントに当たるかを表す指標です。例えば、返戻率が105%であれば、払込保険料100万円に対して満期等で105万円を受け取れることを意味します。国内の学資保険では100%前後から105%程度が主流です。
Q10 : 学資保険において、一般的に保険料の払込期間満了前に契約者が死亡した場合、残りの保険料についてどうなりますか?
学資保険では、契約者(主に親)が死亡した場合、以後の保険料の払い込みが免除され、契約は継続し、子供が進学時に満期保険金(進学祝金など)を受け取れる仕組みが一般的です。これにより、遺された家族の負担を軽減し、教育資金の確保ができます。保険のプランによって詳細は異なる場合もありますが、「払込免除特約」が多くの学資保険に付いています。
まとめ
いかがでしたか? 今回は学資保険クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は学資保険クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。