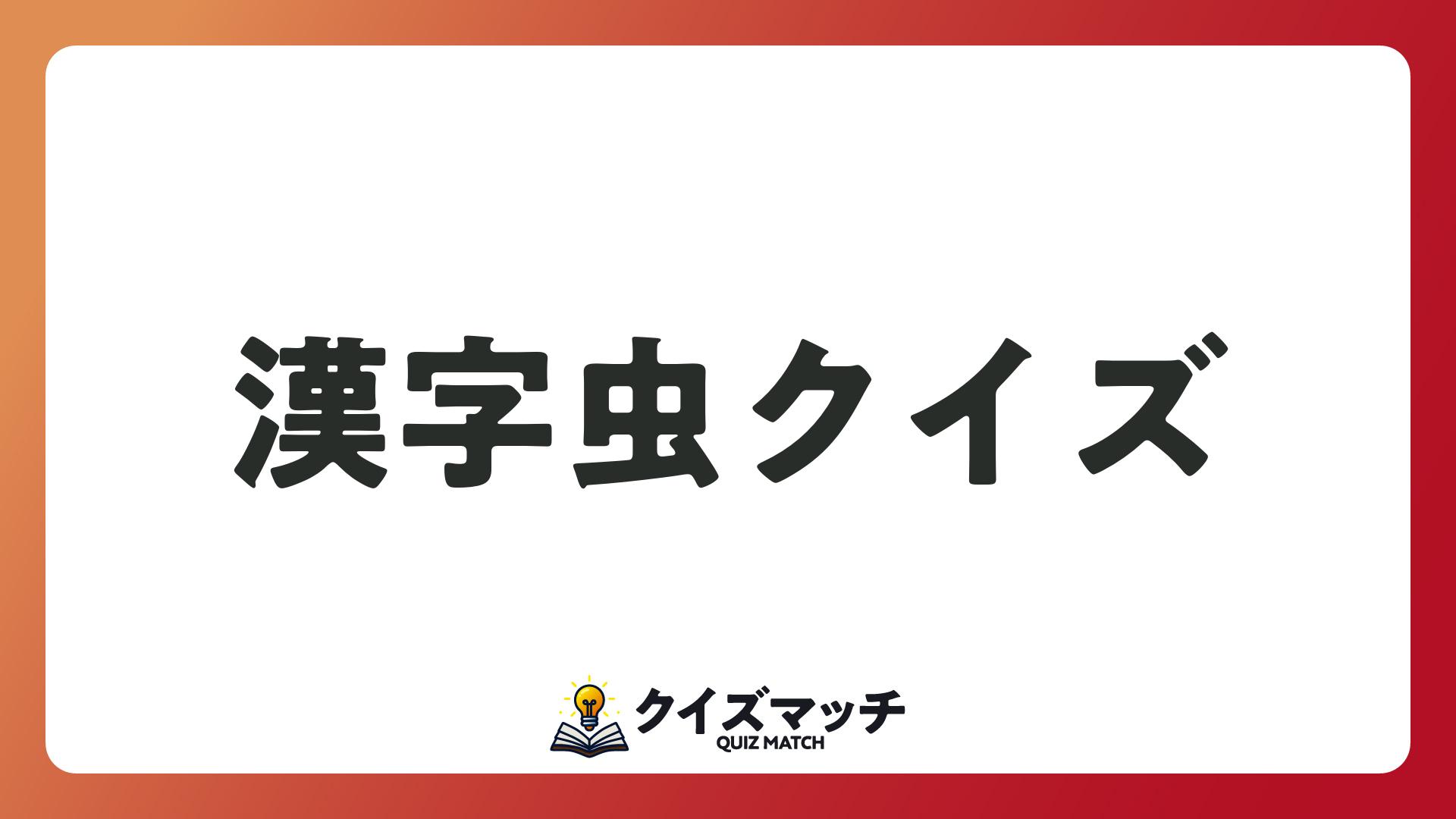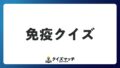虫と漢字の不思議な関係を探る!「漢字虫クイズ」がやってきました。漢字の中には、虫の形や特徴が隠れているものがたくさんあります。「蜂」の構造から虫編の位置を探ったり、「蝉」の音読みを当てるなど、漢字に込められた虫の世界をクイズ形式で紐解いていきます。きっと、日本語の奥深さに驚かされること間違いなし。漢字好きはもちろん、虫好きにもおすすめの10問をご用意しました。虫の漢字探偵、あなたの出番です!
Q1 : 「蝗」という漢字が表す虫は?
「蝗(こう、いなご)」という漢字は、イナゴやバッタなどの飛ぶ昆虫を指します。蝗害(バッタによる作物被害)などの言葉にも使われます。「カブトムシ」は「兜虫」、「カマキリ」は「蟷螂」、「チョウ」は「蝶」を使います。直感的に虫へん+「皇」と組み合わさっていることからもバッタ類を意味することが分かります。
Q2 : 「蜂」に含まれる虫編の位置はどこ?
「蜂」は左側に虫編、その右に「方」がついて出来ています。漢字構成の中で「〜へん」と呼ばれる部首の多くは、左側に配置されます。たとえば「蝉」「蛍」「蝿」なども左側に虫編があります。それぞれ虫を意味する記号的役割を果たし、本体の漢字の意味性や発音を補助する働きも担います。
Q3 : 「蜻蛉」の意味として正しいものは?
「蜻蛉(せいれい)」は、訓読みで「とんぼ」と読みます。長い胴体と大きな羽を持つことから、古くから日本でも親しまれてきた昆虫です。「ほたる(蛍)」、「せみ(蝉)」、「が(蛾)」はいずれも別の漢字を持っています。複数の虫の名前を漢字で書けると、文学作品などでの表現の幅も広がります。
Q4 : 「蛾」という漢字の意味するものは?
「蛾」は「が」と読みます。ガは夜行性の昆虫で、蝶とは翅や休み方、活動時間などが異なります。「ちょう(蝶)」は別の漢字、「はえ(蝿)」や「くも(蜘蛛)」も別の漢字で表されます。虫へんに我を組み合わせた「蛾」は、漢字からも特徴が分かりやすいので間違えないようにしましょう。
Q5 : 「蚊」の訓読みは?
「蚊」は訓読みで「か」と読み、小さく人を刺す虫として有名です。虫へんに、文(ぶん)の下に点を書きます。「くも」は「蜘蛛」、「あり」は「蟻」、「せみ」は「蝉」と表記します。いずれも虫へんの仲間ですが、日常的に目にする虫の名前の漢字を覚えておくと、ほかの選択肢と間違いにくくなります。
Q6 : 「蝶」の読みとして正しいものはどれ?
「蝶」は音読みで「チョウ」と読みます。訓読みはありません。「とんぼ」は「蜻蛉(せいれい)」、「が」は「蛾(ガ)」です。「かぶとむし」は「甲虫」や「兜虫」とも書きますが、「蝶」ではありません。蝶は美しい翅を持つ昆虫であり、漢字からも見分けやすい代表的な虫です。
Q7 : 「蛍」の訓読みは?
「蛍」は訓読みで「ほたる」と読み、夏の夜に光ることで有名な昆虫です。虫へんに「火」と似た部分を持つ「蛍」は、その明かりをイメージさせます。「こおろぎ」は「蟋蟀」、「せみ」は「蝉」、「はえ」は「蝿」などで表します。他の選択肢の漢字と混同しないように注意が必要です。
Q8 : 「蟻」の訓読みは?
「蟻」は訓読みで「あり」と読みます。これは社会性昆虫として知られるアリを表す漢字です。「みみず」は「蚯蚓(きゅういん)」と書きます。「かまきり」は「蟷螂(とうろう)」などで表され、ごきぶりは「蜚蠊(ひれん)」が正式な漢字です。虫へんに「義」と書きますが、意味や読みからも「あり」であることが分かります。
Q9 : 「蝉」という漢字の音読みはどれ?
「蝉(せみ)」の音読みは「セン」です。訓読みは「せみ」といい、夏に鳴く昆虫として知られています。他の選択肢の「チョウ」は「蝶」や「丁」、「ハチ」は「蜂」、「カナブン」はカナブンを表す固有名ですが、「蝉」の音読みとしては使われません。日本語の漢字では音読みと訓読みがありますが、虫の漢字は和名と中国由来で使い分けられることが多いです。
Q10 : 「蜂」という漢字に含まれる虫編以外の部首はどれですか?
「蜂」という漢字は、虫編(むしへん)と「方(かた)」の組み合わせでできています。虫編は昆虫や虫に関係する漢字によく使われ、「蜂」は昆虫であるハチを表します。虫編の横に「方」の形が付いているのが特徴です。他の選択肢の「風」は「鳳」や「風」、「立」は「站」や「竜」、「田」は「畑」などに使われますが、この場合「方」が正解です。
まとめ
いかがでしたか? 今回は漢字虫クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は漢字虫クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。