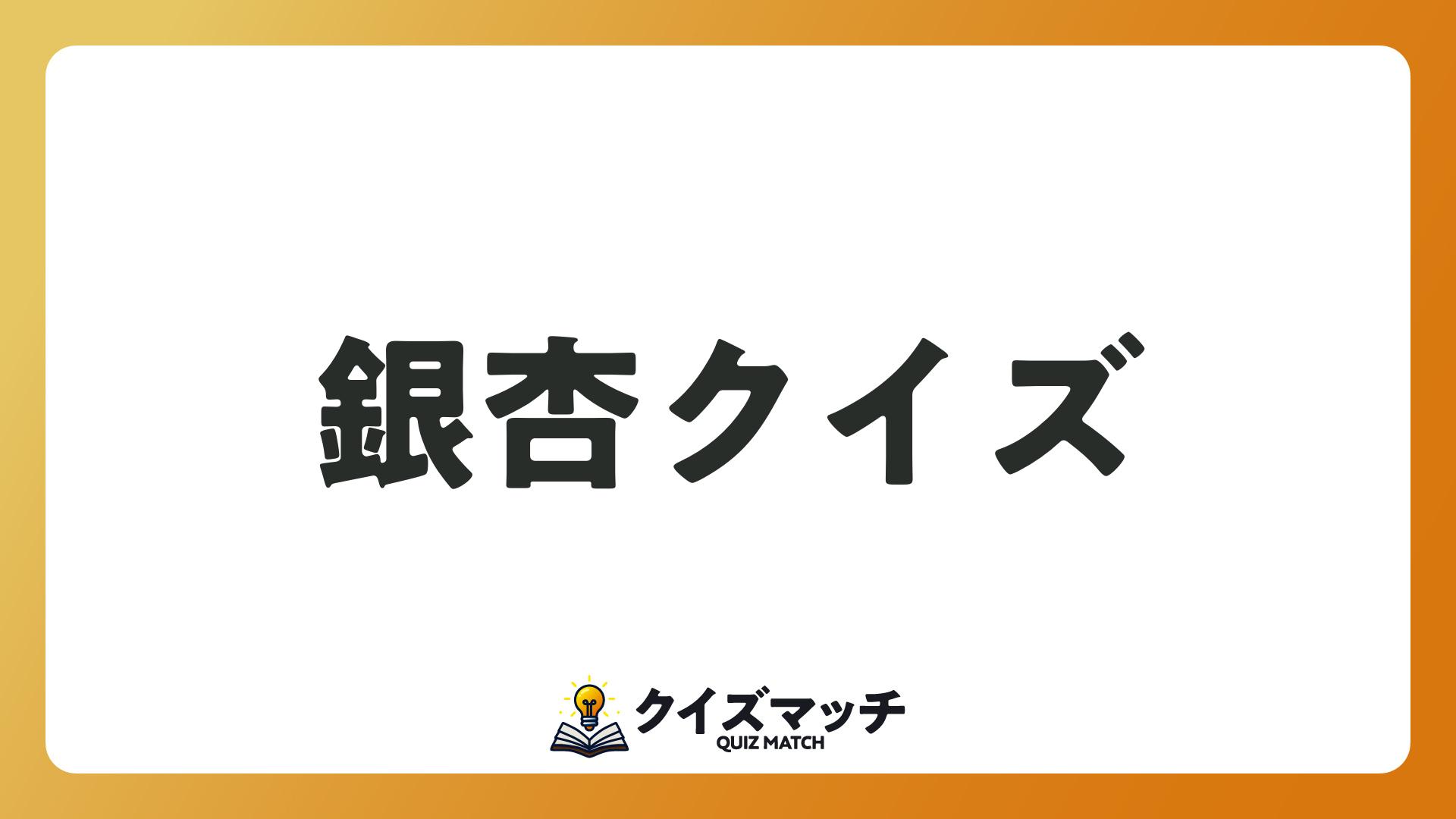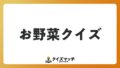銀杏は、その独特の扇形の葉と美しい黄葉が知られる、古代から変わらぬ姿を残す希少な樹木です。この記事では、銀杏の学名やその特徴、利用方法といった基本的な知識から、食べ過ぎの注意点まで、銀杏に関する10の興味深いクイズに挑戦していただきます。銀杏を身近に感じていただき、この”生きた化石”に対する理解を深めていただければと思います。
Q1 : イチョウが生きた化石と呼ばれる理由は何ですか?
イチョウは約2億年以上前からほぼ変わらない姿で生きており、恐竜時代から地球上に存在していた稀有な樹木です。このため、「生きた化石」と呼ばれます。現在野生種は中国の一部にしか存在せず、ほとんどは植栽ですが、原始的な特徴を今も色濃く残しているためこのように言われています。
Q2 : 銀杏の食べすぎに注意するべき主な理由は何ですか?
銀杏を食べすぎると、特有の有毒成分が神経に影響して中毒症を起こすことがあるため、食べすぎに注意が必要です。子どもは特に危険で、10粒ほどでも症状が出る場合があります。ほかの理由(消化不良やアレルギー)は可能性がありますが、最も重大なのは中毒症です。
Q3 : イチョウの葉の形の特徴はどれですか?
イチョウの葉は扇状に広がる独特の形をしています。これは、世界的にも希少な形状で、現存する樹木の中では他に見られません。ギザギザや針状の葉は他の樹木に見られるものです。扇型の葉は古代から「生きた化石」とも呼ばれるイチョウの大きな特徴です。
Q4 : 銀杏の実を焼く際に、爆発しにくくするための下処理は?
銀杏の実は加熱すると内部の水分が膨張し爆発することがあります。これを防止するために、殻に小さな穴をあけておくことで蒸気の逃げ道ができ、爆発を防ぐことができます。水に漬けたり塩を振っても爆発防止の効果はありません。また砂をまぶして加熱する調理法もありますが、爆発防止としては穴開けが有効です。
Q5 : 銀杏の殻を割るのによく使われる道具は何ですか?
銀杏の固い殻を割るにはペンチを使うのが一般的です。家庭用の手軽な方法として、台所用のペンチがよく使われます。他にもナッツクラッカーも使われますが、ピンポイントで挟みやすいペンチが最も一般的です。ハンマーやトンカチでは割れすぎたり中身が潰れる恐れがあります。
Q6 : 日本で街路樹として最も多く植えられている樹木は何でしょう?
日本の都市部で街路樹として最も多く植えられているのはイチョウです。病害虫に強く、成長も早いため各地で見られます。桜やケヤキもよく植えられていますが、総数で見るとイチョウが一番多いとされています。スギは主に山林や植林地に多い樹木です。
Q7 : イチョウの葉が黄色くなる現象を何と呼ぶでしょう?
イチョウの葉が秋になると黄色くなる現象は「黄葉(こうよう)」と呼ばれます。「紅葉」はカエデなど葉が赤くなることを指し、「落葉」は葉が落ちる現象そのものを指します。「褐葉」は茶色く枯れることですが、イチョウ特有の鮮やかな黄色は「黄葉」といわれます。
Q8 : 銀杏の実に含まれる成分で、食べすぎると中毒の危険があるものはどれですか?
銀杏の実にはビタミンB1の働きを妨げるメチルビタミンB1拮抗物質が含まれており、これを過剰に摂取すると中毒を起こすことがあります。特に子供の場合は、5~6粒でも中毒症状が出ることがあります。中毒症状にはけいれんや意識障害が見られることがありますので注意が必要です。他の選択肢は誤りです。
Q9 : イチョウの木が多く街路樹に利用される理由はどれですか?
イチョウは公害や病害虫に非常に強く、都市部の大気汚染にも耐性があります。このため、街路樹として多く利用されています。また、葉の形や紅葉の美しさも理由の一つですが、最も大きな理由はその頑強さにあります。実は食用ですが、街路樹に果実を目的に植えることは主な理由ではありません。
Q10 : 銀杏の学名はどれですか?
銀杏(ギンナン)は、イチョウの実であり、イチョウ科イチョウ属の植物です。学名はGinkgo bilobaです。ビロバは「2つの葉」という意味で、イチョウの葉の特徴である切れ込みが深いことに由来します。他の選択肢は、ブナ(Fagus crenata)、コナラ(Quercus serrata)、イロハモミジ(Acer palmatum)で、どれもイチョウとは異なります。
まとめ
いかがでしたか? 今回は銀杏クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は銀杏クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。