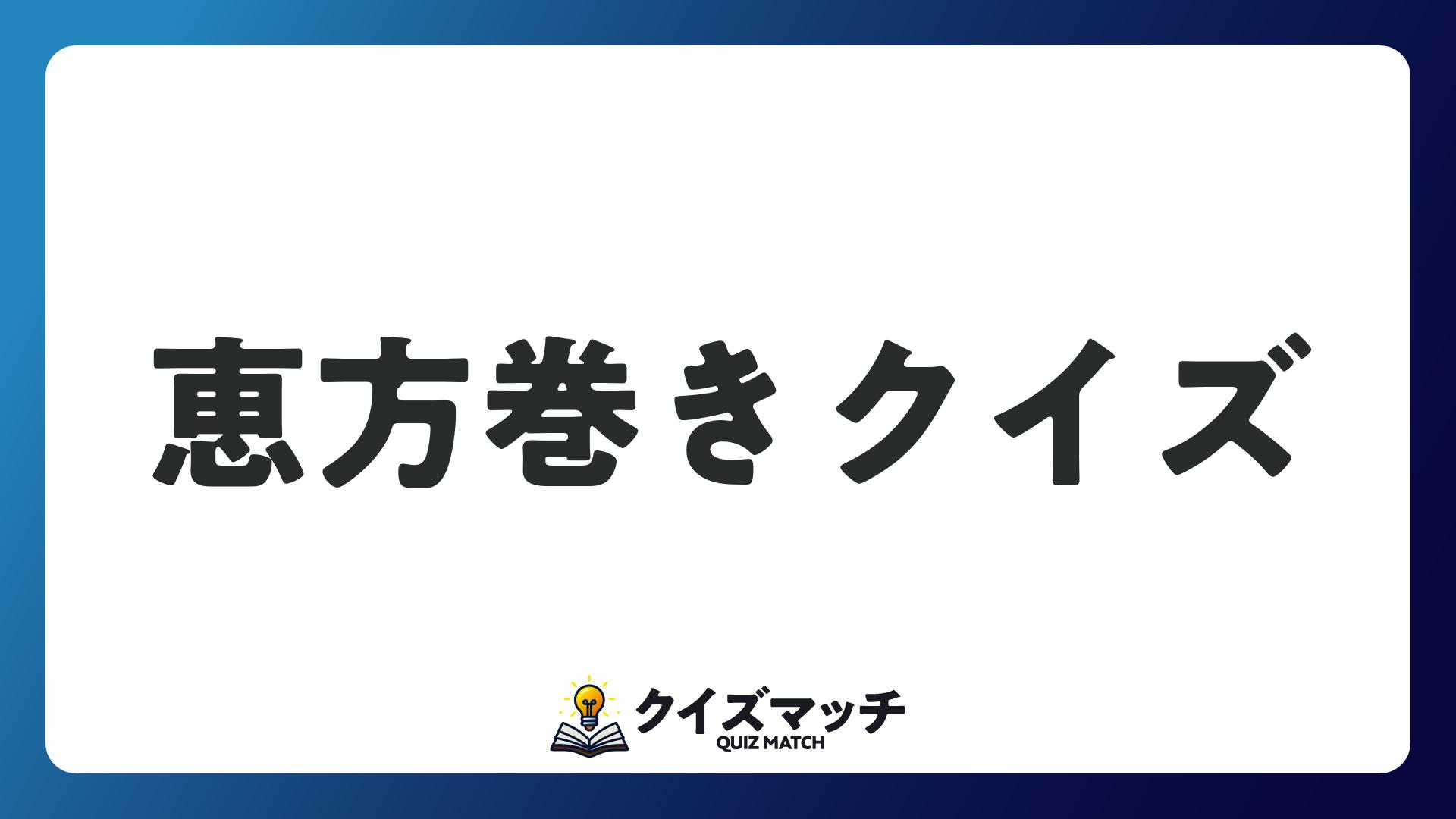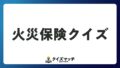節分の時期になると、あちらこちらで「恵方巻き」の販売が行われます。この恵方巻きには、実は深い歴史と縁起の良い習わしが隠れています。そこで今回は、恵方巻きに関する楽しい10問のクイズをご用意しました。恵方巻きの起源や食べ方、呼び名の変遷など、意外な事実が満載です。節分を前に、恵方巻きについて楽しく学んでみましょう。
Q1 : 恵方巻きの全国的な普及のきっかけとなったのは何でしょう?
恵方巻きが全国に広まったのは、1990年代にコンビニチェーンが販売戦略として商標登録や宣伝を行い大々的に売り出したことがきっかけです。それ以前は関西が中心の行事でした。テレビやSNSの影響もありますが決め手はコンビニです。
Q2 : 2024年の恵方はどの方角でしたか?
2024年の恵方は『東北東』でした。恵方は年ごとに決められていて、『東北東』『南南東』『西南西』『北北西』の4方向のいずれかです。節分の時期にその年の恵方を調べ、向いて食べるのが習わしです。
Q3 : 恵方巻きを食べる理由として最も一般的に言われているものは何?
恵方巻きは元々、商人たちが『商売繁盛』を祈願して食べていたと言われています。健康や恋愛成就、学業成就なども悪くありませんが、特に大阪の商人文化が由来とされているため、商売繁盛に結びついています。
Q4 : 恵方巻きに関する正しい情報はどれ?
恵方巻きを食べるときは、願い事を心の中で祈りながら無言で食べるのが縁起が良いとされています。話したり切ったりすると福が逃げると考えられています。切らずに無言で食べきることがポイントです。
Q5 : 恵方巻きの呼び名として、かつて使われていた名称はどれ?
『恵方巻き』という呼び名は比較的新しく、かつては『丸かぶり寿司』や『太巻き寿司』などと呼ばれていました。『恵方巻き』は1990年代にコンビニなどの販売戦略で広まった名称です。
Q6 : 恵方巻きの起源はどの地域とされていますか?
恵方巻きの起源は主に大阪を中心とした関西圏とされています。江戸時代末期から明治時代にかけて商人の間で商売繁盛を祈願して広まったと言われています。全国に広まったのはコンビニなどの販促活動のおかげです。
Q7 : 恵方巻きを食べるときに守るとよいとされる作法はどれ?
恵方巻きは、福が途切れないように『切らずに1本丸ごと』食べるのが縁起が良いとされています。家族で分けたり、途中で切って食べるのは、福が切れることを意味すると考えられています。
Q8 : 恵方巻きはその年の「恵方」を向いて食べるものですが、この「恵方」を決める基準は何でしょう?
毎年変わる『恵方』は、その年の福徳を司る『歳徳神(としとくじん)』がいるとされる方角です。方角は干支により定められていて、毎年変動します。二十四節気や太陽の方角は関係ありません。
Q9 : 恵方巻きの具として、伝統的に使われる食材はいくつあるとされることが多い?
恵方巻きの具材は、縁起が良いとされている七福神にちなんで7種類使われることが多いです。必ず7つとは決まっていませんが、定番として七福神にあやかり、『海老』『かんぴょう』『しいたけ煮』『きゅうり』『伊達巻(玉子焼き)』『うなぎ』『桜でんぶ』などがあります。
Q10 : 恵方巻きを食べる行事はどの節句と深い関わりがありますか?
恵方巻きは、節分の日に食べる風習と深く関係しています。節分は季節の変わり目にあたり、旧暦の大晦日ともされています。この日に福を呼び込むため、恵方を向いて恵方巻きを食べると縁起が良いとされています。ひな祭りや七夕、敬老の日は恵方巻きの風習とは関係ありません。
まとめ
いかがでしたか? 今回は恵方巻きクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は恵方巻きクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。