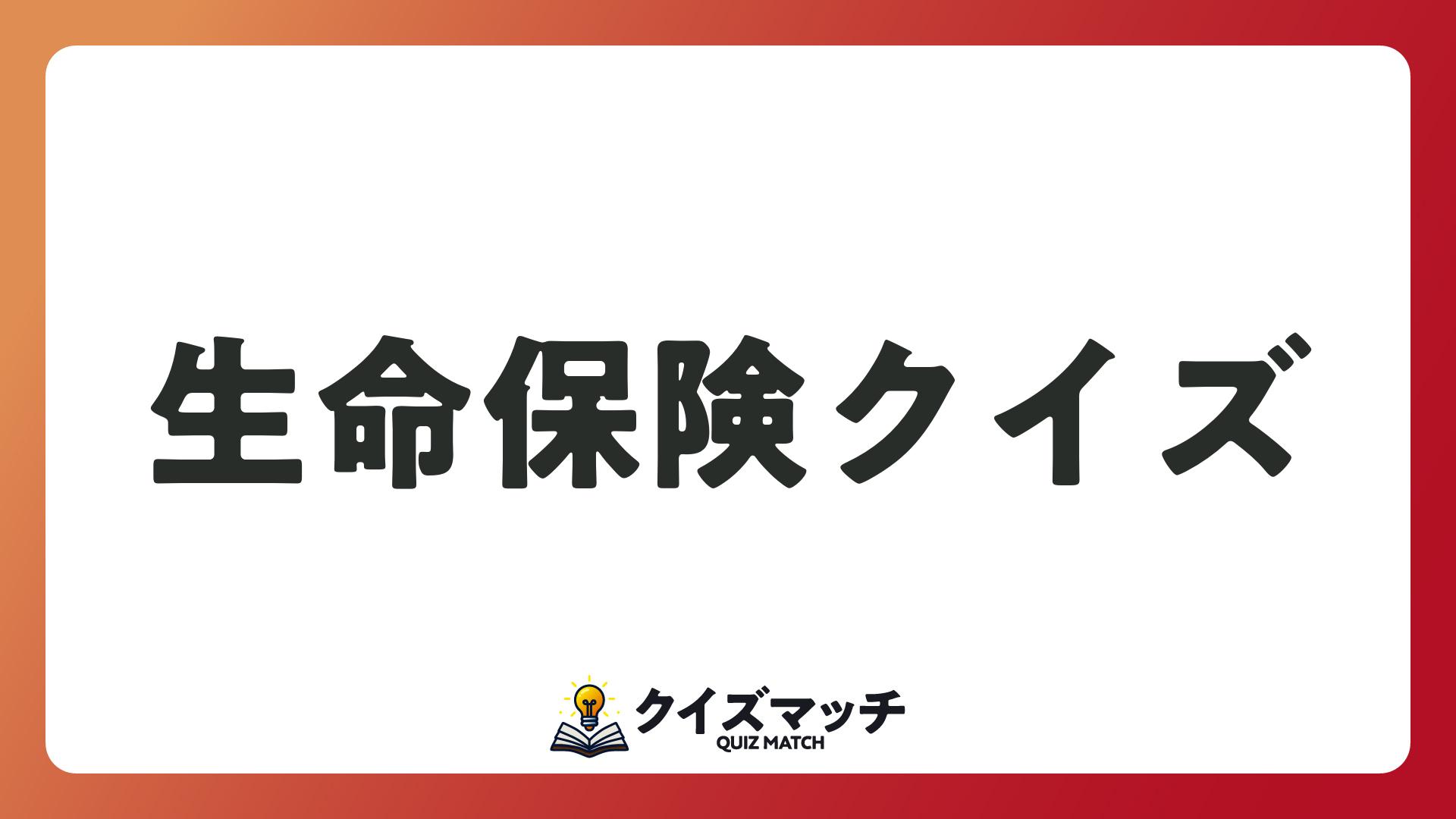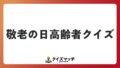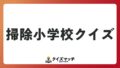生命保険は、私たちの大切な人や財産を守るための不可欠な備えです。この記事では、生命保険に関する基本的な知識を問うクイズを10問紹介します。終身保険の特徴や保険金の支払い条件、解約時の返戻金など、保険の重要ポイントを確認できます。また、相続税対策や保険外交員の資格要件など、生命保険の活用方法も学べます。保険の基礎知識を深めながら、自身にとって最適な保険選択ができるよう、ぜひこのクイズに挑戦してみてください。
Q1 : 保険外交員(ライフプランナー)が持つ資格として正しいのはどれですか?
生命保険を販売するためには、「生命保険募集人資格」が必要です。これは、生命保険会社が定める教育・試験に合格し、所定の手続きを経て得られます。宅地建物取引士や弁護士、旅行業務取扱管理者などの資格は、生命保険募集には直接必要ありません。
Q2 : 相続税対策で生命保険が活用される理由として正しいものはどれですか?
生命保険金は原則として受取人固有の財産とみなされるため、相続人同士のトラブル防止や現金を確実に遺す手段として活用されます。また、「500万円×法定相続人の数」まで非課税枠があるため、相続税対策として多く利用されています。
Q3 : 変額保険の特徴として正しいものはどれですか?
変額保険は、保険料の一部を投資信託等で運用し、その運用実績によって解約返戻金や死亡保険金の額が変動する商品です。したがって元本保証はなく、増えることも減ることもあります。特約付きや保険料変動型もあり、リスクを理解した上で利用されます。
Q4 : 生命保険の『告知義務違反』に該当するのはどれですか?
生命保険申込時には健康状態や既往症について正確な申告(告知義務)が求められます。持病や症状を隠して申し込んだ場合、後から発覚すれば契約が無効になったり、保険金が支払われなくなる恐れがあります。これは公平性とリスク評価の観点から重要なルールです。
Q5 : 保険金が支払われる『高度障害』の基準として正しいのはどれですか?
高度障害保険金の支払い対象となる『高度障害』は、両眼の失明や両手足の喪失など、日常生活を独力で送ることが著しく困難な重度障害状態を示しています。ただのケガや通院、年齢だけでは該当しません。具体的な基準は各社の約款に詳細に規定されています。
Q6 : 保険金の受取人として指定できないのは誰ですか?
生命保険の受取人は一般的に契約者本人やその家族(配偶者・子どもなど)に限定されます。原則として、法的に利害関係(保険利益)が認められる関係でなくてはなりません。特別な事情がない限り、赤の他人や社員・友人など第三者を任意で指定することはできません。
Q7 : 保険を解約したときに受け取れる可能性があるのはどれですか?
保険契約を途中で解約した際には、契約内容によって、解約返戻金が支払われる場合があります。これは、契約期間中に積み立てられた一部の資金が返却されるものです。すべての保険に解約返戻金があるわけではなく、掛け捨て型の定期保険などでは返戻金がない場合もあります。
Q8 : 医療保険の入院給付金が支払われる条件として正しいのはどれですか?
医療保険の入院給付金は、多くの場合、入院日数が一定数(たとえば1日以上など)を超えた場合に支払われます。また、契約内容によって給付金の支給条件が異なるため、事前に契約約款や担当者への確認が必要です。自宅療養は入院に該当しないため、通常は給付対象ではありません。
Q9 : 生命保険会社が支払わない場合の代表的な例はどれですか?
多くの生命保険約款では、戦争やその他の紛争行為に起因する死亡については、保険金支払いの対象として除外(免責)されています。これは予測できない大規模損失のリスクを回避するためです。病気や事故、老衰など通常の死亡原因は保険の対象ですが、戦争や自殺(一定期間内)は対象外となる場合があります。
Q10 : 終身保険に該当する特徴はどれですか?
終身保険は、保険料を支払い続ける限り、一生涯にわたり死亡保障が続く保険です。途中で解約しなければ保障は一生続き、解約返戻金や満期保険金を受け取れることも特徴です。一方、定期保険は一定期間のみ保障され、掛け捨て型の商品が多いです。終身保険は長期的な資金準備や相続対策にもよく用いられます。
まとめ
いかがでしたか? 今回は生命保険クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は生命保険クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。