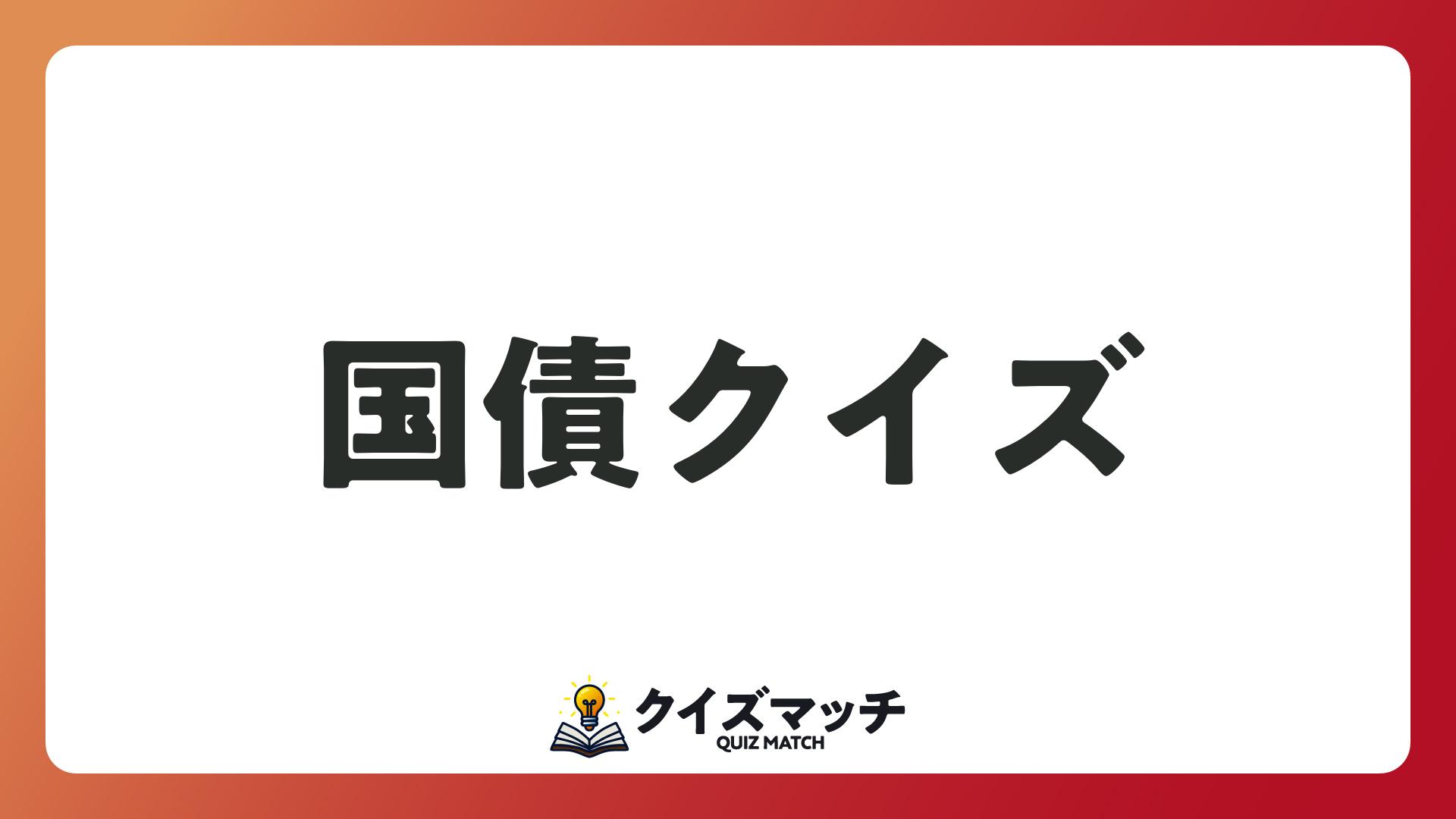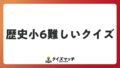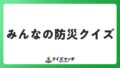日本国債は、国の財政健全化の根幹を成す重要な財政ツールです。本記事では、国債の基礎知識から最新の動向まで、10問のクイズを通してわかりやすく解説していきます。国債の発行主体や購入主体、利払い財源、格付けの影響など、国債に関する基本的な知識から、直近の発行残高や信用リスクといった経済的影響まで、幅広いトピックをカバーしています。国債に関心のある方やファイナンス初心者の方など、さまざまなニーズにお応えする内容となっております。
Q1 : 日本国債の発行残高(GDP比)は約どの程度か(2024年時点)?
2024年時点での日本国債の発行残高(普通国債)はGDP比で200%を大きく超え、約250%程度となっています。これは主要先進国のなかで最も高い水準で、財政持続性への懸念が指摘されています。国際比較でも突出した数値です。
Q2 : 国債の元利払いが保証されているのはなぜか?
国債の元利払い(元本・利息の支払い)は日本国債法等で法的に義務付けられており、予算編成においても優先されます。これにより、政府は財政的に厳しい状況でも元利払いを最優先して行う責任が生じています。
Q3 : 日本国債における「新発債」とは何か?
「新発債」とは、その年度の歳出に充てるために新しく発行される国債を指します。国の新たな借金です。一方、過去発行分の償還資金を賄うためのものは「借換債」、既存債は「既発債」といいます。
Q4 : 日本国債の信用リスクが顕在化した場合、政府が最初にとるべき対応は?
国債の信用リスクが顕在化した場合、政府はデフォルトを回避し、市場の信認を保つために財政再建策(歳出削減や増税等)を提示・実施することが必要です。そうすることで投資家の信頼喪失を食い止めます。
Q5 : 債券の格付けが引き下げられると国債の金利は通常どうなるか?
信用格付けが低下(格下げ)すると、その国債に対する信用リスクが高まるため、投資家が要求する利回り(=金利)は上昇する傾向があります。需要が減り価格が下がることで、結果的に金利が上がります。
Q6 : 市場で取引されない国債は次のうちどれ?
市中消化国債とは市場参加者による入札を経て発行され、市場で流通する形式の国債です。これに対し、財政融資資金特別会計などへの政府内部消化の国債は市場で取引されません。主な国債は市場で取引(流通)されますが、「市中消化国債」そのものは「市場で取引されない国債」を指す用語ではありません。選択肢のなかで「市場で取引されない国債」という表現が最も当てはまるものはこの選択肢です。
Q7 : 国債の利払いコストや元本償還の財源になるのはどれか?
国債の利払いおよび元本償還は主に税収によって賄われます。税収が不足する場合には新たな国債発行で賄われることもありますが、原則として国債の返済等は将来世代に税負担を転嫁することになります。
Q8 : 10年物日本国債の呼称として正しいものは?
日本国債では、10年物の利付国債を「長期国債」と呼称します。短期国債は1年未満、中期国債は2年・5年、長期国債は10年、20年・30年・40年は「超長期国債」と分類されます。
Q9 : 日本国債の主たる購入主体はどこですか?
日本国債の最大の購入主体は銀行等の金融機関です。特に都市銀行や地方銀行、信用金庫などが多く保有しています。次いで保険会社、生損保も大きな保有者です。個人投資家や外国政府は国債保有全体に占める割合は小さいです。
Q10 : 日本国債の発行主体はどこですか?
日本国債の発行主体は財務省(国)です。国の財政資金調達手段として発行され、一般会計や特別会計の財源に充てられます。日本銀行は発行後の売買や、市場安定を目的とした買い入れオペレーションを行いますが、発行の主体ではありません。経済産業省や総務省も国債の発行には関与しません。
まとめ
いかがでしたか? 今回は国債クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は国債クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。