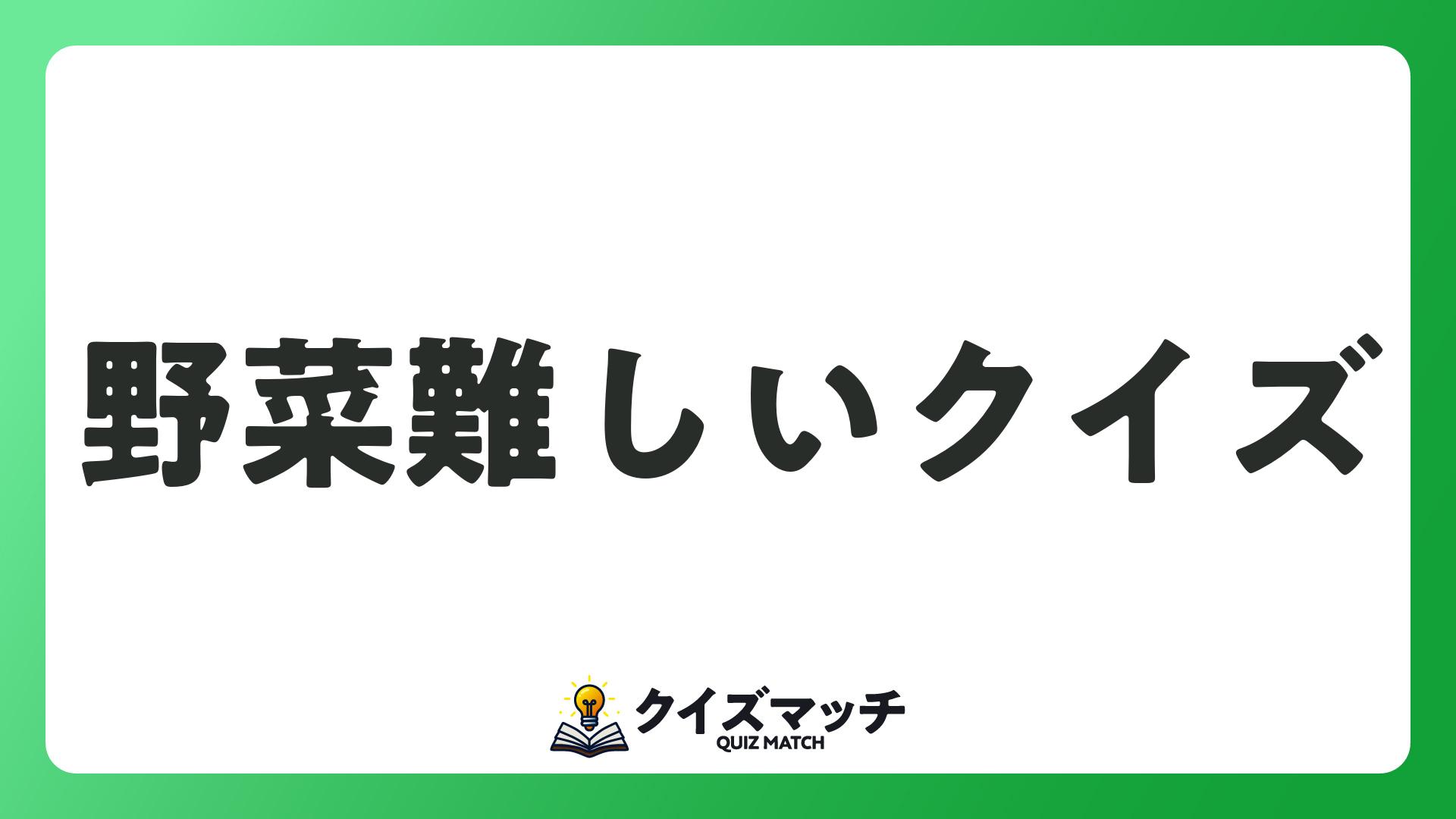野菜を題材にしたクイズに挑戦してみましょう。見た目や成分、歴史など、野菜にはたくさんの不思議な事実が隠されています。食べ慣れた野菜の新しい一面を発見できるかもしれません。出題されるクイズは見た目や栄養、産地といった知識が問われるものばかり。野菜通でなくても楽しめるはずです。野菜に詳しくなって、料理の幅も広がるかもしれませんよ。いつもの食べ物にも注目してみましょう。
Q1 : 『空心菜』という別名を持つ野菜はどれ?
空心菜は正式にはエンサイ(ヨウサイ)と呼ばれるヒルガオ科の野菜です。その茎は空洞になっており、炒め物などで用いられることが多いです。熱帯アジアを中心に栽培され、日本でも夏季に出回ることが増えてきました。ターサイやミズナはそれぞれ別の品種です。
Q2 : 『春の七草』のうち、冬でもよく食べられる葉物野菜はどれ?
春の七草は日本の伝統的な行事で食べられる7種類の野菜のことですが、この中でナズナ(ぺんぺん草)は冬でも野原などに生えており食用として利用できます。クセが少なくおひたしや和え物などに使われることが多いです。他は春先になると目に付く植物です。
Q3 : 日本原産の野菜は次のうちどれ?
シソ(大葉)は、日本に古くから自生していた植物であり、日本原産とされています。ピーマンやキャベツ、ニンジンは外国から伝来したものであり、日本古来の野菜ではありません。シソは独特の香りがあり、刺身のつまとしてだけでなく、薬味や天ぷらなど幅広く利用されています。
Q4 : 白菜がよく栽培されるのはどの季節か?
白菜は冷涼な気候を好み、主に秋から冬にかけて栽培・収穫されます。特に冬場は鍋料理の定番として広く知られています。春や夏は高温によって病気が発生しやすかったり、品質が落ちやすいですが、冬場になると肉厚で甘みのある白菜が収穫可能です。冬の代表的な野菜とされています。
Q5 : さつまいもの表皮の色はどの成分によるものか?
さつまいもの表皮が赤紫色をしているのは、アントシアニンが含まれているからです。アントシアニンはポリフェノールの一種で、抗酸化作用が期待できます。食品中では、ブルーベリーや黒米にもこの成分が多く含まれます。アントシアニンは水に溶けやすいため、調理の際に色が抜けることもあります。
Q6 : 紫外線対策・美白効果が期待される成分『β-カロテン』が特に多い野菜はどれ?
β-カロテンは、植物の色素成分の一つで、抗酸化作用があり、特に紫外線から肌を守る働きや美白効果が期待されています。ニンジンは100gあたり約8000μgものβ-カロテンを含んでおり、緑黄色野菜の代表格です。また、β-カロテンは脂溶性なので、油と一緒に調理すると吸収率が向上します。
Q7 : 『野菜の王様』とも呼ばれるほど栄養価が高い野菜は?
ほうれん草は『野菜の王様』と称されるほどビタミンやミネラル、鉄分などが豊富な緑黄色野菜です。特に鉄分が多いことで有名で、貧血予防や健康維持に役立ちます。さらに葉酸も多く、妊婦さんにもおすすめの野菜です。加熱してもビタミンの損失が比較的少ないのも特徴です。
Q8 : 和名を『牛蒡』とする野菜はどれ?
牛蒡(ごぼう)は日本や中国など東アジアで古くから食用されている根菜です。漢字で「牛蒡」と書きますが、サツマイモやレンコンとは全く異なる根の形や風味を持っています。日本では、きんぴらごぼうや炊き込みご飯などで使われており、食物繊維が豊富な食材として知られています。
Q9 : 野菜の中で『ペクチン』が多く含まれているのはどれか?
ペクチンは、主に果実や野菜の細胞壁に含まれる多糖類の一種で、ゼリー状を作る役割があります。特にトマトはペクチンを多く含み、そのためトマトを加工して作るジャムやケチャップが固まりやすいです。他にもリンゴや柑橘類にも多いですが、野菜の中ではトマトが代表的です。
Q10 : アスパラガスの食用部はどの部分ですか?
アスパラガスの食用部は土から伸びてくる若い茎の部分です。収穫する時期によって、アスパラガスは柔らかく甘みも増します。実はアスパラガスにも花や実ができるのですが、一般的に市販されているものは茎の部分が多く出回っています。栄養価も高く、β-カロテン、ビタミンC、葉酸などを豊富に含んでいるのが特徴です。
まとめ
いかがでしたか? 今回は野菜難しいクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は野菜難しいクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。