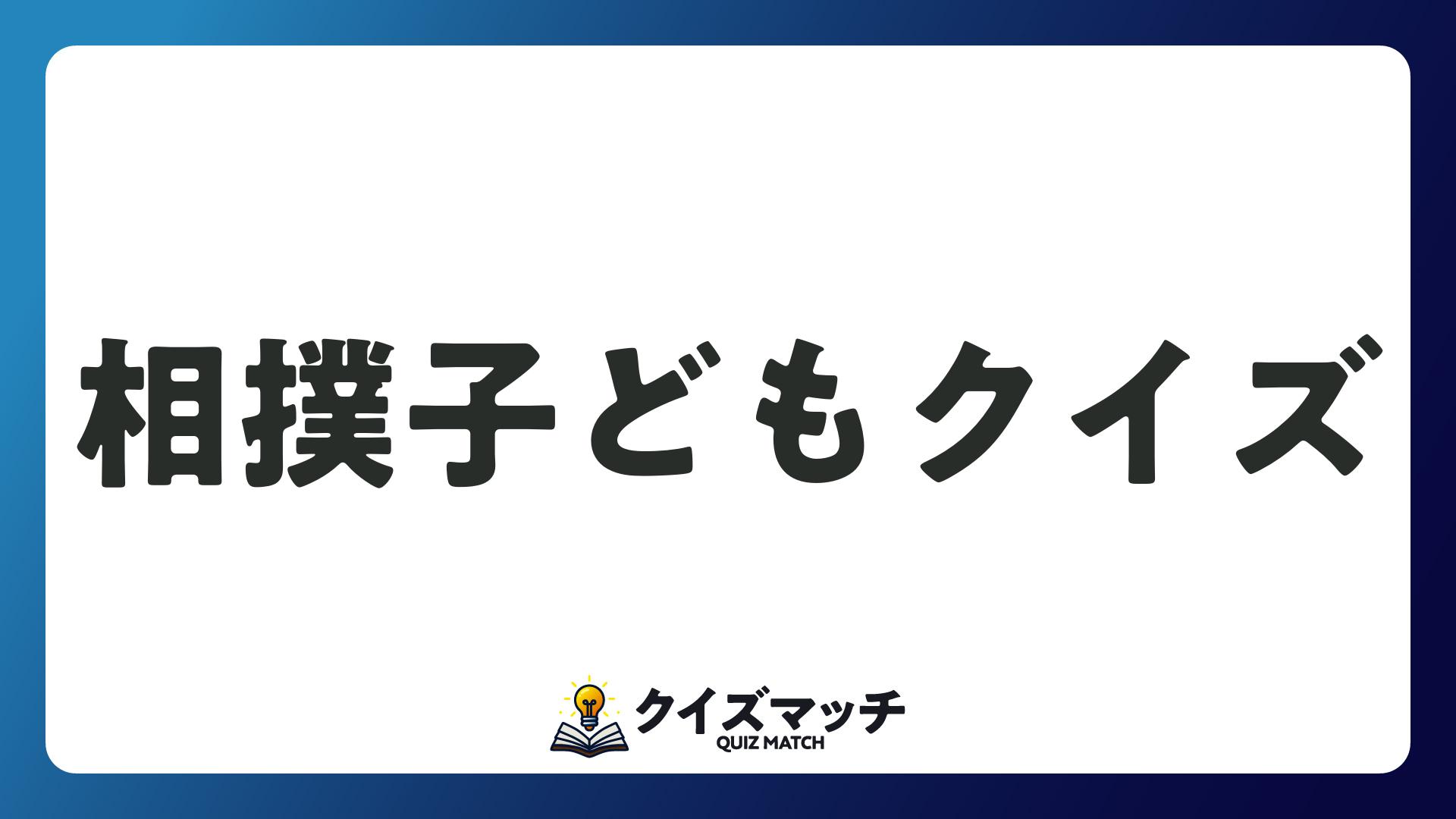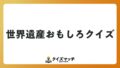相撲には、長い歴史と伝統が息づいています。その魅力を子どもたちにも伝えるべく、相撲に関する楽しい10問のクイズをご用意しました。土俵の形や力士の称号、儀式など、相撲ならではの独特の文化について学べる内容です。この機会に、子どもたちに相撲の世界を少しでも知ってもらえればと思います。みなさんも一緒に相撲クイズにチャレンジしてみましょう。
Q1 : 次のうち、相撲の本場所が行われていない都市はどれ?
現在、相撲の本場所が開催されているのは、東京(両国)、大阪、名古屋、福岡の4都市のみです。札幌では本場所は行われていません。札幌では巡業(地方場所)はありますが、本場所はありません。本場所は1月東京、3月大阪、5月東京、7月名古屋、9月東京、11月福岡で開催されます。
Q2 : 相撲で使う『まわし』の色が決まるのは誰の判断ですか?
力士の『まわし』の色は、基本的に本人が好きな色を選びます。新人の下位力士の場合は黒のまわしが基本ですが、上位になれば好きな色を選ぶことができます。色にはゲン担ぎや個性が反映されます。協会が一律に決めたり、親方やファンの投票で決まることはありません。
Q3 : 幕内力士の毎場所の番付発表はどのように行われますか?
番付は昔ながらの和紙に力士のしこ名を筆書きした「紙」に印刷されて発表されます。この発表は場所の約2週間前に行われます。伝統様式を守っており、最近はインターネットでも見られますが、基本は紙です。土俵上で口頭発表はしませんし、テレビのみということもありません。
Q4 : 相撲の取組で制限時間いっぱいを知らせるために使う音は何?
相撲の取組が始まる直前、「制限時間いっぱい」を知らせるときは、木を打ち合わせた「拍子木の音」を使います。これは独特のリズムで、一試合ごとに場内に響き渡ります。鐘や太鼓ではなく、行事が木を打ち鳴らす音が合図となります。拍子木の音は日本の伝統的な音風景のひとつでもあります。
Q5 : 相撲の行司は何を使って勝敗を示しますか?
相撲の行司は「軍配」(ぐんばい)という道具を使って勝敗を示します。軍配はもともと戦で指揮官が兵を指示するために使う道具ですが、相撲では勝った方に軍配を向けて勝者を示します。扇子やうちわによく似ていますが、正式には軍配という名称です。指だけで勝敗を示すことはありません。
Q6 : 相撲の勝敗を決める際に使われる言葉『寄り切り』は何を意味しますか?
『寄り切り』とは、相手の体をまっすぐ前に押し、土俵の外へと押し出す技のことを指します。直接倒すわけではなく、体を密着させたまま力を込めて土俵外へ追い出すことが勝ちとなります。他の選択肢のように倒したり担いだりする技ではありません。最も基本的な決まり手の一つです。
Q7 : 力士が試合前に土俵にまく白い粉は何ですか?
相撲で力士が土俵にまく白い粉は「塩」です。これは清めの儀式の一つで、土俵を清浄に保つ意味と怪我をしないようにする願いが込められています。食塩には殺菌効果もあり、伝統的な儀式となっています。砂糖や小麦粉、砂ではありません。塩まきは外国人にもユニークで興味深いポイントとして認知されています。
Q8 : 相撲の土俵入りで力士が手に持つものはどれですか?
横綱が行う土俵入りの際には「しめ縄」を体に巻いて登場します。これは神聖なものとされ、神を祀る意味も込められています。軍配や扇子は行司が持つものであり、たてがみは馬の髪ですが相撲とは関係ありません。しめ縄はご利益や清浄を示すためのもので、神聖な雰囲気を強調します。
Q9 : 相撲で一番位が高い力士の称号は何ですか?
相撲の階級では、横綱が最高位にあたります。横綱は勝ち星や品格などで認められた場合のみ昇進できる特別な存在です。大関も高い位ですが、横綱ではありません。関脇や小結も幕内上位ではありますが、横綱より下です。横綱になると基本的に降格はありませんが、成績不振や不祥事などで引退することもあります。
Q10 : 相撲の土俵の形はどれですか?
相撲の土俵は丸い形をしており、正式な競技場では直径4.55mの円形です。この円周上で相撲が取られ、力士が土俵の外に出たり、地面に体の一部がついたりしたら負けとなります。四角形や三角形ではなく、丸型が正しい解答です。土俵の周囲は俵で囲まれていて、これがしきいとして役目を果たしています。
まとめ
いかがでしたか? 今回は相撲 子どもクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は相撲 子どもクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。