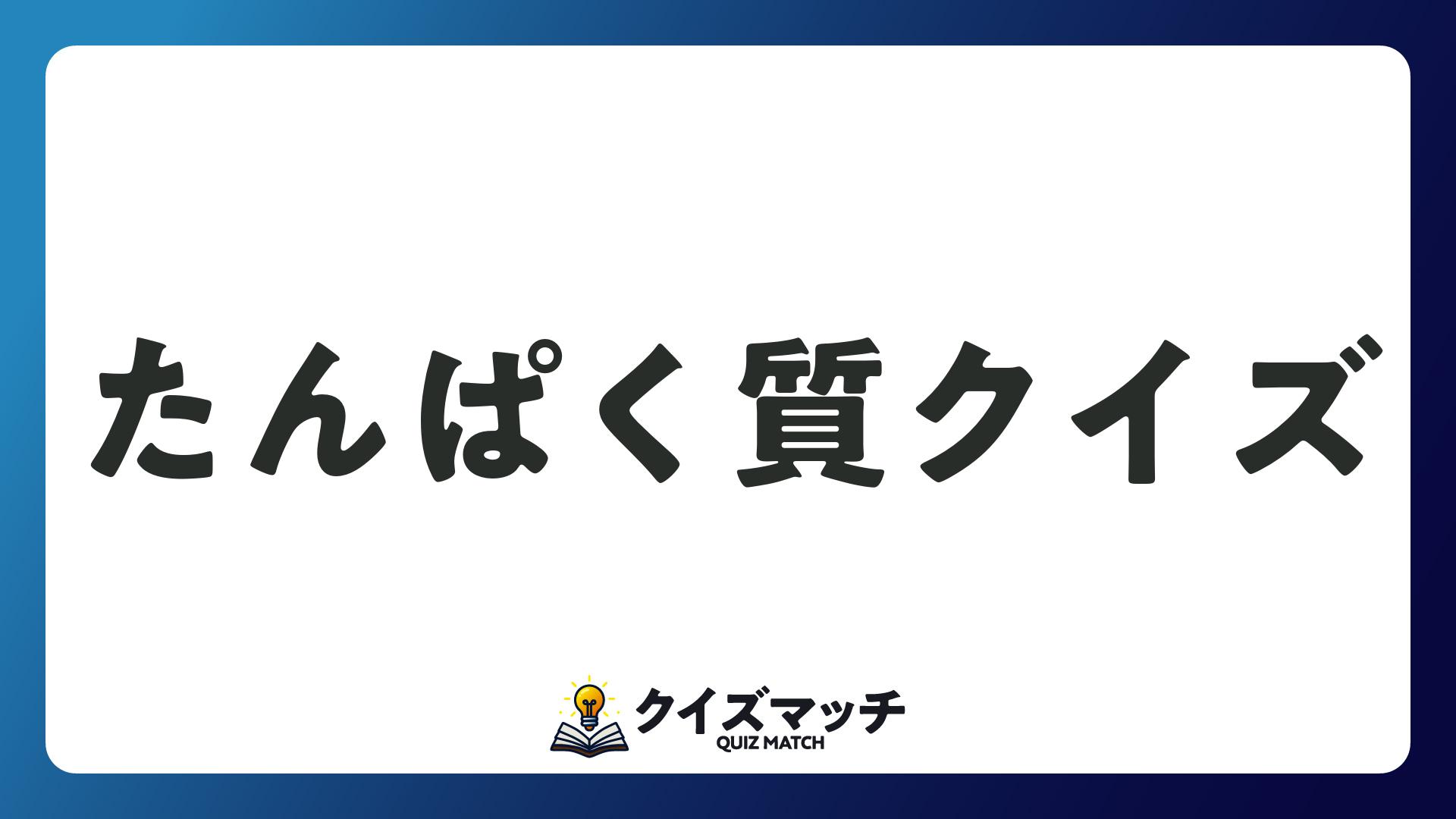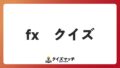私たちにはたんぱく質がとても大切な役割を果たしていることをご存知でしょうか。たんぱく質は主に体の構成成分として、筋肉や内臓、酵素やホルモンなどに重要な働きをしています。一方でエネルギー源としての役割もあります。この記事では、たんぱく質のさまざまな特性を10問のクイズを通して楽しく学んでいただけます。食べ物に含まれるたんぱく質の種類や、人体におけるたんぱく質の機能など、基礎から応用まで網羅しています。たんぱく質について理解を深め、健康的な食生活につなげていただければと思います。
Q1 : たんぱく質の摂取量の目安として、日本人の食事摂取基準(2020年版)で示されている成人男性(18~64歳)の推奨量は1日あたり何gか?
日本人の食事摂取基準(2020年版)によれば、18~64歳男性の1日推奨量は65gです。これは健康を維持し、日常生活で必要なたんぱく質をまかなうのに必要な量ですが、個人差や活動量によっても変わります。摂りすぎや不足には注意が必要です。
Q2 : たんぱく質の構造に関わる結合はどれか?
たんぱく質は、アミノ酸同士が「ペプチド結合」という結合によってつながり、一次構造を形成しています。また、立体構造形成には水素結合も関与しますが、基本単位同士をつなぐのが「ペプチド結合」です。
Q3 : 次のうち、たんぱく質の主な機能ではないものは?
たんぱく質は酵素やホルモン、抗体の材料となるなど多彩な生体機能を担います。しかしエネルギー供給だけを主な機能にしているわけではありません。主に炭水化物の補完的にエネルギー源となります。
Q4 : たんぱく質1gあたりのエネルギー量(kcal)は?
たんぱく質1gあたりのエネルギーは4kcalです。これは炭水化物と同じエネルギー量ですが脂質は1gあたり9kcalと高くなっています。たんぱく質の主な役割はエネルギー供給というより体の構成成分となることです。
Q5 : たんぱく質が不足すると起こる主な症状はどれか?
たんぱく質が不足すると、筋肉量が減少しやすく、免疫力の低下や疲れやすさ、むくみが出ることがあります。これはたんぱく質が筋肉や体組織、酵素、ホルモンの構成に必要不可欠だからです。骨や視力、体温は直接的な影響を受けにくいです。
Q6 : たんぱく質は体内で分解されると、主に何にまで分解されるか?
たんぱく質は消化酵素によって最終的にアミノ酸に分解され、小腸から吸収されます。アミノ酸は体内で新たなたんぱく質の合成や代謝に利用される重要な物質です。脂肪酸やグルコース、核酸はたんぱく質の分解産物ではありません。
Q7 : 大豆のたんぱく質は、次のうちどれに分類されるか?
大豆のたんぱく質は植物性たんぱく質に分類されます。動物性たんぱく質は肉や魚、卵などに含まれますが、植物性は大豆や豆類、穀物などが主な供給源です。近年は大豆由来のたんぱく質が健康志向の人にも注目されています。
Q8 : ヒトの体内で合成できず、食事から摂取しなければならないアミノ酸を何というか?
必須アミノ酸とは、体内で十分に合成できず、食事から摂取する必要のある9種類のアミノ酸を指します。例えば、ロイシン、リジン、トリプトファンなどです。これが不足すると、成長障害や健康被害が起きるため、バランスよく摂取することが大切です。
Q9 : 動物性たんぱく質が多く含まれている食品は次のうちどれか?
卵は動物性たんぱく質が豊富な食品の代表例です。卵白は特に純度の高いたんぱく質を含んでおり、必須アミノ酸のバランスも良好です。小麦やご飯は主に炭水化物、豆腐は植物性たんぱく質を多く含みますが、動物性たんぱく質ではありません。
Q10 : たんぱく質は主にどの栄養素に分類されるか?
たんぱく質は三大栄養素(炭水化物・脂質・たんぱく質)のうちの一つで、主に体を作る材料として重要な働きをします。筋肉や臓器、皮膚、酵素、ホルモンなど、人体の多くの部分がたんぱく質からできています。また、エネルギー源にもなりますが、主な役割は体の構成成分です。
まとめ
いかがでしたか? 今回はたんぱく質クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回はたんぱく質クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。