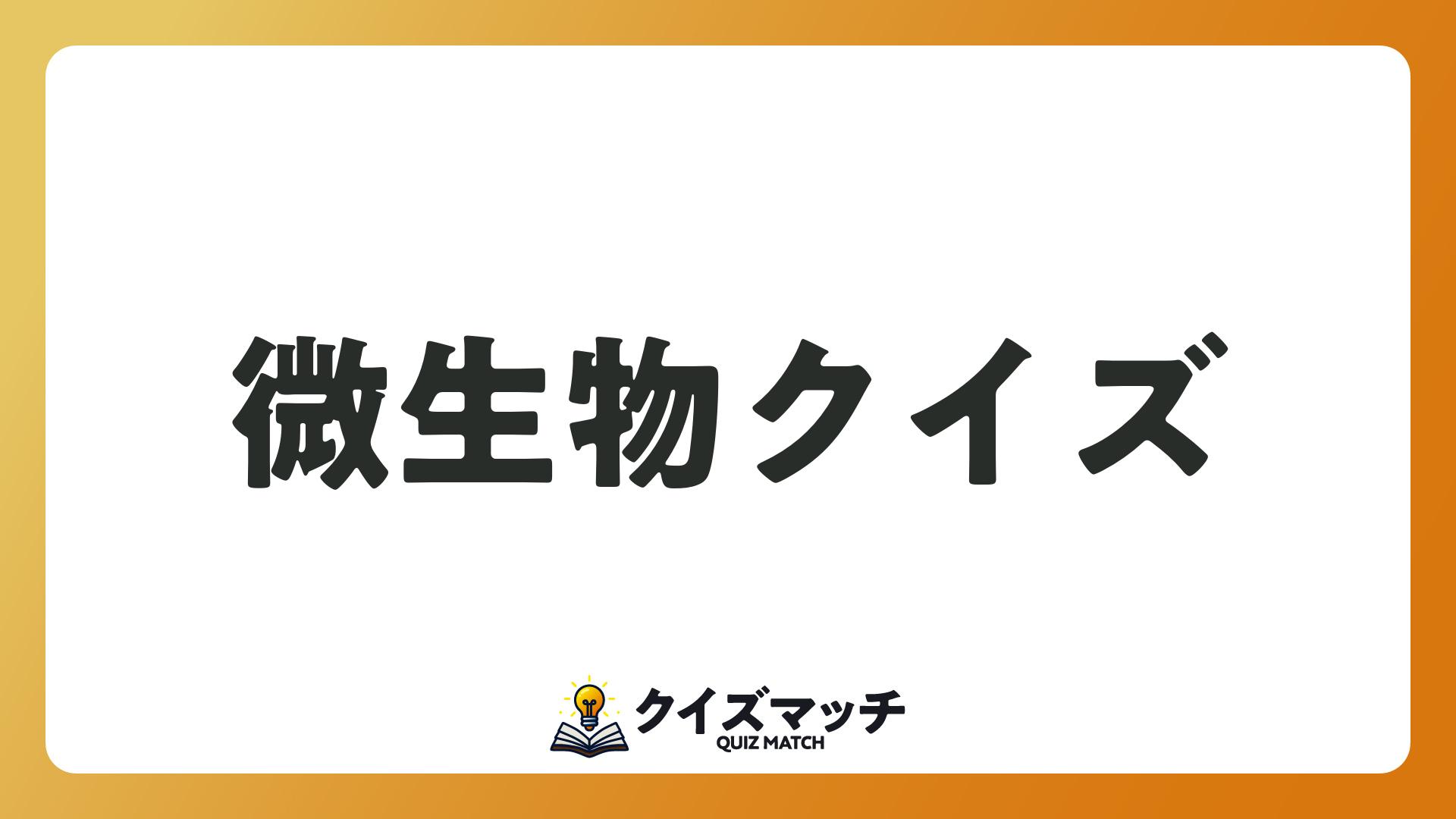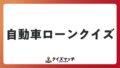微生物はこの世界を支える不可欠な存在です。私たちの身体の中にも、食べ物の中にも、様々な微生物が住み着いています。この微生物クイズでは、そんな微生物の不思議な性質や役割について、楽しみながら学んでいきましょう。細菌からウイルス、そしてカビやイーストまで、微生物の多様性を知ることで、私たちの生活や健康との関わりを深く理解することができます。次のクイズを通して、微生物の魅力に迫っていきます。
Q1 : 高温や高塩濃度でも生育できる微生物を何と呼びますか?
高い塩濃度環境で生育可能な微生物は「好塩菌」と呼ばれます。好塩菌は塩湖や塩田などの極限環境に適応しており、細胞の浸透圧調整やたんぱく質機能維持のため特殊な適応機構を持ちます。味噌や醤油の発酵にも利用されています。
Q2 : 納豆菌(Bacillus subtilis var. natto)の特徴はどれですか?
納豆菌は50度前後の高温を好み、納豆独特の発酵に必要な強い発酵力を持ちます。この菌は納豆のネバネバ成分であるポリグルタミン酸を産生し、タンパク質の分解能力も高いです。そのため独特の味や香りを作り出します。
Q3 : 次のうち、偏性嫌気性菌はどれ?
クロストリジウム属(Clostridium)は偏性嫌気性菌で、酸素が存在すると生存できません。破傷風菌やボツリヌス菌など人体に有害な種も含みます。嫌気的条件下でのみ増殖し、酸素を避けるため芽胞の形成にも関与します。
Q4 : ヒトのインフルエンザウイルスが主に感染する細胞は何ですか?
インフルエンザウイルスは呼吸器上皮細胞を主な標的とします。ウイルスは鼻や喉、気管支の粘膜細胞に侵入して増殖し、発熱や咳などの症状を引き起こします。細胞表面のシアル酸を利用して取りつくことが、感染サイクルの重要なステップです。
Q5 : 結核菌(Mycobacterium tuberculosis)はどのような特徴を持っていますか?
結核菌はグラム染色では染まりにくい(中間的な性質をもつ)が、特に耐酸性が高く、抗酸菌と呼ばれます。ワックス状の細胞壁を持ち、アルコールや酸への抵抗性を示します。この特徴が診断や治療の難しさにつながっています。
Q6 : 炭疽菌(Bacillus anthracis)の特徴として正しいものはどれですか?
炭疽菌(Bacillus anthracis)はグラム陽性の桿菌であり、芽胞を形成します。芽胞は極めて高い耐久性をもち、過酷な環境下でも生存可能です。芽胞の特徴が炭疽菌の感染力と環境中での持続性、またバイオテロ要因としての利用のリスクに繋がっています。
Q7 : ペニシリンを発見した微生物は次のうちどれか?
ペニシリンはアオカビ(Penicillium notatum)から抽出された初の抗生物質です。1928年、アレクサンダー・フレミングによって発見され、その後多くの感染症治療に革命をもたらしました。アオカビは土壌などに広く存在している真菌です。
Q8 : 乳酸菌の主要な代謝産物はどれですか?
乳酸菌は糖を分解して乳酸を生成することで知られており、その代謝産物が乳酸です。この乳酸によって環境は酸性化し、食品保存性の向上や腸内フローラの調整に役立ちます。ヨーグルトや漬物など発酵食品の製造に欠かせません。
Q9 : ヒトの腸内細菌で最も数が多いとされるグループはどれですか?
ヒト腸内には多様な細菌が共生していますが、最も数が多いのはバクテロイデス門(Bacteroidetes)に属する細菌です。特に、大腸ではバクテロイデス属とファーミキューテス門(Firmicutes)に属する細菌が圧倒的に多く、消化を助けたり、免疫調節の役割を果たしています。
Q10 : イースト菌はどの分類群に属する微生物ですか?
イースト菌(酵母菌)は真菌に属する微生物です。パンの発酵や酒造りなどに利用されているイースト菌は、単細胞の真核生物であり、細菌とは異なり核膜をもちます。真菌にはカビやキノコも含まれますが、イースト菌は発酵能力の高さから食品産業で特に重要な役割を担っています。
まとめ
いかがでしたか? 今回は微生物クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は微生物クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。