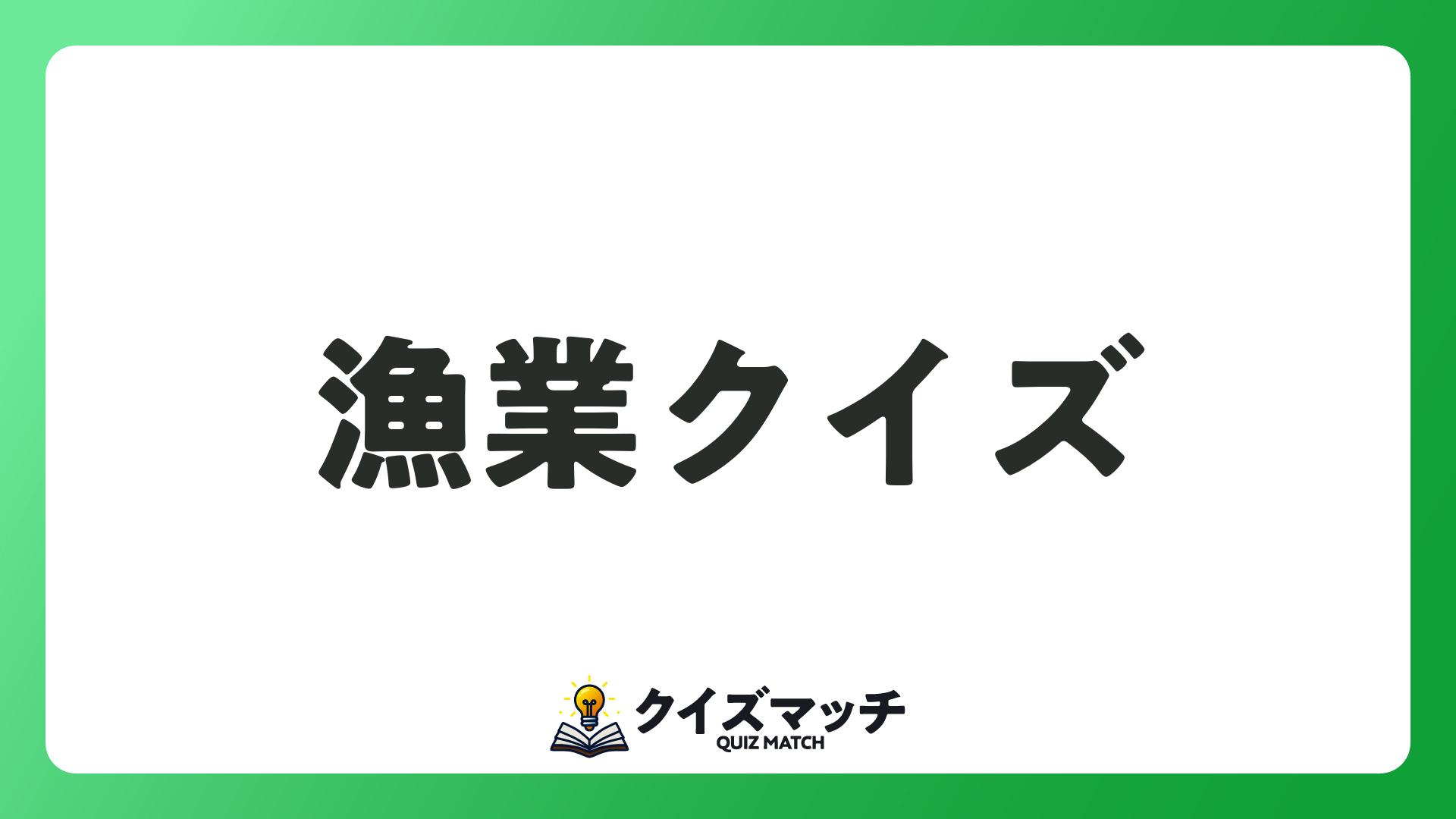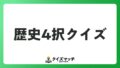日本は世界有数の漁業大国として知られていますが、その豊かな水産資源と漁業実態についてあまり知られていないのが現状です。この記事では、日本の漁業に関する10の興味深いクイズをお届けします。イワシやサバ、マグロなどの主要な水産物から、EEZやTAC制度といった漁業制度まで、さまざまな角度から日本の漁業の実態に迫ります。漁業に関する知識の幅を広げ、日本の水産業についてより理解を深めていただければ幸いです。
Q1 : 「海女」が主に行う漁業は何と呼ばれる?
「海女」とは、伝統的に素潜りによってアワビやサザエ、ウニなどを採取する女性漁師のことを指します。このような漁は「素潜り漁」と呼ばれ、道具を用いずに自らの力で潜水し海産物を採取するため、昔から続く日本独特の漁法です。
Q2 : 日本の「遠洋漁業」で代表的に漁獲される魚は?
日本の遠洋漁業は、国内から遠く離れた海外の海域で操業します。その代表的な魚がマグロです。日本のマグロ漁船は世界中の海を舞台に操業しており、マグロ類全体の消費量・流通量も世界最大級です。
Q3 : 日本で「青魚」と呼ばれる代表的な魚はどれ?
青魚とは、背が青い色をした魚類の総称で、DHAやEPAといった健康成分が豊富なのが特徴です。代表的な青魚にはサバ、イワシ、アジなどがあります。タイやフグは赤身、白身の魚であり、青魚には分類されません。
Q4 : 日本の漁業で使われる「沖合底びき網漁業」で主に獲れる魚は?
沖合底びき網漁業は、海底付近に生息する魚介類を一網打尽にする方法です。主にタラやカレイ、エビ類などがこの漁法で漁獲されており、タラが最も代表的な魚です。カツオやサンマ、マグロはこの漁法ではほとんど漁獲されません。
Q5 : ノルウェーが主に養殖している魚はどれ?
ノルウェーはサーモン養殖の世界的先進国であり、アトランティックサーモンの生産量は世界一です。ノルウェーサーモンは日本だけでなく世界中に輸出されています。イカやマグロ、ニシンも漁獲されていますが、養殖ではサーモンが圧倒的です。
Q6 : 日本の伝統的な定置網漁業の主な対象魚は?
定置網漁業は、日本の沿岸で古くから続く伝統的な漁法です。季節によってさまざまな魚が対象になりますが、特にブリが代表的な対象種とされています。ブリは出世魚としても有名で、冬には脂がのって高値で取引されます。
Q7 : 漁獲量の過剰抑制と資源管理のために導入される制度は何?
TAC(Total Allowable Catch)制度は、漁獲を資源量に応じて制限するために導入された制度です。対象となる魚種ごとに年間漁獲可能量を定め、資源の持続可能な利用を目指しています。GDPやEPAは経済・貿易に関する用語、ISOは国際標準化の規格です。
Q8 : 日本三大漁港のひとつに数えられる漁港はどこ?
日本三大漁港とは、焼津漁港(静岡)、銚子漁港(千葉)、釧路漁港(北海道)です。その中でも焼津漁港はカツオやマグロの水揚げで有名です。函館や八戸も大きな漁港ですが、三大漁港には含まれません。
Q9 : 日本の漁業区域を示す用語で、EEZは何の略?
EEZは「Exclusive Economic Zone(排他的経済水域)」の略で、国連海洋法条約に基づき、沿岸国が領海基線から200海里以内の水域で漁業資源などを独占的に利用・管理できる権利を持つ区域です。日本のEEZは世界でも6番目の広さを誇ります。
Q10 : 日本で最も漁獲量が多い魚はどれ?
日本で最も漁獲量が多い魚はイワシです。特に、カタクチイワシやマイワシなどが大量に漁獲され、魚粉や飼料、加工品など幅広く活用されています。イワシは資源量の変動が大きいですが、日本の水産業において重要な位置を占めています。サバやアジ、サンマも漁獲量が多い魚ですが、イワシの総漁獲量には及びません。
まとめ
いかがでしたか? 今回は漁業クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は漁業クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。