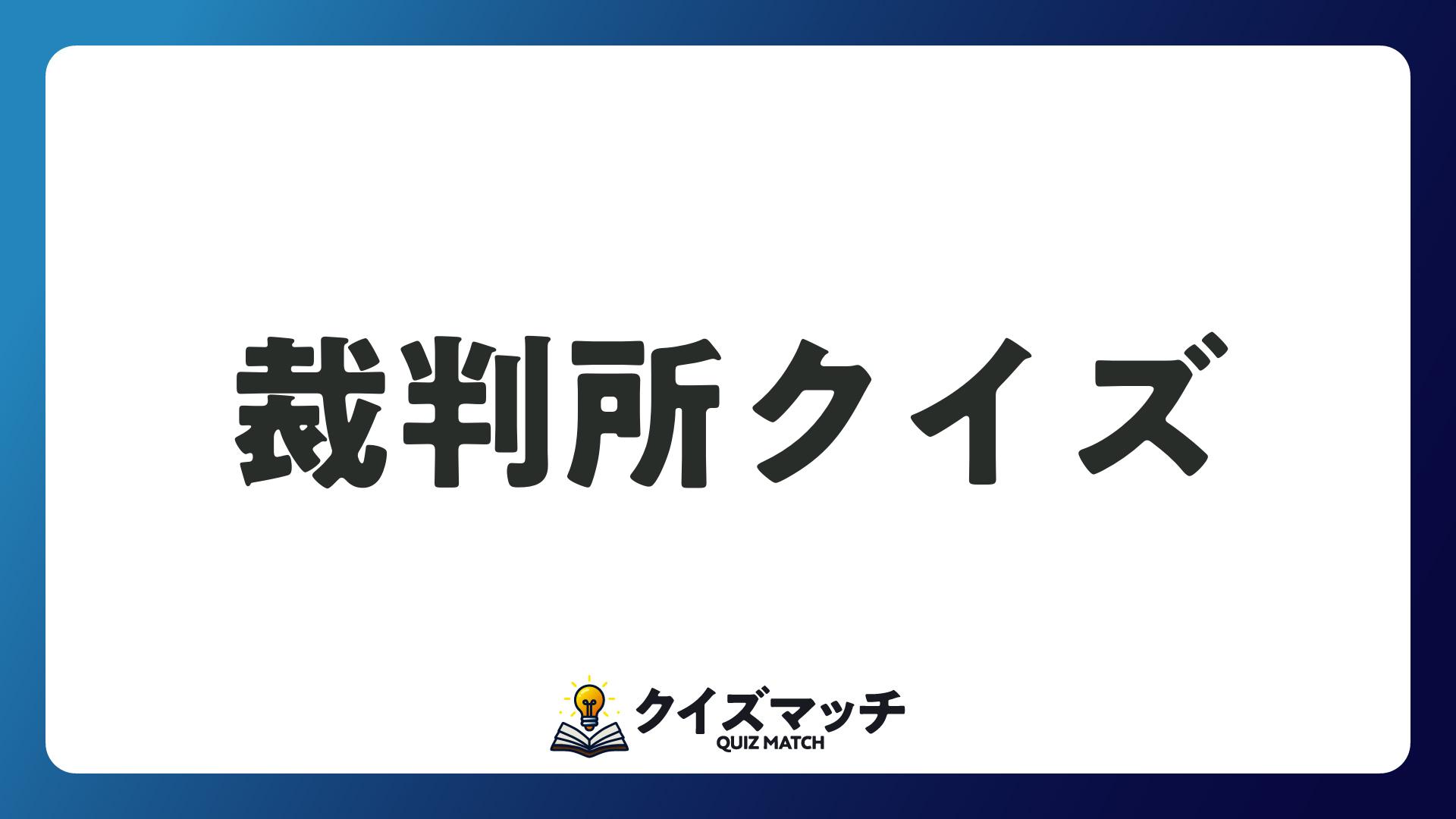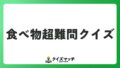現代社会に欠かせない司法制度について、最高裁判所の立地や裁判官の任命方法、裁判所の種類と役割など、基本的な知識を問うクイズを10問ご用意しました。判例や手続きの細かい内容だけでなく、司法制度の全体像を理解するためのクイズも含まれています。この記事を通して、日本の司法制度について興味関心を持っていただければと思います。
Q1 : 家庭裁判所が扱う事件として最も適切なものはどれですか?
家庭裁判所は家事事件(離婚、親権、遺産分割など)や少年事件を主に扱います。民事事件の中で家庭に関することであればここが担当です。刑事事件や商取引、行政訴訟はそれぞれ別の裁判所が担当します。
Q2 : 高等裁判所の数は日本国内でいくつですか?
日本全国には現在8つの高等裁判所があります。東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、そして高松です。それぞれの管轄地域ごとに設置されており、全国を網羅しています。
Q3 : 日本の司法制度における三審制とは、どのような意味ですか?
三審制とは、同じ事件について三回まで異なる階級の裁判所で裁判を受けられる制度です。具体的には、第一審(例:地方裁判所)、第二審(高等裁判所)、第三審(最高裁判所)まで、判決に不満がある場合は順に上級の裁判所に上訴できます。
Q4 : 最高裁判所の裁判官のうち、長官以外の裁判官の定年は何歳ですか?
最高裁判所の裁判官(長官を除く)の定年は65歳です。長官についても65歳で退官することが定められています。高等裁判所や地方裁判所の裁判官も同じく65歳が定年となっており、それ以上務め続けることはできません。
Q5 : 裁判所で行われる「公判」とはどのような手続きですか?
公判とは、刑事裁判において証拠調べや弁護人・検察官による主張などが公開の場で行われる手続きです。被告人の有罪・無罪や量刑を決めるための審理が行われ、原則公開が原則です。判決のみならず、審理自体を指します。
Q6 : 裁判員制度が適用されるのはどの刑事事件ですか?
裁判員制度が適用されるのは殺人、強盗致死傷などの重大な刑事事件のみです。すべての刑事事件や少年事件、民事事件には適用されません。裁判員制度は国民の意見や感覚を刑事裁判に反映させるために導入されました。
Q7 : 刑事事件の被告人が不起訴判断に不服がある場合、どのような手続きをとることができますか?
刑事事件で不起訴となった場合、被害者や関係者は検察審査会に申立てをすることができます。検察審査会は一般市民が参加して検察官の不起訴判断が妥当かを審査し、不起訴不当と判断すれば再度検察に起訴を促すことができます。その他の手続きは本問の事例には該当しません。
Q8 : 日本の裁判において、第一審を行う主な裁判所はどこですか?
日本では民事・刑事案件ともに、多くの第一審が地方裁判所で行われます。簡易裁判所は軽微な事件に、家庭裁判所は家事事件や少年事件などに特化しています。高等裁判所は原則として控訴審を担当します。従って一般的な第一審は地方裁判所が担当します。
Q9 : 日本の裁判官はどのようにその職に就任しますか?
日本の裁判官は原則として内閣によって任命されます。最高裁判所長官だけは天皇が内閣の指名によって任命します。普通の裁判官や高等裁判所長官は内閣が直接任命します。選挙や国民投票によって任命されるわけではありませんが、最高裁判所の裁判官については国民審査という制度もあります。
Q10 : 日本における最高裁判所の所在地はどこですか?
日本の最高裁判所は東京都千代田区隼町に所在しています。最高裁判所は、日本の司法の最上位にある裁判所であり、最終的な憲法判断や法律の解釈を行います。地方裁判所や高等裁判所が全国各地にありますが、最高裁判所は全国で一か所のみであり、首都東京内に設置されています。
まとめ
いかがでしたか? 今回は裁判所クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は裁判所クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。