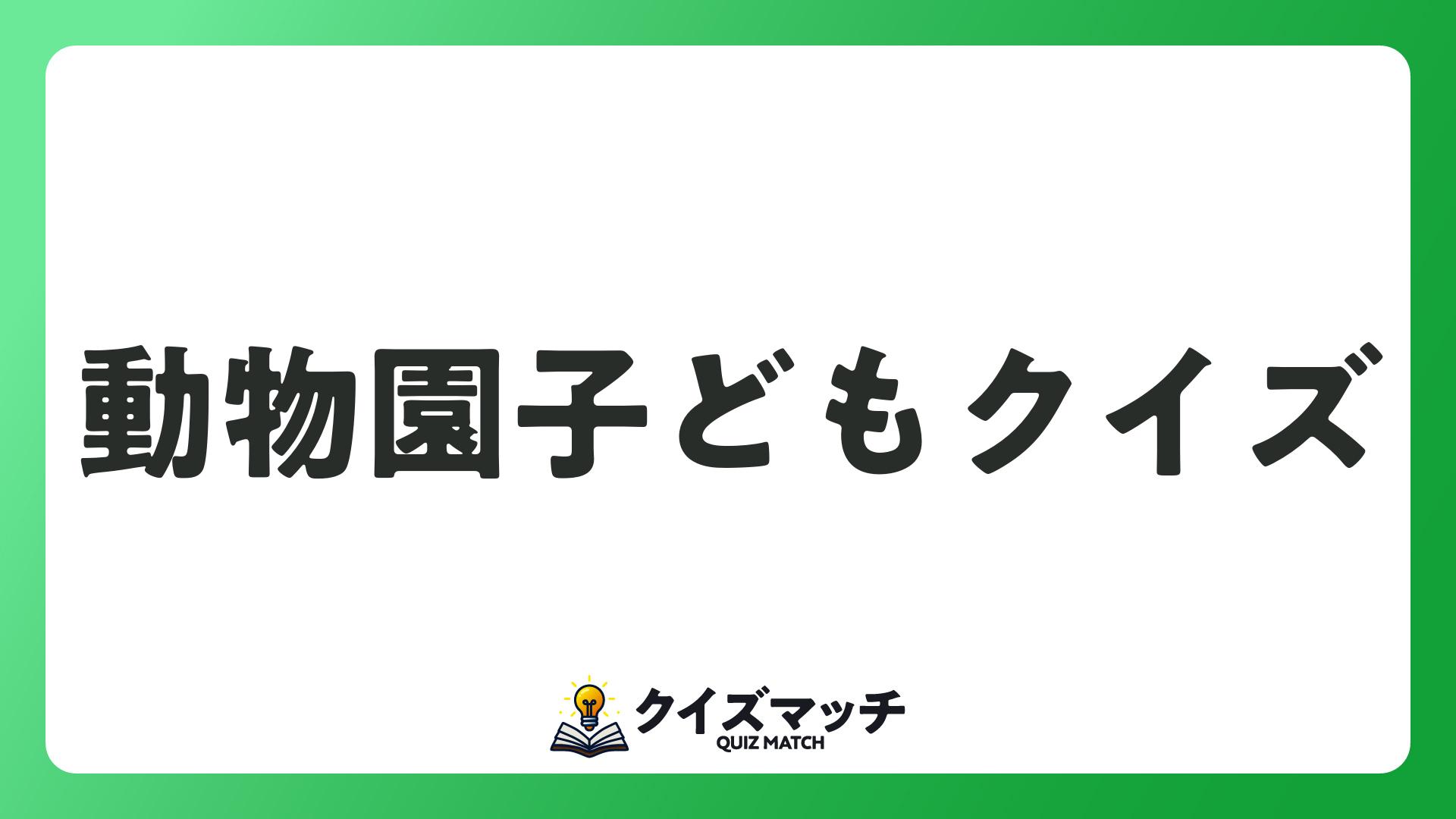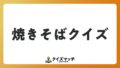子どもに人気な動物園の住人たちについて、楽しいクイズをご用意しました。キリンの首の骨の数や、ゾウの鼻の使い道、夜行性のレッサーパンダなど、見た目とは違う意外な事実がたくさん。動物の習性や生態を知れば、きっと動物園のさらなる魅力が発見できるはずです。ぜひ、この機会に家族みんなでクイズに挑戦してみてください。クイズを通して、動物たちの驚くべき特徴をお楽しみください。
Q1 : アシカは前足で歩いたりジャンプしたりできる。
アシカは前足(前びれ)を器用に使って陸上を歩いたり、小さなジャンプをしたりすることができます。アザラシは体を這うようにしか移動できませんが、アシカは体を持ち上げて移動できるため、動物園のショーでもコミカルな動きが人気です。前びれの発達のおかげで、陸でも活発に動き回れます。
Q2 : ライオンのオスだけたてがみがあるのはなぜ?理由は体を守るためである。
オスのライオンは、首から肩にかけて長いたてがみを持っていますが、これはライオン同士が戦うときや敵から攻撃されたときに頭や首を守る役割があります。たてがみは厚くて硬いため、けがをしにくくなっています。また、たてがみの立派さがメスへのアピールにもなっているとも言われています。
Q3 : レッサーパンダは夜行性である。
レッサーパンダは主に夜や明け方、夕方に活動する夜行性の動物です。昼間は木の上や草むらでゆっくり寝ていることが多いです。野生では夜や早朝にエサを探し、動物園でも夕方以降に活発に動く姿がよく見られます。夜行性のため、動物園では寝ていることも多いです。
Q4 : フラミンゴの羽の色がピンクなのは食べ物と関係がある。
フラミンゴの羽の色がピンクなのは、主に食べているエサに含まれるカロテノイド色素という成分の影響です。エビやプランクトンなど、この色素を多く含む食べ物を食べることで、羽が鮮やかなピンク色になります。もし色素の少ないエサだけを食べると色あせて白っぽくなる場合もあります。
Q5 : カバは泳ぐのが得意で水中でもとても速く動ける。
カバは水辺で生活しますが、実は『泳ぐ』というより川や池の底を歩いて移動することが得意です。足が短くて体が重いため、浮くことよりも底を歩く方が素早く動けます。水の中で目や鼻を出して呼吸している姿も有名です。泳ぎ自体は得意ではありませんが、水中で敏捷に動けます。
Q6 : ゴリラは野性で家族を作って暮らしている。
ゴリラは野生で群れを作って暮らします。この群れは『家族』と呼ばれることが多く、リーダー格の雄「シルバーバック」1頭と雌や子どもたちで構成されます。ゴリラはとても社会的な動物で、仲間たちと協力しながら生活しています。動物園でも同じように複数のゴリラで群れを作って飼育されることが多いです。
Q7 : コアラは一日にどれぐらいの時間寝ることが多いでしょう?
コアラは一日におよそ18~20時間、長いと22時間も寝ることがあります。ユーカリの葉を主食としているため、消化に時間がかかるほか、エネルギーがあまり摂れないので、あまり動かずよく寝ることで体力を温存しているのです。動物園でコアラが寝ていることが多いのはこのためです。
Q8 : ゾウの鼻は口のように物をつかむことができます。
ゾウの鼻(鼻先)はとても発達しており、物をつかみ、持ち上げ、口に運ぶことができます。例えば草をつかんで食べたり、水をすくって飲んだりします。ゾウの鼻は筋肉がたくさんあり、非常に器用です。人間の手のように細かい作業もできるので、食事や水を飲むときには欠かせない道具になっています。
Q9 : パンダはもともと雑食ですが、主に何を食べているでしょうか?
パンダは実は本来雑食性のクマ科の動物ですが、野生のパンダは主に竹を食べています。竹以外にも時々小さな動物や魚も食べますが、竹が最も大きな割合を占めており、一日に10kg以上食べることもあります。動物園でも竹を主食として与えられています。
Q10 : キリンの首の骨の数は人間と同じ7つです。
キリンの首はとても長いですが、実は骨の数は人間と同じく7つです。人間もキリンも哺乳類のため、首の骨(頸椎)の数は同じなのです。ただし、キリンの首の骨は1つ1つがとても大きく長いので、見た目は違います。進化の過程で骨の数が変わったのではなく、骨そのものが長くなったことで首が長くなったのです。
まとめ
いかがでしたか? 今回は動物園 子どもクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は動物園 子どもクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。