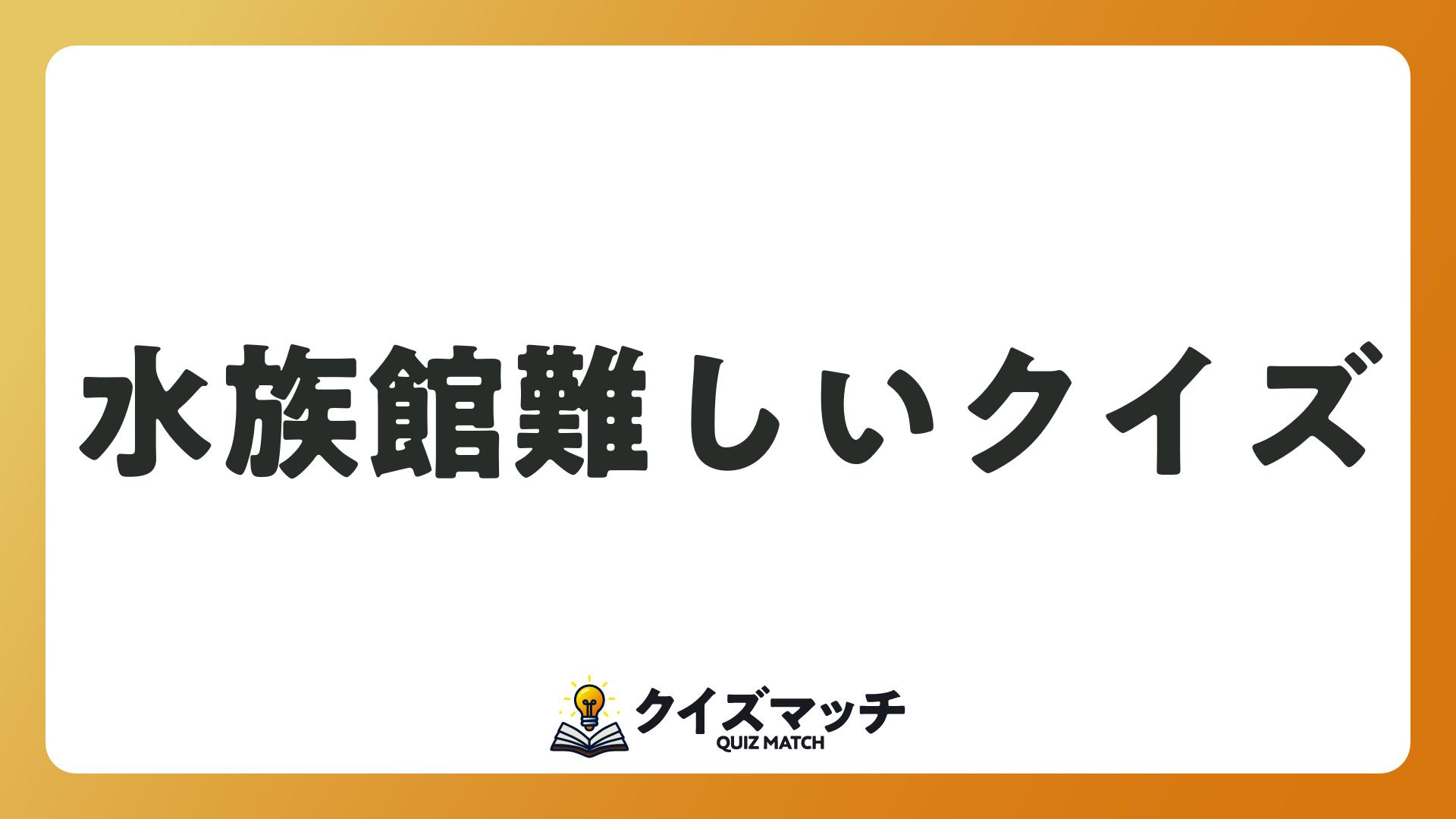水族館のファンなら誰もが知りたがる難しい水族館クイズ10問!世界最大の淡水魚や、日本を代表する水族館の特徴など、見逃せない貴重な情報が満載です。ジンベエザメやチンアナゴ、クラゲといった人気の生物について、その魚種の特性や水族館での飼育状況を詳しく解説。さらに、イルカとクジラの違いや、ラッコの原産地など、一般的にはあまり知られていないトピックスにも迫ります。水族館通も、初めての方も必見のクイズ集です。知識を深めながら、ワクワクする驚きの事実に出会えるはずです。
Q1 : サンゴ礁水槽に欠かせない照明の役割は?
サンゴは体内の褐虫藻と共生し、褐虫藻が行う光合成によって栄養を得ています。そのためサンゴ水槽では太陽光に近い強い照明が不可欠となります。照明がないとサンゴは衰弱し、やがて死んでしまうため、水族館では照明にこだわった水槽管理が行われます。
Q2 : 日本で一番古い海浜水族館はどこ?
鳥羽水族館(三重県)は1955年開館の歴史ある水族館で、日本初の海浜水族館です。多様な生きものの飼育・展示で知られ、ラッコやジュゴンの飼育でも有名になりました。
Q3 : タコが水族館で水槽を脱走することがあるのはなぜ?
タコは頭が良く、体を極めて柔軟にできるため、わずかな隙間からでも水槽の外へ出ることができます。餌の探索や好奇心による脱走がよく報告されており、世界中の水族館でしばしば問題となっています。
Q4 : 淡水エイの仲間が主に生息している場所はどこ?
淡水エイの多くは南米アマゾン川流域に自然分布しています。河川やその支流で独自に発達した種類が多く、独特な模様と丸い形状が特徴です。他の地域にも淡水エイがいますが、種類・数ともにアマゾン川流域が中心です。
Q5 : 水族館でよく見る『ラッコ』の原産地はどこ?
ラッコは主に北太平洋沿岸、特にアラスカ沿岸で多く生息します。かつては日本にも生息していましたが、商業捕獲の影響で絶滅状態となっています。水族館で見られるラッコは多くがアラスカ周辺を原産地としています。
Q6 : イルカとクジラの最大の違いは何?
イルカとクジラの違いについては明確な分類基準がないのが事実です。生物学的には歯クジラ亜目・ヒゲクジラ亜目と分けますが、イルカも『クジラ』の一種です。大きさで便宜上呼び分けることがありますが、厳密な境界はなく、分類の基準が明確かと言われるとそうではありません。
Q7 : クラゲの常時大量展示で有名な水族館はどこ?
山形県の鶴岡市立加茂水族館は「クラゲドリーム館」として世界に誇るクラゲ展示数を誇ります。様々な種類のクラゲが常時約60種以上展示され、クラゲの生態や美しさを間近で観察できます。他の水族館でもクラゲ展示はありますが、加茂水族館ほどの大規模展示はありません。
Q8 : 『チンアナゴ』が多く展示されていることで知られる水族館はどこ?
すみだ水族館(東京)は、チンアナゴの大規模な展示でよく知られています。砂底からニョキニョキと顔を出す可愛らしい姿が人気で、多数の個体が一度に見られる光景が有名です。新江ノ島水族館も展示していますが、規模や知名度で違いがあります。
Q9 : ジンベエザメが生息している水族館として日本で有名なのはどこ?
沖縄美ら海水族館は、日本でジンベエザメを長期間飼育・展示していることで有名です。同館の大水槽「黒潮の海」では、ジンベエザメが優雅に泳ぐ姿を見ることができます。その他の選択肢も有名な水族館ですが、ジンベエザメの長期飼育施設ではありません。
Q10 : 水族館で飼育されることがある世界最大の淡水魚はどれ?
ピラルクは南米アマゾン川に生息する世界最大級の淡水魚で、最大4.5m近くまで成長することもあります。水族館では淡水の大水槽に展示されることが多く、非常に大きなサイズと、その迫力ある姿で来館者に人気です。アロワナも大型魚ですが、ピラルクほどの大きさにはなりません。
まとめ
いかがでしたか? 今回は水族館 難しいクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は水族館 難しいクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。