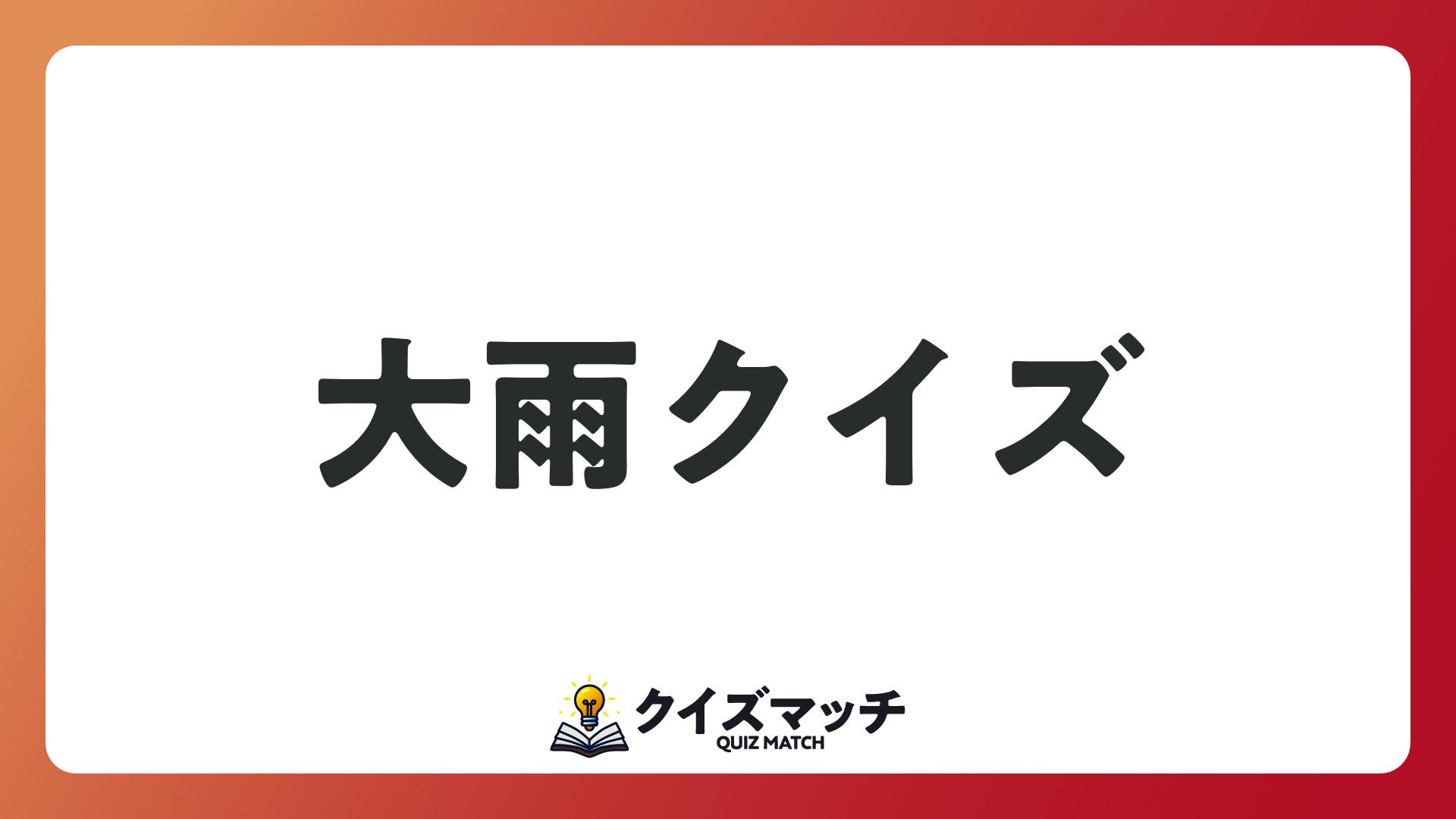大雨は災害につながるさまざまな危険を伴う気象現象です。気象庁が発表する「大雨警報」は、河川の水位上昇や土砂災害などの危険性が高まった際に発表され、避難のきっかけとなります。大雨時には主に土砂災害が発生しやすく、下水道の処理能力を超えた市街地の冠水も懸念されます。また、数十年に一度の異常な大雨が予想される際には「大雨特別警報」が発表されるなど、大雨は非常に危険な状況を意味しています。このクイズでは、大雨に関する基礎知識や災害リスクについて学びましょう。
Q1 : 大雨でマンホールのふたが浮き上がる主な理由は?
大雨が降ると大量の雨水が短時間に下水道へ流れ込み、下水管内の水圧が急激に上昇します。このためマンホールのふたが上方向に押し上げられ、時に飛び出してしまうこともあります。強風や地震の影響ではなく、あくまで下水管内の水圧増加が主な原因です。大雨時には道路のマンホールにも注意しましょう。
Q2 : 現在の日本に存在する「大雨注意報」の基準で、発表基準とされる主な要素は?
「大雨注意報」は、災害発生の危険性が高まった時に発表されますが、その基準には「一定時間の降水量」「連続降水量」「土壌雨量指数」などが利用されます。土壌雨量指数は、雨によって地中にたまった水分量を指し、土砂災害の目安になります。強風や気温、日射の強さは基準要素には含まれません。
Q3 : 大雨に関する用語で1時間あたり50mm以上の降水量は、気象庁がどう分類しているか?
気象庁では「1時間に50mm以上80mm未満」の降水量を「非常に激しい雨」と分類しています。50mm程度の降水では滝のように降ると表現され、道路が川のようになる場合やマンホールから水が噴き出すこともある危険な雨量です。これ未満だと「激しい雨」、これを超えると「猛烈な雨」となります。
Q4 : 大雨による急激な川の増水現象のことを何と呼ぶか?
「鉄砲水」とは、短時間に大量の雨が降ることで山間部や渓流などで突然川が増水し、激しい水流が一気に下流へ押し流される現象を指します。非常に危険で、過去には多くの人的被害が出ています。都市型洪水やゲリラ豪雨も水害に関する用語ですが、急激な増水そのものを指すのは「鉄砲水」です。
Q5 : 「大雨特別警報」はどのような時に発表されるか?
「大雨特別警報」は、数十年に一度しかないような異常な大雨が予想される際に発令されます。この警報が出る状況は極めて危険で、重大な災害が発生するおそれが高いため、自治体の避難指示などに従い、できるだけ速やかに安全な場所に避難する必要があります。「特別」と名付く通り、発表頻度は非常に限られます。
Q6 : 梅雨前線が停滞した場合に日本で起こりやすい天候は?
梅雨前線(ばいうぜんせん)が日本付近に停滞すると、湿った空気が流れ込みやすくなり、各地で長期間にわたる大雨が降ることがあります。これは「梅雨末期の大雨」などと呼ばれ、水害や土砂災害の原因になることも多いです。一方、快晴や強風、気温上昇だけが特徴となるわけではありません。
Q7 : 日本の線状降水帯に関する説明として正しいものはどれか?
線状降水帯は、発達した積乱雲が帯状に連なり、同じ場所で長時間にわたり大雨が降る現象です。短時間に非常に多くの雨が降り続くため、洪水や土砂災害の危険が極めて高まります。2020年や2021年にも日本各地でこの現象が観測され、大規模な水害をもたらしています。
Q8 : 大雨の際に避難が推奨される主な理由はどれか?
大雨が降ると短時間で大量の雨水が発生し、都市部では下水道の処理能力を超えて水があふれ、市街地の冠水や浸水が起きる場合があります。そのため、危険な場所や危険が増す時間帯には避難が推奨されます。土砂災害や河川の氾濫も重なり、人的被害を防ぐ事前対応が重要です。
Q9 : 大雨により発生しやすい災害として正しいものはどれか?
大雨が原因で発生しやすくなる災害は主に「土砂災害」です。これは地中に水がしみこみ、斜面の土が緩むことで崖崩れや地すべり、土石流などが起こるためです。雪崩は主に雪が原因で、山火事や竜巻は主に乾燥や強風が関連します。大雨時は「土砂災害警戒情報」が出ることもあるため注意が必要です。
Q10 : 日本の気象庁が発表する「大雨警報」が発令される主な理由はどれか?
大雨警報は、降雨による河川の水位上昇や土砂災害などの危険性が高まる際に、気象庁が発表する警報です。大雨によって河川の水位が著しく上昇したり、氾濫の恐れが増すことで、人的・物的被害の拡大を防ぐための重要な予報の一つであり、一般市民への注意喚起や避難のきっかけとなります。
まとめ
いかがでしたか? 今回は大雨クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は大雨クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。