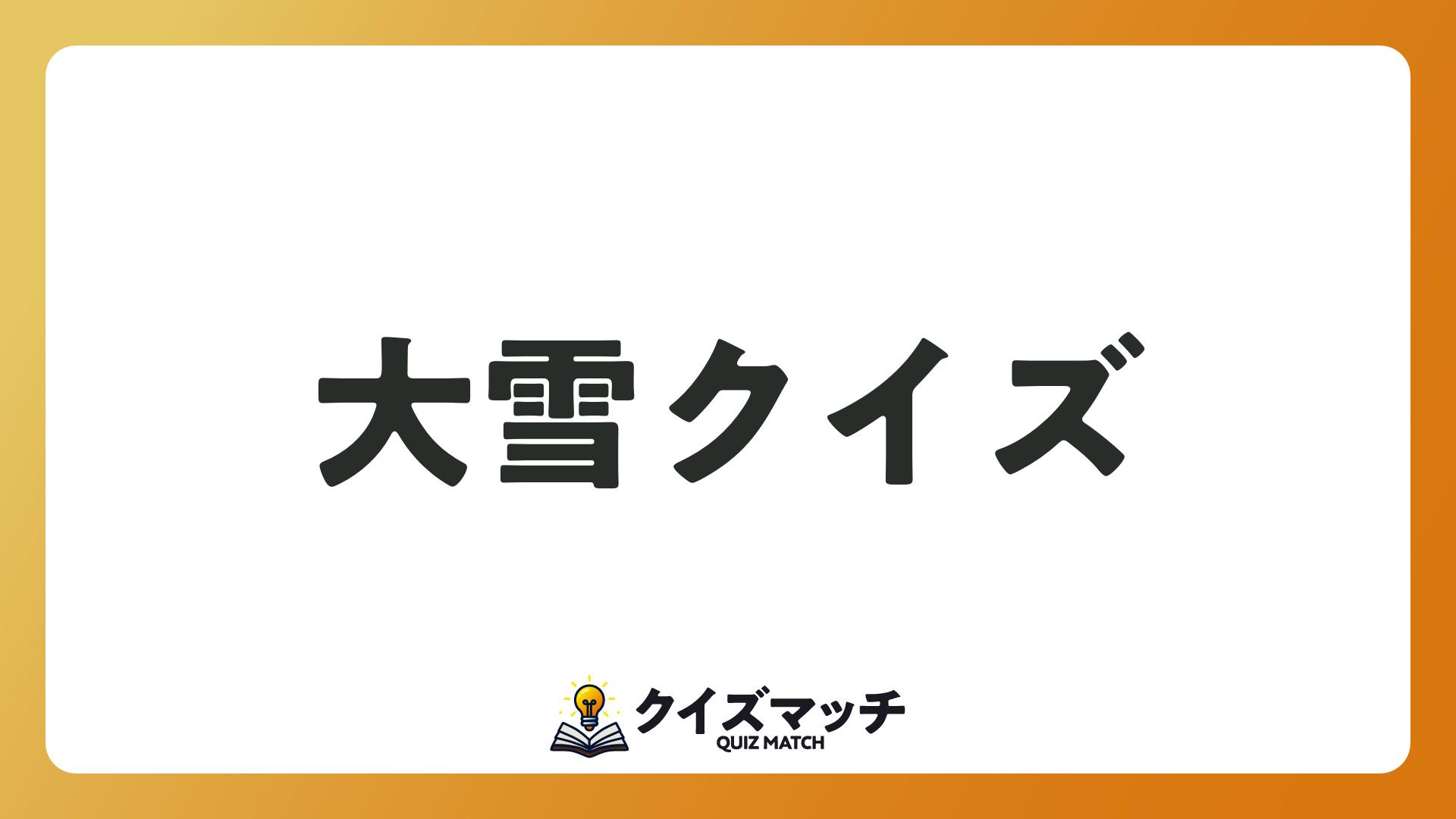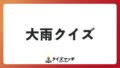二十四節気の一つである「大雪」は、雪が激しく降り始める冬の本番を示す重要な季節の変わり目です。この時期の気象変化は生活に大きな影響を及ぼすため、日本では古くから「大雪」に関する知識や地域の特性を大切にしてきました。この記事では、「大雪」に関するさまざまな知識を盛り込んだクイズを10問ご紹介します。雪国ならではの伝統や気象情報の基準、さらには冬の食材の話題など、「大雪」に纏わる興味深い事柄を学んでいただけます。ぜひ、雪の季節を彩る「大雪」について、一緒に知識を深めていきましょう。
Q1 : 気象庁が発表する「大雪警報」で警戒を呼びかける主な理由はどれですか?
「大雪警報」では、主に交通機関の乱れについて強く警戒が呼びかけられます。積雪や吹雪により道路や鉄道、飛行機などあらゆる交通インフラが麻痺したり、スリップ事故や立ち往生が多発するため、十分な注意と早めの備えが求められています。
Q2 : 日本で一番積雪量が多い都市として知られるのはどこですか?
青森市は、世界有数の豪雪都市として知られています。特に冬季には市街地で数メートルもの積雪が観測されることもあり、幹線道路や生活インフラの整備に積雪対策が不可欠です。気象庁の統計でもしばしば積雪量日本一を記録しています。
Q3 : 「大雪」の時期、東北地方の伝統的な保存食として作られるものは何ですか?
「大雪」から真冬にかけて、寒さを利用して漬物づくりが最盛期を迎えます。秋に収穫した野菜を長期保存するため、各家庭で漬物が盛んに仕込まれる伝統があります。特に東北地方では多くの種類の漬物を冬の保存食として作ります。
Q4 : 気象庁による「大雪」の基準として、積雪何cm以上を警報とすることが多いですか?(地域によって基準は異なります)
気象庁では積雪30cm以上を「大雪」として警報が発表されることが多いです。しかし、この基準は地域やその土地の雪への慣れ具合によって異なりますので、雪に強い地域では基準が高くなることもあります。
Q5 : 「大雪」の頃に旬を迎える魚として適切なのはどれですか?
「大雪」の頃には、ブリが脂がのって旬を迎えます。冬の日本海側ではブリ漁が盛んになり、「寒ブリ」として高級食材として扱われます。刺身はもちろん、照り焼きやぶりしゃぶなど、多彩な料理で楽しまれます。
Q6 : 「大雪」という漢字の意味として正しい解釈はどれですか?
「大雪」は「大いに雪が降る」という意味で、「雪の結晶が大きい」とか「雪が解けて大水になる」といった意味ではありません。文字通り、雪そのものが大量に降る季節を指しています。
Q7 : 「大雪」と対をなす、より早い時期に訪れる二十四節気は何ですか?
二十四節気の「小雪(しょうせつ)」は、「大雪」と対をなし、より早い時期に訪れます。小雪は大雪の前、おおよそ11月下旬を指し、雪がまだ少しずつ降り始める頃とされています。
Q8 : 雪が多く降ることを指す「大雪」ですが、これと関係が深い山岳地帯として有名な場所はどこですか?
日本の立山連峰(たてやまれんぽう)は、日本有数の豪雪地帯で、冬の大雪の象徴的な地域としてよく知られています。特に立山黒部アルペンルート沿いは、積雪量が多く、雪の大谷(巨大な雪壁)など冬の観光名所としても有名です。
Q9 : 「大雪」の期間は、おおよそどのくらい続きますか?
二十四節気の一つ「大雪」の期間は、おおよそ15日間続きます。これは一つの節気が約15日間で構成されているためです。「大雪」は「小雪」と「冬至」の間に位置しており、暦の上では雪が激しく降る冬の本番が始まる時季を表しています。
Q10 : 二十四節気の一つである「大雪」が始まるのは、通常どの月ですか?
大雪は、日本の二十四節気の一つで、例年グレゴリオ暦(新暦)で12月7日頃から始まります。この時期は、雪が激しく降り始める季節として古来から認識されており、「大いに雪が降る」という意味が文字通りこめられています。伝統的な暦をもとにした季節の移り変わりを知る手がかりになります。
まとめ
いかがでしたか? 今回は大雪クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は大雪クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。