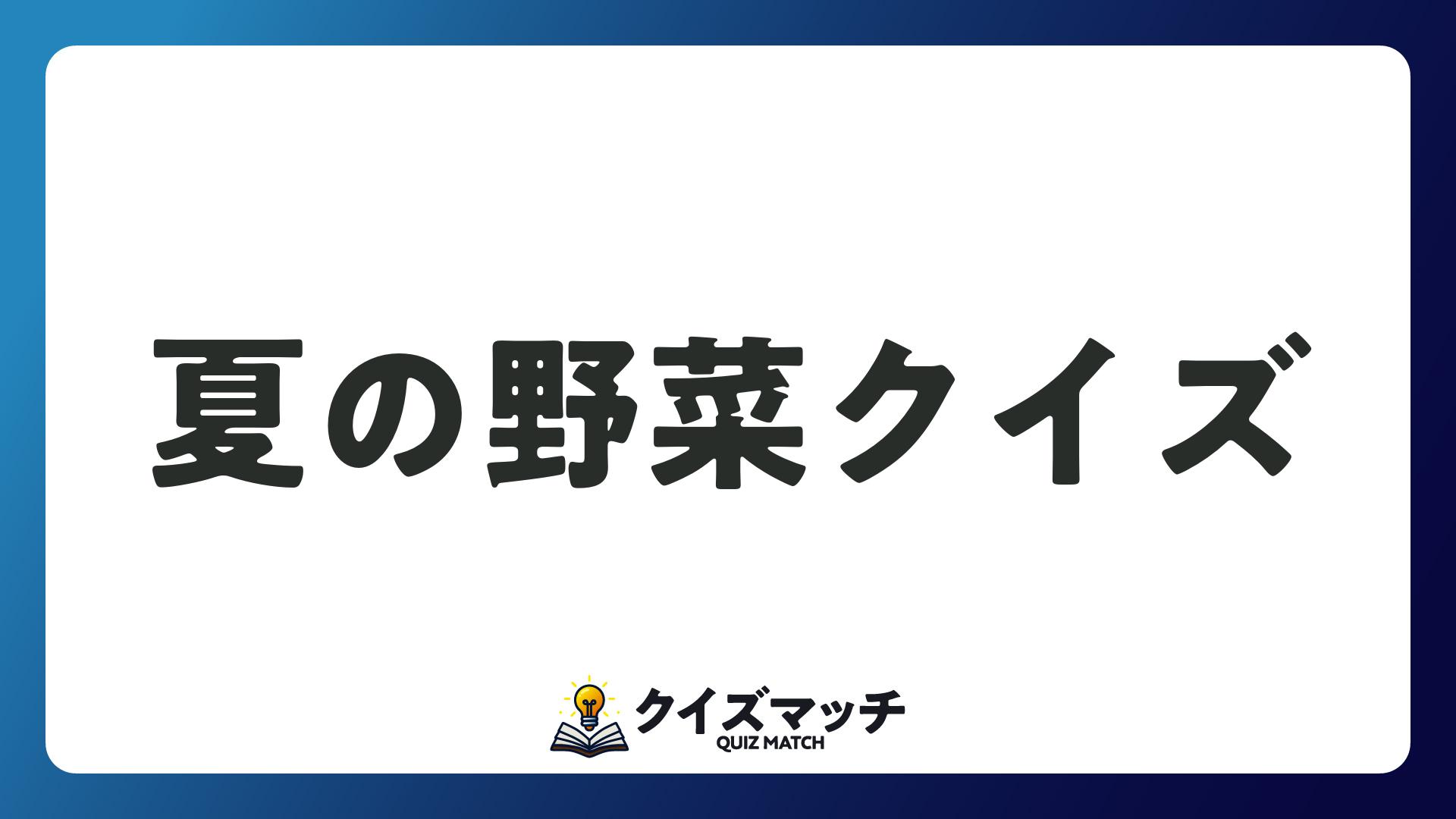暑い夏の季節到来に合わせ、今回は「夏の野菜クイズ」をお届けします。日本の夏を代表する野菜から、珍しい品種まで、全10問のクイズを用意しました。トマトやナス、きゅうりなど馴染み深い夏野菜はもちろん、ピーマンの辛味仲間や、かぼちゃの花まで、夏ならではの食材を徹底的に取り上げています。夏野菜に詳しい方も、そうでない方も、楽しみながら新しい発見ができるはずです。夏を感じながら、クイズに挑戦してみてください。
Q1 : 夏野菜のオクラに多く含まれる、粘り成分の主な特徴は何?
オクラの粘り成分は水溶性食物繊維が豊富なことから生じます。この食物繊維はネバネバしており、腸の健康維持、血糖値の上昇抑制、コレステロールの吸収抑制などの効果が期待できます。香りや甘味、辛味の点では強い特徴はなく、オクラの最大の特徴はその粘りと健康効果です。
Q2 : 夏野菜の代表格で、ビタミンCが豊富な赤い実をつける野菜はどれ?
トマトはビタミンCが豊富な夏野菜で、赤い実が特徴です。サラダや料理の彩りにもよく利用されます。ナスやモロヘイヤ、ピーマンも夏に旬を迎える野菜ですが、赤くなるのはトマトとピーマン(完熟時)のみで、日常的に赤い実といえばトマトです。
Q3 : 夏野菜・ゴーヤの正式な和名はどれ?
ゴーヤの正式な和名は「苦瓜(にがうり)」です。独特の苦味があることからこの名で呼ばれています。沖縄料理の「ゴーヤチャンプルー」などでよく使われる野菜です。みょうが、しそは香味野菜で、へちまは沖縄などで食用にもされますが、ゴーヤの正式な呼び名は苦瓜です。
Q4 : トマトの中で日本で特に夏場に多く出回り、比較的小さい品種名はどれ?
プチトマトは、直径20mm程度の小型のトマトで、夏に多く出回ります。サラダやお弁当の彩りとしても人気です。ミディトマトは中間サイズ、大玉トマトは大きなもの、黒トマトは珍しい品種ですが、今パンとして出回る数はプチトマトが多いです。
Q5 : 夏が旬のきゅうり。日本で一人あたり年間消費量トップの都道府県はどこ?
埼玉県はきゅうりの一人あたり年間消費量が全国トップクラスです。県内には生産地が多く、新鮮なきゅうりが手に入りやすい環境も影響しています。北海道や千葉県、宮崎県も野菜生産が盛んな地域ですが、きゅうりの消費量で見ると埼玉県が上回っています。
Q6 : 夏野菜で、実だけでなく花も食べられることで知られるのはどれ?
かぼちゃは、実だけでなく花も食材として利用されます。特にズッキーニの花(かぼちゃの仲間)はイタリア料理やメキシコ料理などで詰め物をして使われることもあります。他の選択肢のとうもろこし、枝豆、空心菜は主に実や葉を食べ、花は一般的に食用にされていません。
Q7 : ピーマンと同じ仲間で、辛味のある野菜はどれ?
ハバネロはピーマンやパプリカと同じナス科の植物ですが、非常に強い辛味を持っているのが特徴です。パプリカは甘みが強く、ししとうは時折辛い実もありますが基本的には辛くありません。ズッキーニはウリ科の野菜で辛味はありません。このように、ハバネロは辛味のあるナス科野菜の代表格です。
Q8 : 夏に旬を迎えるなすの仲間で、長くて紫色なのはどれ?
長なすは、形が細長くて紫色が特徴のなすの仲間で、夏に旬を迎えます。煮物や焼きナス、炒め物など様々な料理に使われます。他のなすも夏が旬ですが、賀茂なすや丸なすは丸い形が特徴、水なすは主に浅漬けに活用される品種です。地域によって呼び名や品種も異なりますが、長なすはその形から分かりやすく区別されます。
Q9 : 夏野菜を使った料理として正しいものはどれ?
ラタトゥイユは、フランス南部発祥の夏野菜をふんだんに使った煮込み料理です。ナス、ズッキーニ、トマト、ピーマンなど夏が旬の野菜がメインです。他の選択肢であるおでん、鍋焼きうどん、おしるこは主に冬季や寒い時期によく食べられる料理で、夏野菜が主役となることはほとんどありません。
Q10 : 次のうち日本で夏に旬を迎える野菜はどれ?
トマトは夏に旬を迎える代表的な野菜です。日本では、温暖な気候の夏に多くのトマトが収穫され、味や栄養価が最も高まります。一方、大根やごぼうは冬が旬、白菜は主に冬から春にかけて旬を迎えるため、夏にはあまり収穫されません。夏野菜といえば、トマトやナス、きゅうり、ピーマンなどが定番です。
まとめ
いかがでしたか? 今回は夏の野菜クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は夏の野菜クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。