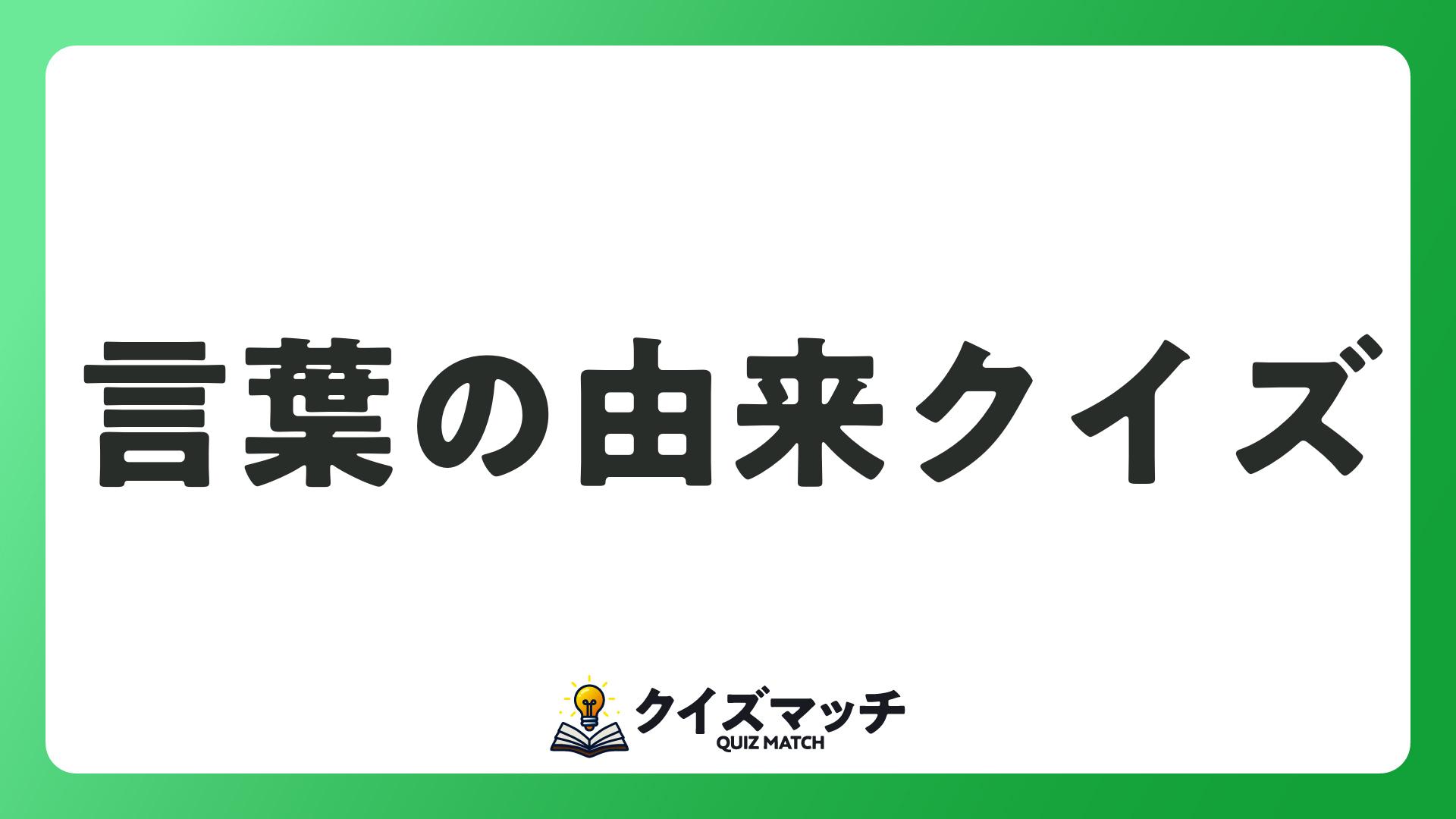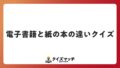日本語には多くの言葉に興味深い由来がありますが、その真意や歴史はよく知られていません。この記事では、日常的に使われている言葉の語源を解き明かす10のクイズを紹介します。サラリーマンの英語由来や、「やぶ医者」の地名由来、「すいません」の意味など、言葉の生い立ちを探ることで、日本語のユニークな文化的背景を垣間見ることができるでしょう。言葉の秘密に迫る、興味深い一読をお楽しみください。
Q1 : 「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」ということわざの『袈裟』は何を指す?
「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」の『袈裟』は僧侶の着る衣服(肩からかける法衣)を指します。本来は8世紀の中国仏教伝来とともに日本に伝わりました。転じてあるものが憎いと、それに関係するもの全てを嫌う心理を表す言葉です。
Q2 : 「糊口(ここう)をしのぐ」の『糊』は何を意味する?
「糊口(ここう)」は「糊(のり=米や穀物で作る薄い粥)」と「口」を合わせ、最低限の食事でなんとか食いつなぐという意味です。『しのぐ』は『忍ぶ』の意味で、日々の食に困窮した暮らしを示します。
Q3 : 「おとしだま(お年玉)」の語源はどこから来ている?
「お年玉」は正月に歳神(としがみ)への供え物の餅(鏡餅)を家長が家族に分け与える習慣が語源です。やがてこれが贈り物全般(特にお金)へと変化しました。「玉」は丸い餅(魂や宝玉の象徴)に由来しています。
Q4 : 「役不足」という言葉の本来の意味は?
「役不足」は本来「自分の才能・能力に対して役目が軽すぎて物足りない」という意味です。しかし現代では「自分の能力を超えた役目を与えられる」という誤用が多くされています。正しい使い方は「彼にこの役は役不足」と、もっと重要な役を与えるべきという意味です。
Q5 : 「たぬき寝入り」の『たぬき』はなぜ使われている?
「狸寝入り」は狸が危険時に死んだふりや寝たふりをする、という民間伝承に基づいています。昔話や説話に狸が化ける・騙す動物として登場し、寝ているふりをすることも狸にたとえられました。実際に狸が寝たふりをするかは不明ですが、日本の動物文化に根付いた表現です。
Q6 : 「晴れ舞台」の『舞台』は元々どの分野の言葉?
「晴れ舞台」の『舞台』は伝統芸能、特に歌舞伎や能の世界で使われた言葉で、舞台の上に立つこと=人前で披露する、人生の晴れの場という意味で用いられ始めました。晴れ=祝いや特別な意味を持ち、人目を引く場面として定着しました。
Q7 : 「おじゃまします」の由来はどのような意味?
「おじゃまします」は、「お邪魔する」の丁寧形で、もともと「邪魔をする」に「お」をつけて丁寧にした表現です。他人の家など自分の生活圏外の領域に入る=相手の時間や空間を妨害するかもしれない、という遠慮を表しています。
Q8 : 「すいません」という言葉の起源はどれ?
「すいません」は「済みません」が変化した言葉で、「申し訳ない・心苦しい」と自分の気持ちが済まないことを表しています。漢字で「済みません」と書き、現代では謝罪や呼びかけに広く用いられるようになりました。
Q9 : 「やぶ医者」の『やぶ』は何に由来している?
「やぶ医者」の『やぶ』は、兵庫県にあった「矢部村」(現在の宍粟市)出身の医者が評判が悪かったことに由来する説が有力です。一方で藪の中=正体不明・うさんくさい医者という説もありますが、地名由来説が一般的です。
Q10 : 「サラリーマン」という言葉の語源はどこの国語に由来する?
「サラリーマン」の語源は英語の「salaryman」ですが、元は「salary(給料)」+「man(男)」という和製英語です。欧米では「office worker」や「white-collar worker」と呼ばれ、日本独自の言葉です。明治時代以降、サラリー(給料)で生活する職業の人々をまとめて表す必要から生まれました。
まとめ
いかがでしたか? 今回は言葉の由来クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は言葉の由来クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。