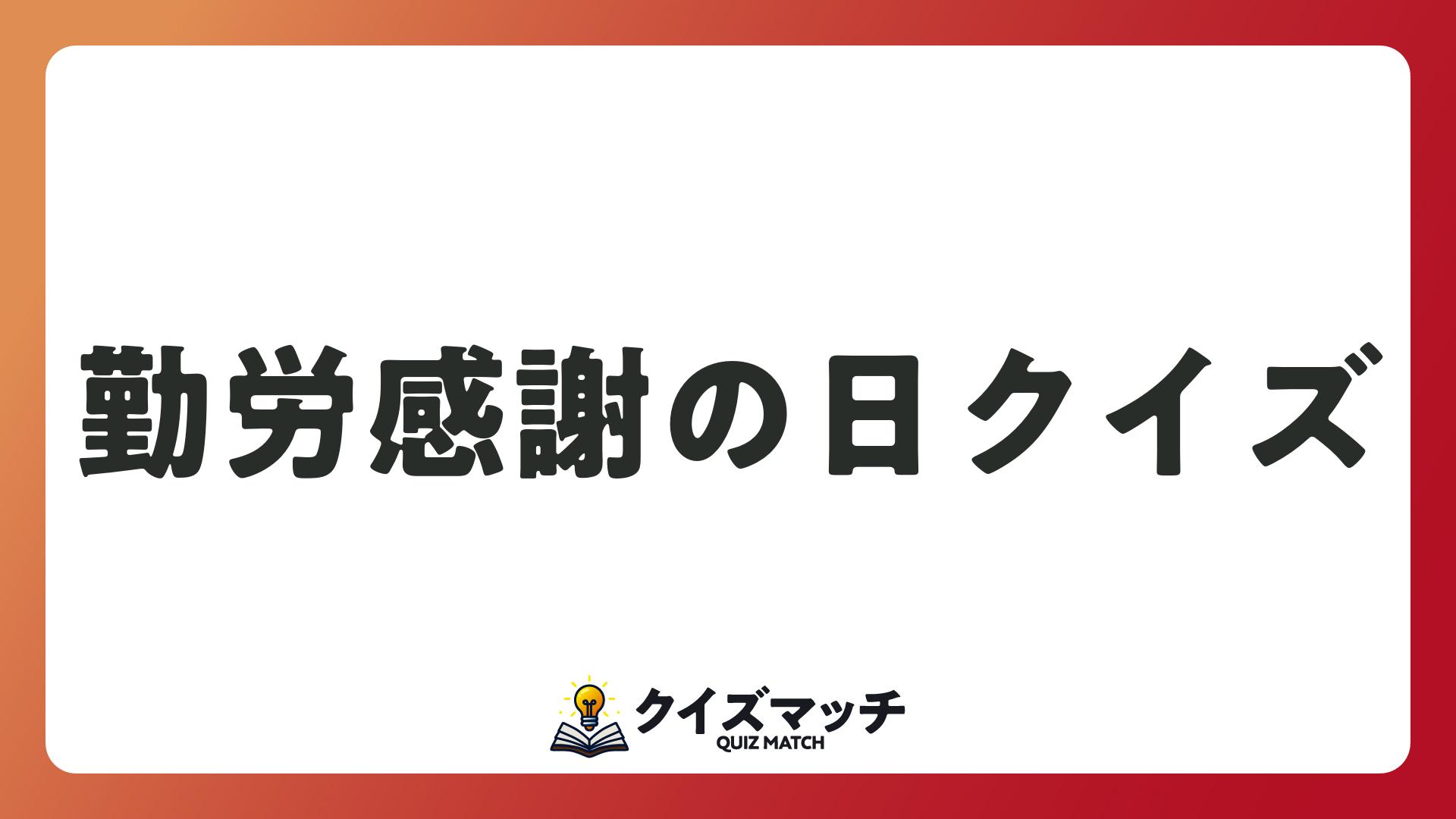勤労感謝の日クイズ
勤労感謝の日は毎年11月23日に祝われる日本の国民の祝日です。この日は、勤労をたっとび、生産を祝い、国民がたがいに感謝しあう日とされています。1948年に現在の「勤労感謝の日」となりましたが、以前は「新嘗祭(にいなめさい)」という行事の日でした。このクイズでは、勤労感謝の日の起源や由来、趣旨や目的など、この特別な日ならではの様々な知識を問います。
Q1 : 勤労感謝の日にちなんで用いられる花はどれ?
勤労感謝の日には、日ごろの感謝を伝える意味でカーネーションが使われることがあります。母の日のカーネーションが有名ですが、働いている人への“ありがとう”の気持ちでも選ばれる花として親しまれています。桜や菊、コスモスはこの日に特別に用いられることはあまりありません。
Q2 : 明治時代・大正時代、勤労感謝の日の前身である新嘗祭が行われていた現場はどこですか?
新嘗祭は宮中(皇居)で天皇が神々に新穀を供え、収穫に感謝する古来からの祭事でした。庶民もこれに倣って各地で収穫を祝う祭りを行ってきました。新嘗祭は国会や民間企業で行われるものではありませんでした。
Q3 : 勤労感謝の日にしばしば行われる学校や地域での活動にふさわしいものは?
勤労感謝の日には、多くの学校や地域で『働く人への感謝の手紙』や『贈り物』を用意する活動が行われています。これは本来の趣旨である勤労者への感謝の気持ちを表すためです。その他の活動もありえますが、この日ならではの行事にはなりません。
Q4 : 国民の祝日に関する法律において、勤労感謝の日を定義している記述は?
祝日法(国民の祝日に関する法律)第2条にて、勤労感謝の日の趣旨は『勤労をたっとび、生産を祝い、国民がたがいに感謝しあう』と明記されています。経済的な意味だけでなく、相互感謝や生産自体も祝うことが趣旨です。
Q5 : 勤労感謝の日に関連して、アメリカの祝日に最も近いとされるのは?
アメリカの『サンクスギビングデー(感謝祭)』は収穫に感謝し、周囲と喜びを分かち合う祝日で、勤労感謝の日が由来にもつながるため『最も近い』とされます。しかし日本の勤労感謝の日は労働への感謝も含まれ、全く同一の由来ではありません。
Q6 : 勤労感謝の日が国民の祝日となったきっかけはどれ?
勤労感謝の日は、1948年に公布・施行された『祝日法』によって新たに定められました。宗教色の強い新嘗祭が時代背景により公的祝日にはそぐわなくなり、社会的な意味づけとして祝日法の中で新たに位置づけられました。
Q7 : 勤労感謝の日の趣旨・目的について正しいものを選んでください。
勤労感謝の日の正式な趣旨は『勤労をたっとび、生産を祝い、国民が互いに感謝しあう』ことです。労働運動や休業が主目的ではありませんし、新米だけを食べるわけでもありません。この祝日は一年の勤労を振り返り、周囲への感謝の気持ちを再認識する日です。
Q8 : 勤労感謝の日が現在の名称に変わったのはどの年?
勤労感謝の日は1948年(昭和23年)に施行された祝日法によって、現在の名称になりました。それ以前は『新嘗祭』として祝われていました。戦後のGHQの意向もあり、宗教的色彩を弱めた名称へと変更され、全国民の祝日として定められました。
Q9 : 勤労感謝の日の起源となった日本古来の行事は何ですか?
勤労感謝の日の起源は古代から行われてきた『新嘗祭』です。新嘗祭は、天皇が五穀の新穀を神に供え、収穫を感謝する重要な祭りでした。1948年の祝日法制定により、宗教色を薄めて『勤労感謝の日』となりました。他の行事は勤労感謝の日の起源ではありません。
Q10 : 勤労感謝の日は毎年何月何日に祝われますか?
勤労感謝の日は毎年11月23日に祝われる日本の国民の祝日です。この日は、勤労をたっとび、生産を祝い、国民がたがいに感謝しあう日とされています。1948年に現在の「勤労感謝の日」となりましたが、以前は「新嘗祭(にいなめさい)」という行事の日でした。11月23日以外の日付では、この祝日が祝われることはありません。
まとめ
いかがでしたか? 今回は勤労感謝の日クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は勤労感謝の日クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。