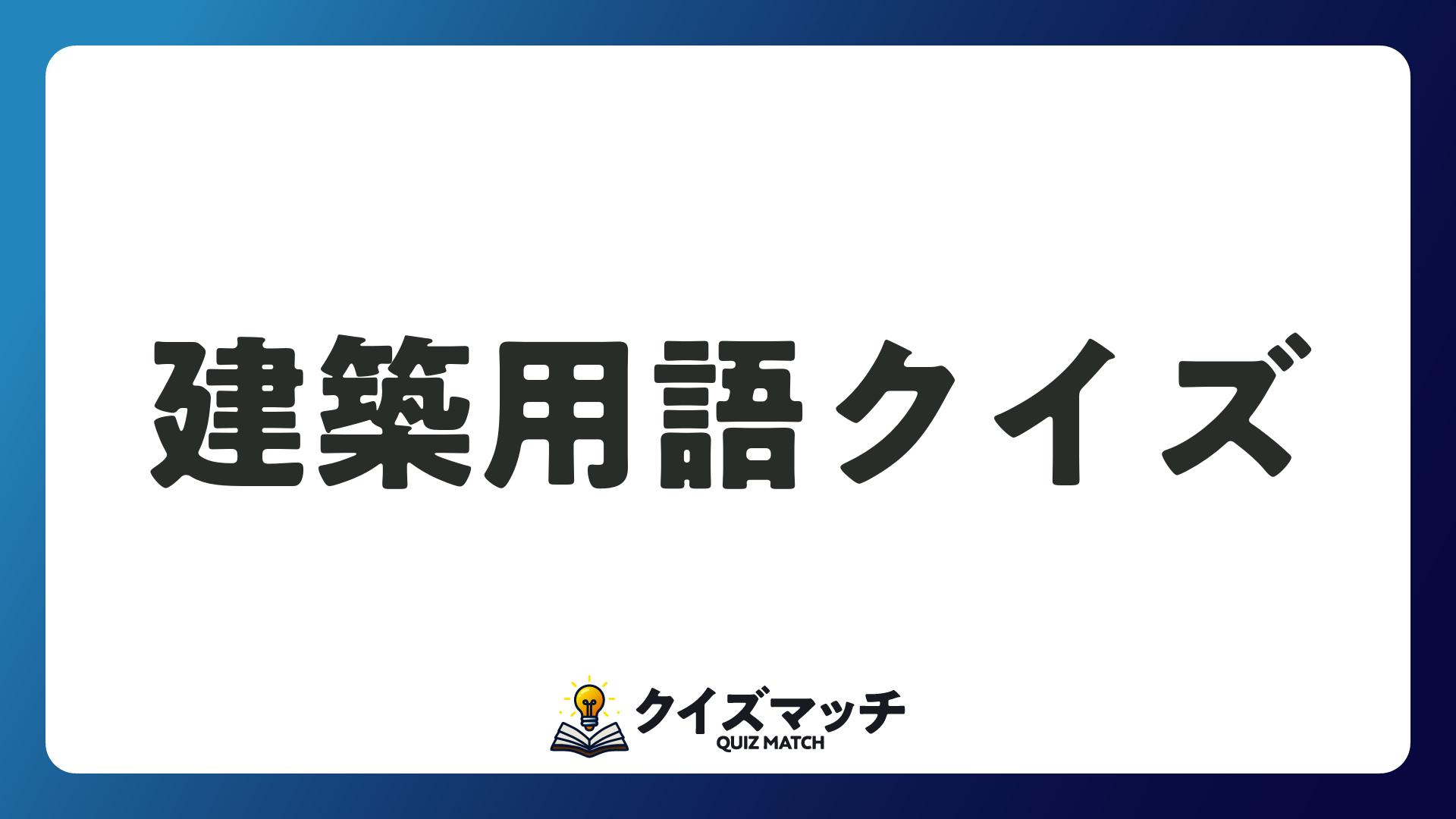建築の専門用語を楽しく学べる「建築用語クイズ」をお届けします。RC造やサッシ、基礎など、建築に関する重要な概念について、10問のクイズに挑戦できます。建築の仕組みや構造、材料といった基礎知識を確認しながら、建築業界のキーワードを楽しく身につけましょう。クイズの中には、見慣れた用語でも意外な正解が待っているかもしれません。建築の世界をさらに深く知りたい方は、ぜひこの機会にチャレンジしてみてください。
Q1 : 「サステナブル建築」の説明として最も適切なのはどれ?
サステナブル建築は、環境の持続可能性を重視し、省エネルギー・省資源・長寿命・環境負荷の低減などの観点から設計・施工・運用される建築のことです。脱炭素、再生可能エネルギーの活用、循環型資材使用などがキーワードとなります。デジタル化や耐震性、伝統様式だけではサステナブルとは言えません。
Q2 : 建築法規で「斜線制限」が定められる目的の一つは?
斜線制限とは、建築物が一定の高さを超えないように「斜線」を設定して制限し、建築物の採光や日照、通風、景観などを確保したり、道路や隣地への圧迫感を軽減したりするために設けられた法規制です。主に建築基準法に基づき用途地域ごとに設定されます。
Q3 : 外壁に施工される「サイディング」の主な機能は何?
サイディングは建物外壁や内壁に張る板状の外装材で、主な機能は建物の美観向上(装飾)と外部からの風雨や衝撃などから構造体を保護することです。近年は耐久性や軽量性、防火性にも配慮されているものが多く使われていますが、断熱や吸音などは主機能ではありません。
Q4 : 建築において「ALCパネル」とは主にどんな材質で作られている?
ALCパネルはAutoclaved Lightweight aerated Concrete(オートクレーブ養生軽量気泡コンクリート)の略です。内部に気泡を多く含んだ軽量のコンクリートで、断熱性・耐火性・耐久性などに優れ、主に外壁・間仕切りなどに用いられています。他の選択肢は構成材料が異なります。
Q5 : 建築設計図面などで「S」と略される建築構造はどれ?
「S」は「Steel(鉄骨造)」を表しており、鋼材を主な構造体として建物を造っている建築物の略称です。日本では構造種別記号として「W:木造」「RC:鉄筋コンクリート造」「S:鉄骨造」「SRC:鉄骨鉄筋コンクリート造」などが使われます。
Q6 : 建物の荷重を地盤に伝えるために設けられる下部構造を何と呼ぶ?
基礎(きそ)は建物の最下部構造で、建物自体の重さや積載荷重を地盤に伝える役割を果たす極めて重要な部位です。一般に直接基礎(べた基礎、布基礎)と杭基礎などがあります。柱は垂直方向の支持材、梁は水平方向の支持材、土台は基礎と柱の間にある部材です。
Q7 : 建築や土木工事で、地面を掘ることを表す用語は?
掘削(くっさく)は、地面や岩盤などを掘る作業全般を指す建築・土木用語です。基礎工事などで行われます。埋戻しは掘った穴を土で埋め戻す作業、盛土は土を盛ること、根切りは構造物を設置するために基礎部分の土を掘る特定の作業で、掘削の一部と言えますが、広義では掘削が適切です。
Q8 : 開口部に取り付け、室内外の遮音や断熱、気密などを高めるために使う部材は?
開口部に取り付ける部材のなかで、特にサッシは窓や扉などの枠に使用するアルミニウムや樹脂製の枠材で、ガラスをはめ込み、断熱・気密・遮音・水密などの性能を向上させる役割を持ちます。パネルは広義の板材、鴨居は引き戸の上枠、束石は基礎部材で全く別の用途です。
Q9 : 建築物の敷地面積に対する建築面積の割合を表す用語は?
建蔽率(けんぺいりつ)は、敷地面積に対する建築面積(建物が敷地に占める水平投影面積)の割合を示す用語です。建築基準法などにより、地域ごとに最大値が定められており、都市計画等で重要な意味を持つ指標です。容積率は延床面積との比ですし、階高は1階ごとの高さです。用途地域は土地の利用目的を定める区分です。
Q10 : 「RC造」はどのような構造材で作られた建築物のことを指す?
RC造は「Reinforced Concrete(鉄筋コンクリート)」の略で、鉄筋とコンクリートを組み合わせた構造材を用いた建築のことを指します。鉄筋の引張強度とコンクリートの圧縮強度を活かして強固な構造を作れるため、住宅や学校、マンションなど幅広く用いられます。他の選択肢と混同しやすいですが、鉄骨造は鋼材のみ、木造は木材、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)はRC構造に鉄骨も加えたものです。
まとめ
いかがでしたか? 今回は建築用語クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は建築用語クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。