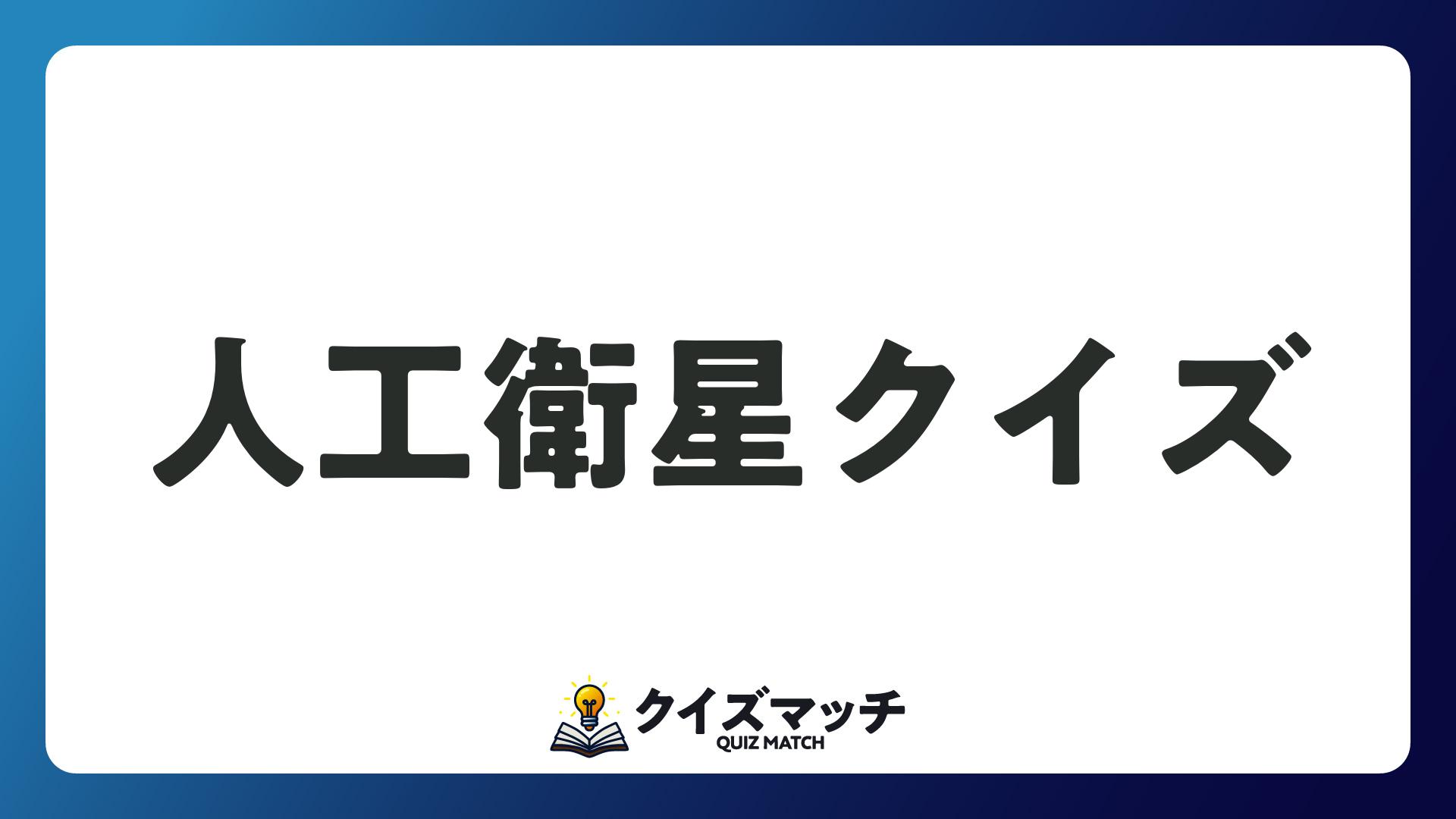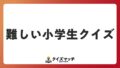地球初の人工衛星「スプートニク1号」を打ち上げたのはソ連でした。以来、宇宙開発競争が本格化し、NASAの設立やアポロ計画など、多くの重要な出来事につながっています。このようなフェーズを経て今日の宇宙開発が進んでいますが、人工衛星の種類や目的は多岐にわたっています。本クイズでは、気象観測衛星や測位衛星、天文衛星といった様々な人工衛星に関する知識を問います。宇宙開発の歴史と最新動向を学べる良い機会となるでしょう。
Q1 : 一般的な低軌道(LEO)を周回する地球観測衛星の公転周期はどれくらい?
低軌道(LEO)の高度(約200~2,000km)を周回する人工衛星は、地球をおよそ90分ほどで一周します。このため、1日に16回ほど地球を周回し、観測や通信など幅広い目的で活用されています。高軌道の衛星ほど周期は長くなります。
Q2 : 人工衛星が軌道上で長期間運用できるよう、必要とされる運動は何と呼ばれますか?
人工衛星を正しい向きに保つための技術を「姿勢制御」と呼びます。ソーラーパネルの発電効率や観測機器の精度を維持するために不可欠です。摂動は外的要因による微小変化、軌道投入はロケット分離後の運動、分離はロケット等からの切り離し操作です。
Q3 : 2020年に日本で開発されたX線天文衛星の名前は?
「ひとみ」は日本のX線天文衛星で、2016年2月に打ち上げられましたが、トラブルにより運用終了となりました。「あらせ」は宇宙線観測衛星、「ひまわり」「だいち」は別分野の人工衛星です。
Q4 : 欧州の衛星測位システムの名称は何ですか?
欧州連合(EU)が進めている独自の衛星測位システムは「Galileo(ガリレオ)」です。アメリカのGPS、ロシアのGLONASS、中国の北斗に並ぶ世界的な測位システムであり、グローバルにサービスを展開しています。
Q5 : 静止衛星の軌道高度はおよそ何kmでしょうか?
静止衛星(静止軌道衛星)は赤道上空約35,786km(約36,000km)にある軌道に配置されます。この高度で地球の自転と同じ周期で回るため、地上の同じ地点の真上に常に位置し、通信や気象観測に多用されています。
Q6 : GPSに対応する日本独自の衛星測位システムの名称は?
日本が展開している衛星測位システムの名称は「みちびき(準天頂衛星システム:QZSS)」です。GPSと互換性があり、2つを組み合わせることでより精度の高い位置情報が取得できます。だいち、ひまわり、いぶきはそれぞれ異なる衛星です。
Q7 : 気象観測に特化した日本の静止気象衛星シリーズ名は何ですか?
「ひまわり」は日本の静止気象衛星シリーズ名で、主に台風や雲の監視など気象観測を目的としています。現在は「ひまわり8号」や「ひまわり9号」が運用中です。だいちやいぶき、みちびきはそれぞれ別の目的の人工衛星です。
Q8 : 日本初の人工衛星「おおすみ」が打ち上げられたのは何年ですか?
日本初の人工衛星「おおすみ」は1970年2月11日にラムダロケットによって打ち上げられました。これにより日本は、アメリカ、ソ連、フランスに次いで、独自のロケットで人工衛星を軌道にのせた4番目の国となっています。
Q9 : 国際宇宙ステーション(ISS)は主にどの高度の軌道に存在していますか?
国際宇宙ステーション(ISS)は地上約400kmの地球低軌道(LEO)にあります。低軌道は地表から約200~2,000kmの範囲で、多くの地球観測衛星や通信衛星が存在します。静止軌道や中軌道はより高い場所で、GPSなど別用途の衛星が使います。
Q10 : 地球初の人工衛星「スプートニク1号」を打ち上げた国はどこですか?
スプートニク1号は1957年10月4日にソビエト連邦(ソ連)によって打ち上げられました。これが人類初の人工衛星であり、この成功によって宇宙開発競争が本格化し、後のアメリカのNASA設立やアポロ計画などにつながりました。アメリカが最初の人工衛星を打ち上げたのはソ連よりも後であり、中国や日本はさらに後になります。
まとめ
いかがでしたか? 今回は人工衛星クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は人工衛星クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。