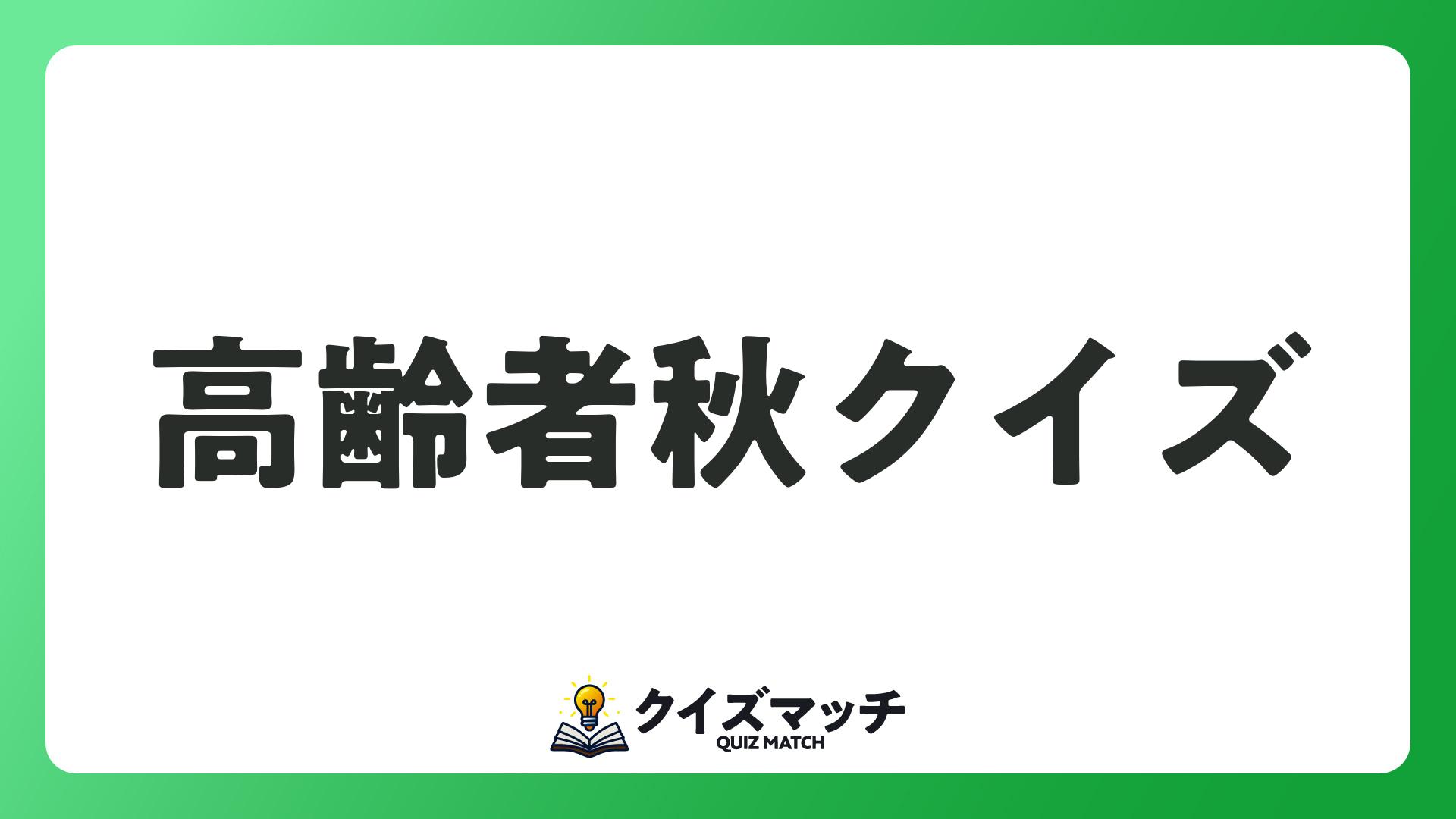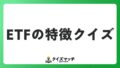秋の訪れとともに、美しい紅葉や実り豊かな自然が日本各地に広がる季節がやってきました。そんな秋ならではの風景や行事、食べ物について、高齢者の方々に楽しんでいただけるよう、10問のクイズをご用意しました。秋の訪れを感じながら、クイズにチャレンジしてみませんか。日本の伝統的な秋の過ごし方を再発見できるはずです。
Q1 : 秋に見られる果物で「柿渋」という染料が作られる植物はどれでしょうか?
柿渋は、カキの渋を利用して作られる自然の染料です。用途は染色、塗料、防水など多岐にわたります。特に市などの伝統的な和紙に柿渋を施し、強度を増す用途で知られています。また、防腐作用があることから、船材や屋根材料の保護に用いられてきました。秋は柿の収穫時期で、そのときに作られるため、秋の風物詩ともいえます。
Q2 : 日本の秋の伝統行事である「十五夜」に関連するものは何でしょうか?
「十五夜」は、旧暦の八月十五日にあたる日で、満月の夜を意味します。この日に行われる伝統行事は「月見」と呼ばれ、秋の収穫に感謝し、月を眺めて美しさを楽しむ行事です。お団子や秋の収穫物を供え、すすきを飾るなど、季節を感じる風習が古くから伝えられています。
Q3 : 秋に見られる天体イベント、流星群の名前は何でしょうか?
オリオン座流星群は、毎年10月中旬から下旬にかけて出現する流星群です。母彗星であるハレー彗星から放出された塵が地球の大気に突入することで発生します。流れ星を見ることができるチャンスであり、多くの人々が夜空を見上げて楽しみにしています。オリオン座付近から放射するように見えるため、この名前がついています。
Q4 : 日本で秋に行われる大きなスポーツイベントは何でしょうか?
国民体育大会、通称「国体」は、日本各地で開催される大きなスポーツイベントで、秋に行われることが多いです。全国のアマチュアスポーツ選手が集まり、競技を行う大会で、陸上競技や水泳など多くの種目が行われます。地域の特色を生かした大会運営が行われるため、スポーツ振興とともに地域活性化にも貢献しています。
Q5 : 秋の七草に含まれない植物はどれでしょうか?
秋の七草は、萩、薄(ススキ)、桔梗、撫子(ナデシコ)、葛、藤袴、女郎花(オミナエシ)です。これらは万葉集の山上憶良の歌に由来しています。花見として知られる春の七草とは異なり、食用ではなく観賞用とされています。一方、ハナミズキは庭木として知られている植物で、秋の七草には含まれません。
Q6 : 秋に収穫される米は何と呼ばれていますか?
新米とは、その年に収穫されたばかりのお米のことを指します。秋は米の収穫期であるため、この時期には特に新米が市場に出回ります。新米は水分を多く含んでいるため、炊いた際にふっくらと仕上がり、独特の香りと甘みがあります。多くの人々にとって、秋に新米を味わう瞬間は一年の楽しみの一つです。
Q7 : 秋分の日はどのような意味を持つ日でしょうか?
秋分の日は、昼と夜の長さがほぼ同じになる日として知られています。この日は日本の国民の祝日として認められており、年によって9月22日から24日の間に設定されます。秋分の日は、自然を敬い、先祖を偲ぶ日とされています。この日を境に、本格的な秋が訪れ、日が短くなっていくのを実感できます。
Q8 : 秋の味覚として親しまれているサンマはどのような魚でしょうか?
サンマは秋を代表する海魚です。脂がのった身と独特の風味が特徴で、日本では焼き魚として親しまれています。特に塩焼きにすると、香ばしい香りが食欲をそそります。産地によっては多くの漁獲量を誇り、秋の食卓には欠かせない存在です。栄養価も優れており、DHAやEPAを豊富に含んでいます。
Q9 : どんぐりは秋になるとよく見かけますが、どの木の実でしょうか?
どんぐりは主にコナラやクヌギといったブナ科の木からなる実です。秋になると地面に落ちているのをよく見かけます。どんぐりはかわいらしい形をしており、自然観察やクラフトの材料としても親しまれています。子供たちにも人気のある素材で、拾ってコレクションにしたり工作に利用することがあります。
Q10 : 日本の秋の風物詩である紅葉狩りはどのようなイベントですか?
紅葉狩りとは、紅葉が美しく色づく季節に山や公園に出かけて、紅葉を楽しむイベントのことです。日本では特に秋の風物詩として親しまれています。紅葉を見ることは、日本で古くからの伝統的な楽しみ方で、景色を堪能しながら季節の移り変わりを感じることができるため、多くの人々に愛されています。
まとめ
いかがでしたか? 今回は高齢者秋クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は高齢者秋クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。