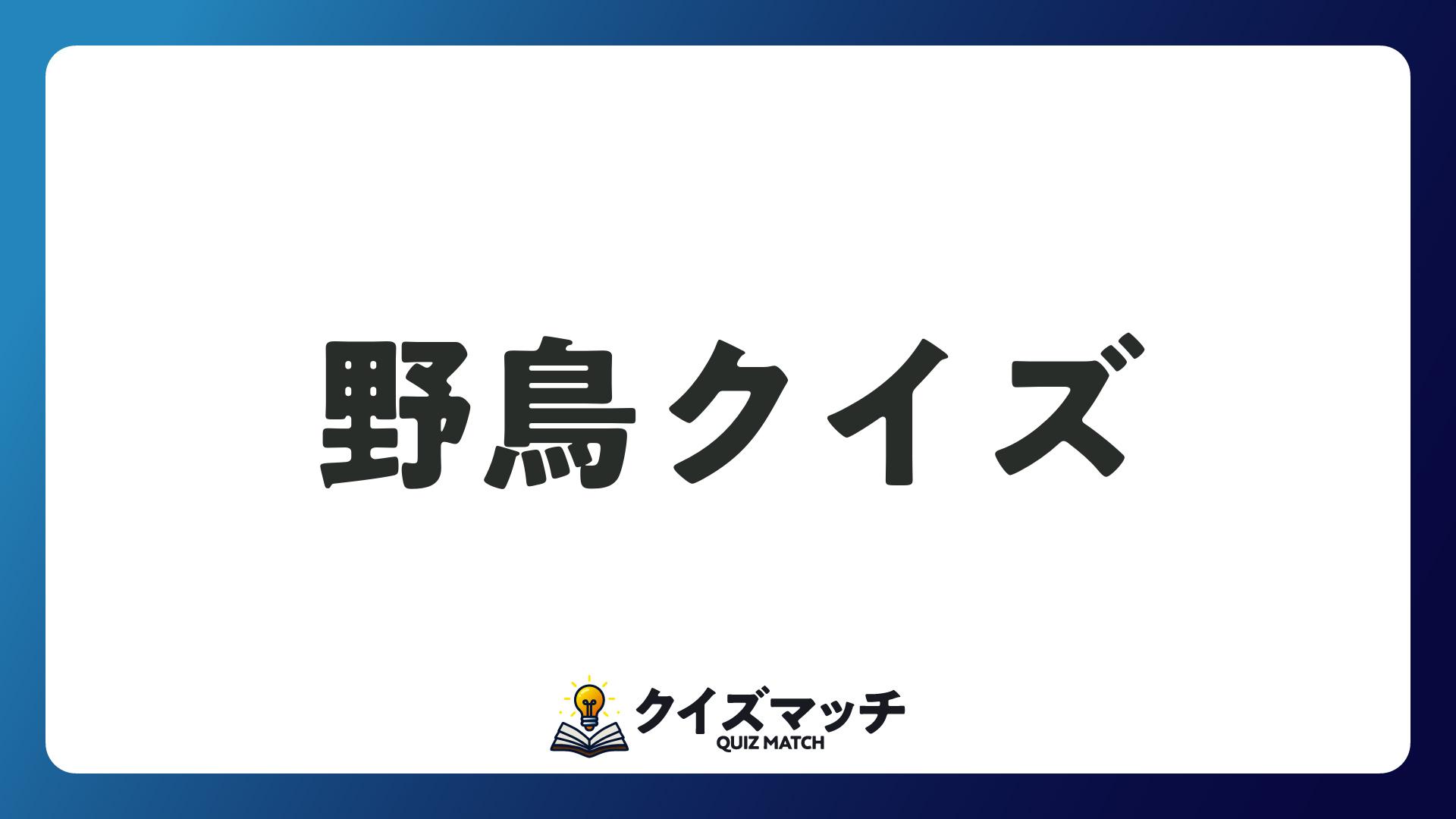野鳥観察を楽しむ人も、これから始めたい人も必見!日本の代表的な野鳥について、実際に見られるその姿や特徴を10問のクイズでご紹介します。キジの美しい姿、ホトトギスの有名な句、冬の訪れを告げるオオハクチョウの仲間など、季節とともに変化する野鳥の世界をお楽しみください。答えはすぐにわかるかもしれませんが、それぞれの鳥の魅力について新たな発見があるはずです。日本の自然を感じながら、ぜひ一緒に野鳥クイズにチャレンジしてみましょう。
Q1 : 「シジュウカラ」や「コゲラ」などの混群を形成することが知られている鳥は?
エナガは主に混群の構成員としてシジュウカラやコゲラと一緒に見られることが多い、小さいながらも見た目が愛らしい鳥です。その小さな体と長い尾が特徴で、いつも群れで行動し、冬になると複数種混合の群れを形成します。樹上を軽やかに移動しながら餌を探し、その様子は自然観察の人気の的です。
Q2 : オスの眉が白く、秋から冬にかけて頭が赤い鳥は?
アトリは冬鳥として日本に渡ってくるスズメ科の鳥で、オスの成鳥は鼻筋から目の上にかけての眉が白色で、頭にかけて赤みがかった色が特徴です。堅い木の実を好んで食べ、落葉広葉樹の林や農耕地に大きな群れで姿を見せます。また、飛び立つ際には独特の群れの動きがあり、その姿は寒い季節に見られる野鳥の一端を感じさせます。
Q3 : 森でよく見かける色鮮やかな青色をした、日本の代表的なカワセミ科の鳥は?
カワセミは「水辺の宝石」とも称される美しい青色と橙色のコントラストが特徴の鳥で、日本全国の水辺に広く生息しています。魚を捕って食べ、川や湖畔でその独特の飛び方と水中へのダイビングを見せてくれます。美しさから観察者も多く、カメラで捉えられた瞬間の美しさは多くの人々に感動を与えます。
Q4 : 冬に渡ってくる「ツグミ」は、古代日本ではどんな鳥として知られていた?
ツグミは古代日本では「食鳥」として知られ、その肉が貴重な蛋白源でした。冬になると北から多くのツグミが日本にやってきて、耕された田畑や林の中でエサを漁ります。その寒さに強い体は地方によっては捕まえて食用とされることもありましたが、今では観察の対象として親しまれています。
Q5 : 「夜鶴」「ヒヨドリ」などと呼ばれ、夜間でも鳴く日本の鳥は?
ヨタカは夕方から夜間にかけて活動することで知られる鳥で、日本全土に分布しています。その名の通り、夜でもよく鳴くことから「夜鶴」という異名を持っています。曇りの日や雨の日は昼間でも鳴くことがあり、虫を主食として飛行しながら捕まえます。木立の中や森の縁でその独特な鳴き声を聞くことができます。
Q6 : 鶯の美しい鳴き声が聞こえる春の到来を象徴する和名は?
鶯(ウグイス)は春の訪れを告げる鳥として「春告鳥」という和名があります。ウグイスの鳴く声は澄んで美しく、日本の風物詩として知られています。主に薮や低木の中に生息し、見つけるのは難しいですが、その澄んだ鳴き声が遠くまで響き渡ります。繁殖期には特に鳴き声が多くなり、ホーホケキョ"と聞こえる声が特徴です。"
Q7 : 留鳥として日本の都市部でも観察される、黒と白の対照的な羽を持つ鳥は?
ハクセキレイは日本全国の都市部から農村にかけて広く見られる小鳥で、特に川や池などの水辺に多く見られます。全体的に白と黒のコントラストがはっきりしているのが特徴で、常に尾を上下に振る仕草が可愛らしいと人気です。人間に対する警戒心が少なく、餌を探して地面を歩く姿をよく目にします。
Q8 : 日本の冬に見られる渡り鳥である『オオハクチョウ』の仲間は?
オオハクチョウは北方で繁殖し、日本には冬に越冬のため移動してきます。ミコハクチョウはオオハクチョウよりもやや小型で、黄色の嘴が特徴です。日本全国の水辺で見られることがあり、その優雅な姿で知られています。群れで行動し、一緒に泳ぎながら生息地の水草や小動物を食べます。
Q9 : ホトトギスが有名な句に登場する日本の俳人は誰でしょうか?
ホトトギスは日本の俳句にしばしば登場する鳥で、正岡子規はこれに因んでその名を選びました。正岡子規の本名は常規で、俳号を「子規」とする際にこの鳥の泣き声を独特な視点で詠んだのが有名です。夏を告げる鳥として、ホトトギスは日本文化に深く根付いています。
Q10 : 日本の国鳥は何ですか?
キジは日本の国鳥として、農村や山地でよく見られる鳥です。雄は美しい緑色の羽を持ち、尾が長く、国内では多くの伝説や文化に関わっています。キジは主に地上で生活し、種子や昆虫を食べる雑食性です。田畑や野原にもよく現れ、人々に親しまれています。
まとめ
いかがでしたか? 今回は野鳥クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は野鳥クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。