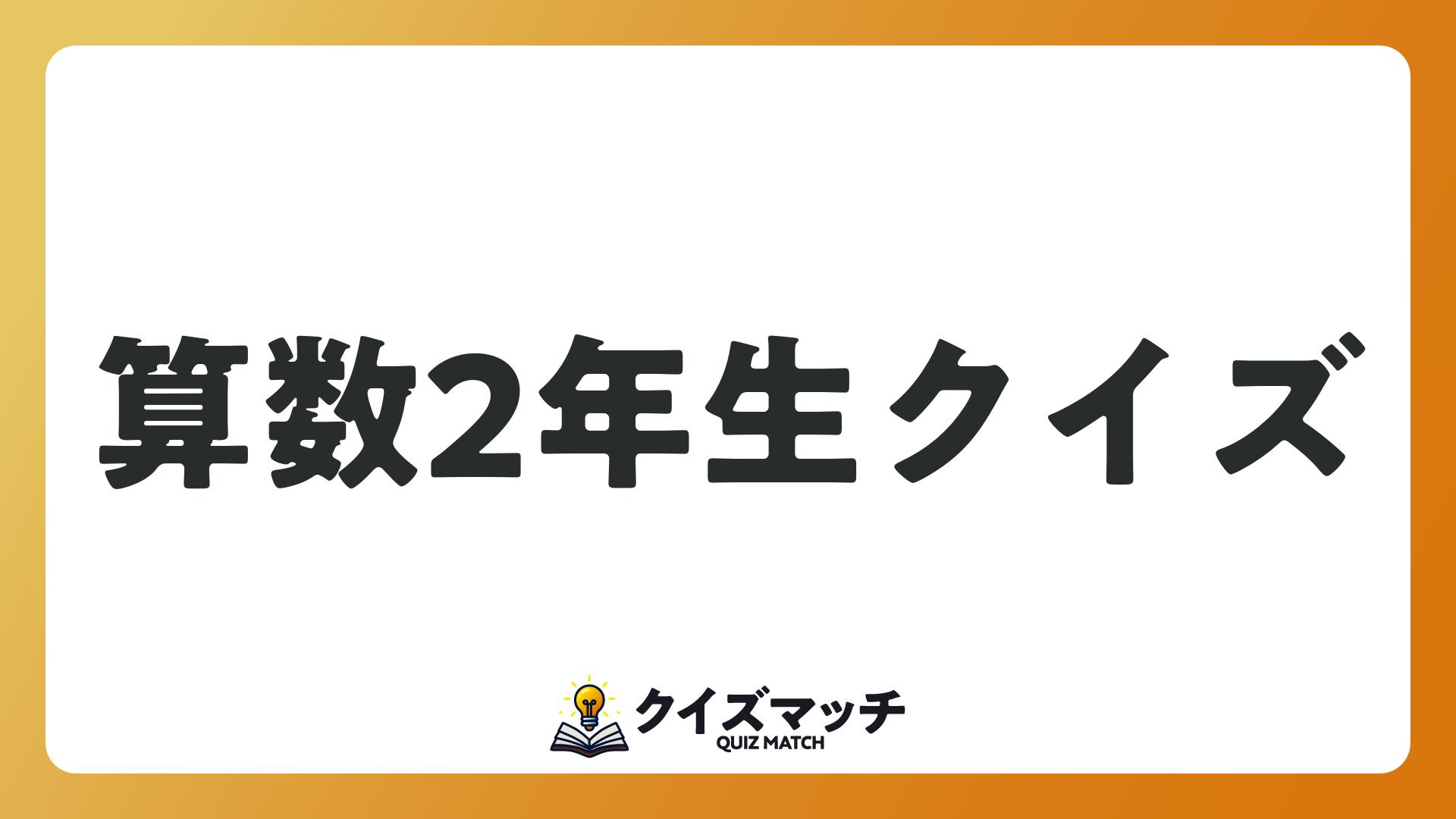小学2年生向けの算数クイズ10問を用意しました。加減乗除の基本的な計算問題から成り立っており、子どもたちの算数の力を確かめるのに最適です。数直線やマス計算を活用しながら、足し算、引き算、掛け算、割り算の基本を楽しく学べるよう工夫しています。クイズに挑戦して、自分の計算力を試してみましょう。正解率を高められるよう、丁寧に解き進めていくことが重要です。計算力の向上とともに、算数の楽しさも感じ取ってもらえれば幸いです。
Q1 : 次の計算の答えはいくつですか? 6 × 5 = ?
6と5を掛け合わせると答えは30になります。これは、6を5回足すことと同じで、6+6+6+6+6=30です。また、掛け算の表で6の段を見ると、5番目がちょうど30になります。掛け算は足し算の連続なので、このように答えを導けます。
Q2 : 次の計算の答えはいくつですか? 13 - 7 = ?
13から7を引くと答えは6になります。数直線においては、13から左へ7進むと6に到達します。筆算で丁寧に解くなら、1の位から順に計算し、上記のような数の引き算を演じることで確認されます。
Q3 : 次の計算の答えはいくつですか? 9 + 8 = ?
9に8を足すと答えは17になります。数直線を利用することで、9から8だけ右へ進むことで17に到達することが確認できます。また、筆算を用いると、1の位から引き続けて9+8=17であり、直接頭の中でその合計を考え出せます。
Q4 : 次の計算の答えはいくつですか? 20 ÷ 5 = ?
20を5で割ると答えは4になります。これを意味するのは、20を5等分したとき、各部分に4が入ることです。掛け算の逆として理解すると、4を5つ掛けた数が20であることが確認できます。つまり、4×5=20なので、20÷5=4です。
Q5 : 次の計算の答えはいくつですか? 5 × 4 = ?
5と4を掛け合わせると答えは20になります。この掛け算は、5を4回足すことと同等です。5+5=10、さらに5+5=10を足して、10+10=20になります。また、掛け算の表を見ても、5の段の4番目が20であることが確認できます。
Q6 : 次の計算の答えはいくつですか? 15 - 5 = ?
15から5を引くと答えは10になります。この計算は、15本の棒から5本の棒を取り除くようなもので、残りは10本となります。また、数直線を使うと、15から左に5だけ進むと10に到達します。筆算を使う場合も同様に15から5を引き、答えはそのまま10です。
Q7 : 次の計算の答えはいくつですか? 12 ÷ 4 = ?
12を4で割ると答えは3になります。割り算は等分に分けることを意味します。12を4つのグループに均等に分けると、各グループには3が入ります。また、掛け算の逆として考えると、何を掛ければ12になるかを考えます。ここで、4×3=12が成り立つため、答えは3です。
Q8 : 次の計算の答えはいくつですか? 7 × 3 = ?
7と3を掛け合わせると答えは21になります。掛け算は足し算の繰り返しで、7を3回足すことと同じです。つまり、7+7+7=21となります。掛け算の表を使っても7の段の3番目が21であることが確認できます。具体的には7+7=14、14+7=21のように計算を進めます。
Q9 : 次の計算の答えはいくつですか? 14 - 6 = ?
14から6を引くと答えは8になります。数直線を使って14から左に6進むことで、8が得られます。また、筆算を使う場合、14を上に、6を下に書き、1の位と10の位から順に引き算をします。まず1の位の4から6を引きますが、引けないので、10を繰り下げて14とし、4+10-6=8と求めます。
Q10 : 次の計算の答えはいくつですか? 18 + 9 = ?
18に9を足すと答えは27になります。数直線を使って18から9だけ右に進むと27になります。また、筆算を使う場合は、縦に18と9を書き、1の位から順に足します。8+9で17、繰り上がった1を10の位の1と足して2、よって答えは27です。
まとめ
いかがでしたか? 今回は算数 2年生クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は算数 2年生クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。