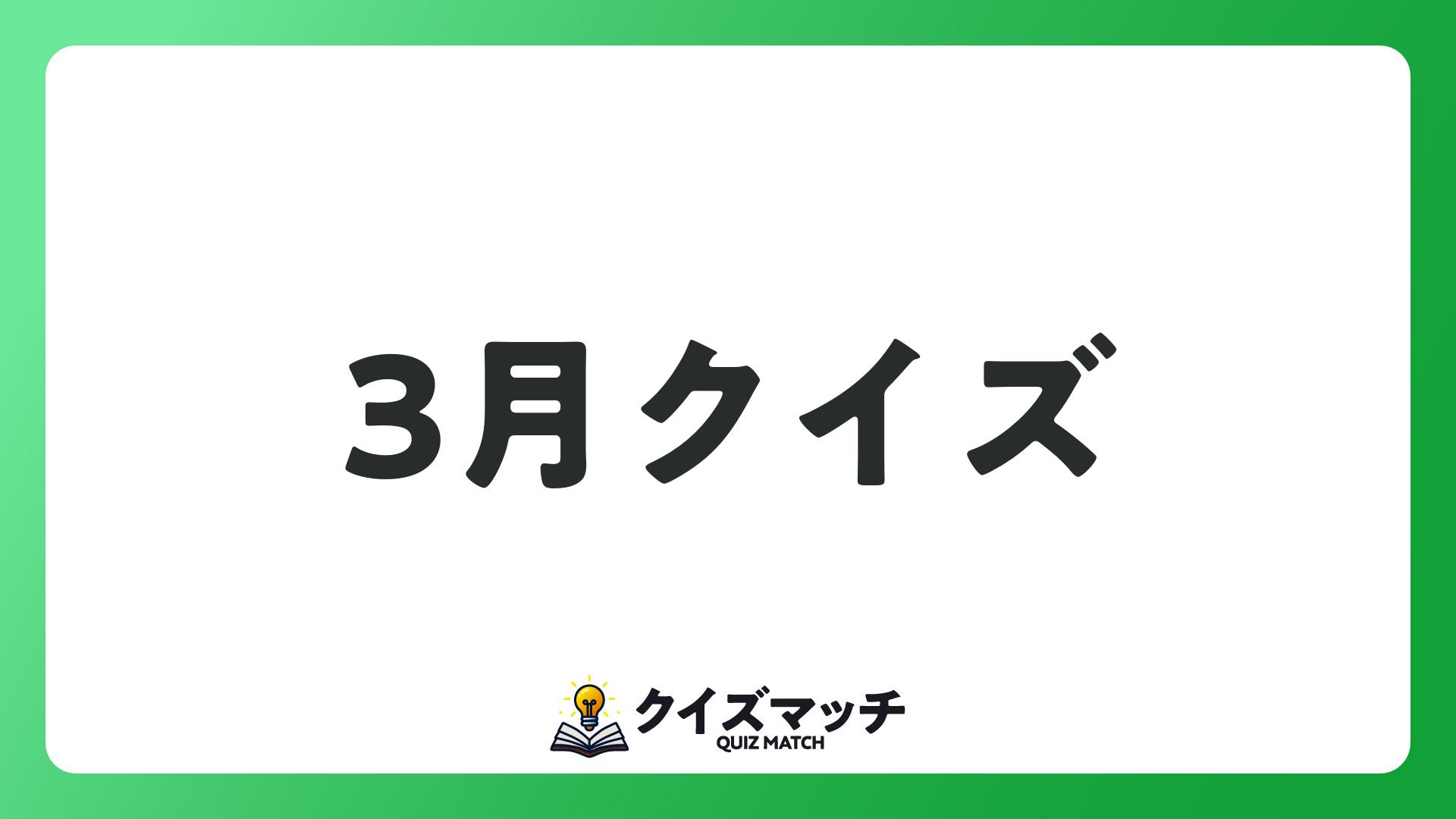3月は、日本の伝統的な季節の移り変わりを感じさせる大切な時期です。この季節には、春分の日をはじめ、ひな祭りやおwater送りなど、様々な行事や習慣が根付いています。日本人の生活や文化とも深く関わる3月のエピソードを、楽しく学べるクイズを10問ご用意しました。日本の歴史や自然との関わりを振り返りながら、3月ならではの魅力を探っていきましょう。
Q1 : 3月4日は、何の日として広く知られているでしょうか?
3月4日は「ミシンの日」として知られています。これは「ミ(3)シ(4)」という語呂合わせから来ており、日本縫製機械工業会によって制定されました。ミシンは衣類や家庭用製品の製造に欠かせない道具であり、この日にちなんで様々なイベントが催されます。ミシンの日は、家庭裁縫や手作り製品に関心を抱く人々にとって特別な日となっています。
Q2 : 日本における3月の祝日である春分の日は、固定日ではなくどのように決まるでしょうか?
春分の日は、昼と夜の長さがほぼ等しくなる日として知られていますが、これは太陽が赤道を通過する瞬間を基準に、毎年微妙に変動します。そのため、春分の日は必ずしも固定された日にちではなく、毎年3月20日頃に設定されます。国立天文台が年ごとの計算結果をもとに発表し、それに基づいて祝日が決定されます。この日は、自然をたたえ、生物をいつくしむ日としての意義があります。
Q3 : 春分の日近くに日本で行われるお祭り「太宰府梅祭り」はどの県で開催されるでしょうか?
太宰府梅祭りは、福岡県の太宰府市で毎年春分の日付近に開催されるお祭りで、梅の花の美しさを祝うことが主目的です。太宰府天満宮は梅の名所としても有名で、境内に咲く美しい梅の花々が観光客を魅了します。梅祭りは花の観賞だけでなく、雅楽や伝統芸能の披露、屋台の出店などさまざまな催し物があり、地域の文化や自然を楽しむ機会となっています。
Q4 : 3月の英語名は何に由来するでしょうか?
3月の英語名「March」は、ローマ神話の戦いの神「マルス(Mars)」に由来しています。マルスは農業の神としても知られ、戦いと平和の両面を兼ね備えた神としてローマ人に崇拝されていました。また、ローマ暦では3月が新年の始まりであり、農作業の準備が始まる時期であったため、マルスにちなんでこの月名が付けられました。
Q5 : 3月に日本で行われる伝統的な祭り「お水送り」はどこの県で行われるでしょうか?
お水送りは、福井県の若狭町にある神宮寺で行われる伝統的な祭りで、3月2日に開催されます。この祭りは、奈良県の東大寺で行われる「お水取り」の行列に水を送る儀式として知られています。お水送りの水は年中行事として奈良の二月堂に送られ、それが一年の終わりと新しい年の始まりを象徴する行事として結びついています。
Q6 : 3月3日に日本で祝われる「ひな祭り」は、どのような別名を持っているでしょうか?
ひな祭りは3月3日に女の子の健やかな成長と健康を願って祝う日本の伝統行事で、「桃の節句」とも呼ばれています。「桃」は古来より邪気を払うとされ、春の訪れを告げる花の一つとして祝祭に用いられています。桃の節句は、江戸時代以降、ひな人形を飾ったり、ちらし寿司やはまぐりの吸い物を食べるなどの風習が定着し、現代まで継承されています。
Q7 : 3月に行われる世界的な行事「聖パトリックの祝日」はどの国の守護聖人を祝う日でしょうか?
聖パトリックの祝日は、アイルランドの守護聖人である聖パトリックを祝う祝日です。キリスト教の宣教師であり、多くの奇跡の伝説で知られる聖パトリックが亡くなった日とされる3月17日に祝われます。この日は緑色の服を着たり、シャムロック(三つ葉のクローバー)を身につける習慣があり、現在では世界中で多くの人々に祝われる国際的なイベントになっています。
Q8 : ホワイトデーは3月14日に祝われますが、どの国が発祥でしょうか?
ホワイトデーは、日本で発祥した行事で、1978年に福岡市の製菓業者がバレンタインデーのお返しの日として開始しました。当初は「マシュマロデー」として始まりましたが、後にキャンディや他のスイーツも贈られるようになり、名前も「ホワイトデー」と変わりました。今では日本だけでなく、韓国や台湾など一部のアジア諸国でも祝われています。
Q9 : 春分の日は3月に含まれていますが、日本の国民の祝日として定められたのは何年でしょうか?
春分の日は、日本で国民の祝日として1948年7月20日に制定されました。この日は、昼と夜の長さがほぼ等しくなる日で、自然をたたえ、生物をいつくしむ日とされています。春分の日は、日本だけでなく多くの国や文化で季節の変わり目として重要視されており、新しい取り組みや人生の節目に位置付けられることもあります。
Q10 : 3月は日本の暦でどのような名前で呼ばれているでしょうか?
3月は、日本の旧暦で「弥生(やよい)」と呼ばれています。弥生という名称は、草木が芽吹き始める季節を意味しています。春の訪れを感じさせる言葉で、古来より3月を特徴づけるものとなっています。このように、日本の月の名前には自然や季節の変化が反映されており、伝統的な文化や生活習慣と密接に結びついています。
まとめ
いかがでしたか? 今回は3月クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は3月クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。